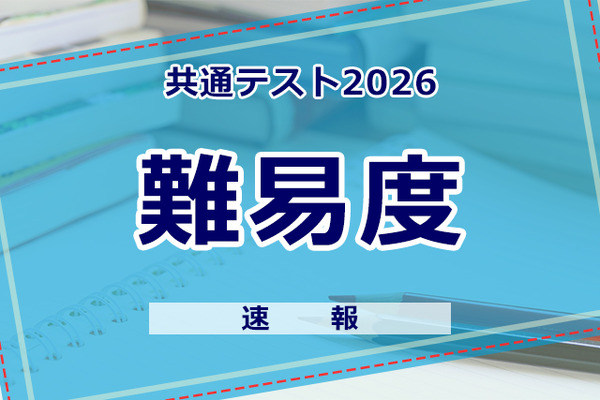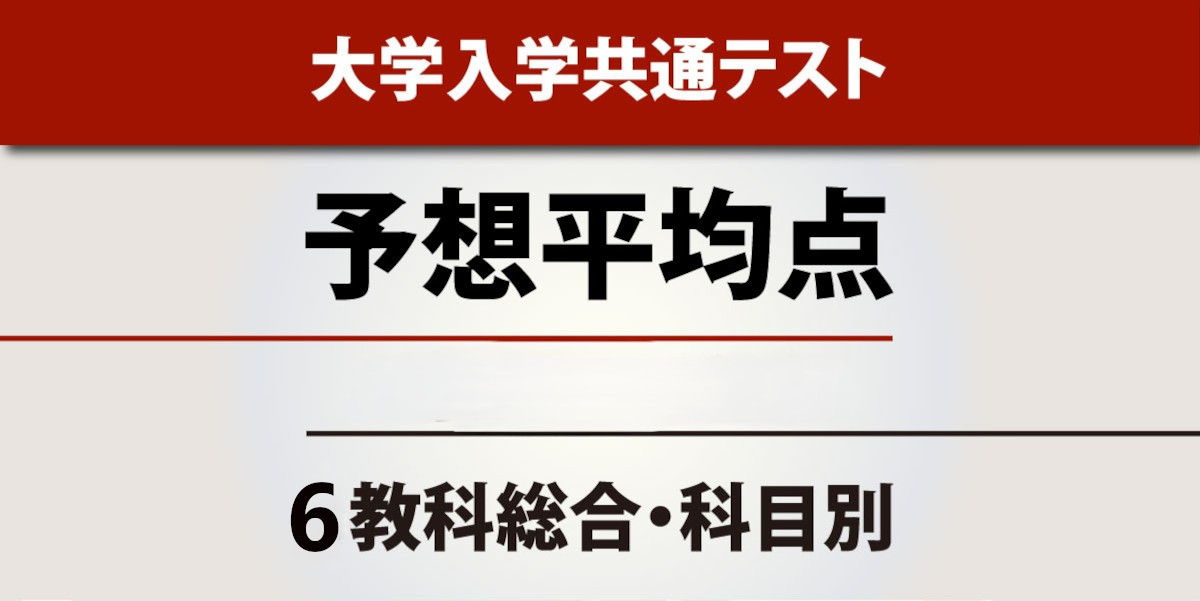コラム:円安加速に2つの要因、警戒すべき参院選後の「日本売り」=佐々木融氏

[東京 17日] - 7月に入ってから、日本の長期金利が上昇しながら円が売られるという流れが続いている。つまり、日本国債と円の両方が売られている。株式市場をみても、アジア株や米ナスダック総合指数などが堅調な一方、日経平均株価は下落している。いわゆるトリプル安となっており「日本売り」のような動きとなっている。
背景として考えられる要因は二つある。
一つめは、今週末の参議院選挙で自民・公明党の連立与党が参議院でも過半数を確保できない可能性が意識され始めていることだ。仮に過半数を確保できたとしても、ギリギリの状況では政策はポピュリズム的な方向に傾くことになり、消費税減税や現金給付などにより財政赤字拡大・政府債務残高増加となる可能性が高まる。
日本のインフレ率(消費者物価指数前年比)は主要7カ国(G7)の中で最も高い状態が既に7カ月も続いている。インフレ率が3%台半ばなのに10年国債金利は1.5%台にとどまっており、財政支出拡大懸念がなくても長期金利は上昇しやすい。加えて、各党ともインフレ率が高いという問題に減税や現金給付で対処しようとしている。こうした政策は結果的にインフレを助長させることになる。また、インフレ率上昇は円という通貨の価値が下落していることを意味し、他通貨に対する円安がさらにインフレ率を押し上げ、結果的に日本の金利を更に押し上げることになる。ちなみに、自民党は2040年度までに名目GDPを1000兆円にするという目標を掲げているが、今後日本のインフレ率が現状レベルで推移するだけで目標は達成できる。
二つめの要因は、日米通商交渉の解決のめどが見えないことだろう。日本は最終的には対米直接投資を一段と積極的に行うことや、米国からの財の輸入増加による対米貿易黒字縮小、つまり日本全体の貿易赤字拡大という形で米国との合意を結ばなければならないと考えられる。これらの合意は当然円売りを増加させることになるため、為替市場では円安が進みやすくなる。また、交渉が長引くことによって日本からの輸出が減少しても、結局日本の貿易赤字は拡大するので、同じく円安要因となる。仮に参院選の結果を受けて石破内閣退陣ということにでもなれば、日米交渉は振り出しに戻ってしまい、状況はますます悪化するだろう。
こうした二つの要因が重なったことで、日本国債、円、日本株が売られる「トリプル安」という現象になっていると考えられる。もっとも、今のところはまだ「日本売り」と呼ぶほどの事態にはなっていないだろう。円について言えば、現状の円売りは、歴史的水準まで積み上がっていた投機筋の円ロング(買い持ち)ポジションの手仕舞いが進んでいることが背景にある。つまり、積極的に円を売っているというより、買っていた円の売り戻しを余儀なくされている状況だ。シカゴ通貨先物市場を通じた投機的円ロングポジションとドル/円相場の5月以降の相関関係が維持されると仮定すると、円ロングポジションが全て手仕舞われたらドル/円相場は155円近辺まで上昇することになる。
「日本売り」のリスクが懸念されるのは、投機筋の円ロングポジションが手仕舞われた後だろう。投機筋が過去最高の2倍の水準まで円ロングポジションを膨らませてもドル/円相場は140円程度までしか下落しなかった。つまり、円のファンダメンタルズは弱いままである。トランプ米大統領が高率の相互関税を発表した4月2日以降でみると、主要通貨の中で最弱通貨はドルだが、それと大差なく2番目に弱い通貨は円だ。その結果、対スイスフランで円は史上最安値を更新、対ユーロでは1年ぶりの安値を更新し、ユーロ発足以来の円の安値まであと1%ちょっとだ。
今後、本格的に「日本売り」がテーマとなり、投機筋が同じ勢いで今度は円売りを仕掛けてきたら、円の下落が加速してしまう可能性がある。今や日本はエネルギー、食料、医薬品といった生活必需品の貿易赤字が膨らんでいるため、円安になってこれらの生活必需品が割高になっても、円を売って輸入せざるを得ない。米国企業から購入しているデジタル関連のサービスももはや準生活必需品と言えるかもしれない。昨年の貿易・サービス収支の赤字は6兆円を超えていた。
日本企業は対外直接投資を続けるだろう。石破首相はトランプ米大統領と対米直接投資の大幅増加を約束しており、これも実行せざるを得ない。日本企業は昨年ネットで30兆円近くの対外直接投資を行っているが、今後は対米直接投資を中心に金額がさらに増えてくるかもしれない。
インフレ率の高止まりと低金利で、持っていると実質的に目減りする銀行預金から外国株投信への資金シフトもさらに進むかもしれない。家計は今でも1000兆円以上の現金・預金を保有しており、毎日200─300億円が外国株投信に向けて流れている。これが1年間毎日続いても1000兆円の1%にも満たない。外国株投信への流出額が倍増しても不思議ではない。
そんな時に、日本が格下げされたら事態はさらに悪化する。米国との通商交渉が行き詰まっている状況は、政治的に日本が格下げされるリスクを高めるかもしれない。日本が格下げされれば国債も多少は売られるだろうが、それよりも危険なのは日本の銀行の外貨調達に支障を来す場合だ。邦銀の海外支店貸出は100兆円以上となっており、90年代後半のジャパン・プレミアム発生時よりも大きい。外貨調達に支障をきたした場合、結果的に誰かが円を売って外貨を購入しなければならなくなる可能性がある。
ドル/円相場が再び160円に近づけば、ドル売り・円買い介入が意識されるかもしれない。しかし、日本の外貨準備は160兆円程度しかない。前述の様々な潜在的な円売り額と比べるといかに小さいかがわかる。当然のことながら全て使うわけにもいかない。24兆円も費やした後すぐに元の円安水準に戻ってしまったと市場が認識したら、そこからさらに投機筋の円売りアタックが始まるかもしれない。次に円買い・ドル売り介入が行われる時は、22年や24年の時とは全く異なるレベルの緊張感で円相場の動向を見ることになるかもしれない。
編集:宗えりか
*本コラムは、ロイター外国為替フォーラムに掲載されたものです。筆者の個人的見解に基づいて書かれています。
*佐々木融氏は、ふくおかフィナンシャルグループのチーフ・ストラテジスト。1992年上智大学卒業後、日本銀行入行。調査統計局、国際局為替課、ニューヨーク事務所などを経て、2003年4月にJPモルガン・チェース銀行に入行。2010年にマネージングディレクター就任、2015年から2023年11月まで同行市場調査本部長。23年12月から現職。著書に「弱い日本の強い円」、「ビッグマックと弱い円ができるまで」など。
*このドキュメントにおけるニュース、取引価格、データ及びその他の情報などのコンテンツはあくまでも利用者の個人使用のみのためにコラムニストによって提供されているものであって、商用目的のために提供されているものではありません。このドキュメントの当コンテンツは、投資活動を勧誘又は誘引するものではなく、また当コンテンツを取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。当コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供せず、また、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません。このドキュメントの使用は、資格のある投資専門家の投資助言に取って代わるものではありません。ロイターはコンテンツの信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、コラムニストによって提供されたいかなる見解又は意見は当該コラムニスト自身の見解や分析であって、ロイターの見解、分析ではありません。
私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」, opens new tab