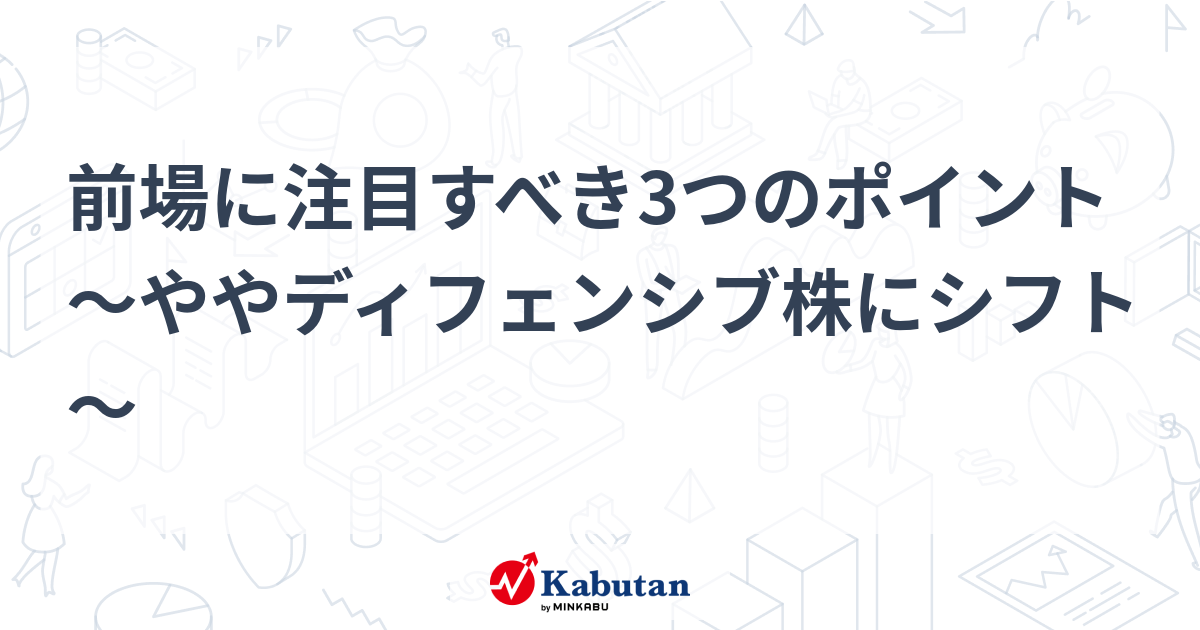黒田緩和2年も遠い物価2%、副作用に警戒感-15年上期・日銀議事録

日本銀行は16日、2015年1-6月の金融政策決定会合の議事録を公表した。大規模緩和の導入から2年が経過しても物価目標の実現が遠い中、黒田東彦総裁(肩書は当時、以下同)は、基調は高まっているとして政策効果を強調する。一方で、政策委員の中に副作用への警戒感が広がり始める。
「物価の基調は着実に高まっていることから、2年程度の期間を念頭に置いて、できるだけ早期にというコミットメントに沿った動きになっている」。黒田総裁は、消費者物価(生鮮食品を除くコアCPI)見通しを下方修正し、2%の物価安定目標の実現時期を先送りした4月30日の会合で語った。
13年4月に「2%の物価目標を2年程度で実現する」と黒田総裁が宣言してスタートした量的・質的金融緩和だが、2年後もコアCPIはゼロ%程度で推移していた。一方で正副総裁を中心に、予想物価上昇率などを反映する「物価の基調」は高まっているとし、16年度にはコアCPIが2%に達する見通しを経済・物価情勢の展望(展望リポート)で示した。
現在の植田和男総裁は、利上げを急がずに緩和的な金融環境を続ける根拠に、基調的な物価上昇率が2%に達していないことを挙げている。3%超の物価上昇が続く現在と当時の環境は真逆と言えるが、金融政策のコミュニケーションが難しくなる局面では、外部から具体的な数値が見えない「物価の基調」が多用される傾向にあるようだ。
「2年で2%」のコミットメントに関し、中曽宏副総裁は同じ会合で、「目標実現時期の遅れを極力短くする」ためにも重要だとの見解を表明。黒田総裁もコミットメントを変更する必要はないと応じるが、その後も目標達成時期は先送りが繰り返されることになる。
副作用
大規模緩和が長期化する中で、副作用への懸念が次第に強まっていく。木内登英審議委員は4月7、8日の会合で、マネタリーベースと長期国債の保有残高の増加ペースについて、当時の年間80兆円から同45兆円に減額する議案を提出したが、反対多数で否決された。
木内氏は、大規模緩和の「副作用にも十分注意を払いながら、効果と副作用のバランスを最善のものにすることを目指すことが重要だ」と説明。副作用として、国債市場で日銀の存在が過大になっていることによる市場機能の低下や金融機関の収益・仲介機能への影響、財政健全化のインセンティブの低下などを挙げた。
これに対し、金融緩和に積極的なリフレ派の岩田規久男副総裁と原田泰審議委員が反論する。岩田氏は4月30日の会合で、潜在成長率を重視する木内氏に対して「潜在成長率を金融政策では動かせないとすると、木内委員は、一体、ここに何をしにいらっしゃったのかということになる」と皮肉交じりに述べている。
緩和長期化
6月18、19日の会合では森本宜久審議委員が、当初のもくろみよりも大規模緩和の実行期間が長くなり、規模も格段に膨らんでいくことは否定できないと懸念を示す。現在の金融緩和政策は量・質の両面から市場に極めて強いインパクトを持つ異次元の政策とし、「本来長く続けていくことに、多くの難しさをはらんだ政策ではないか」との見解を示した。
同じ会合で佐藤健裕委員が日銀のコミットメントだけで「人々の予想物価上昇率を押し上げていけるかは不確実性がある」と指摘したように、物価の基調に強まりが感じられない状況が続く。原油価格も下落を続け、コアCPIは再びマイナス圏に沈む。日銀は16年1月にマイナス金利政策の導入に踏み切るが、賛成5・反対4という僅差での決定だった。