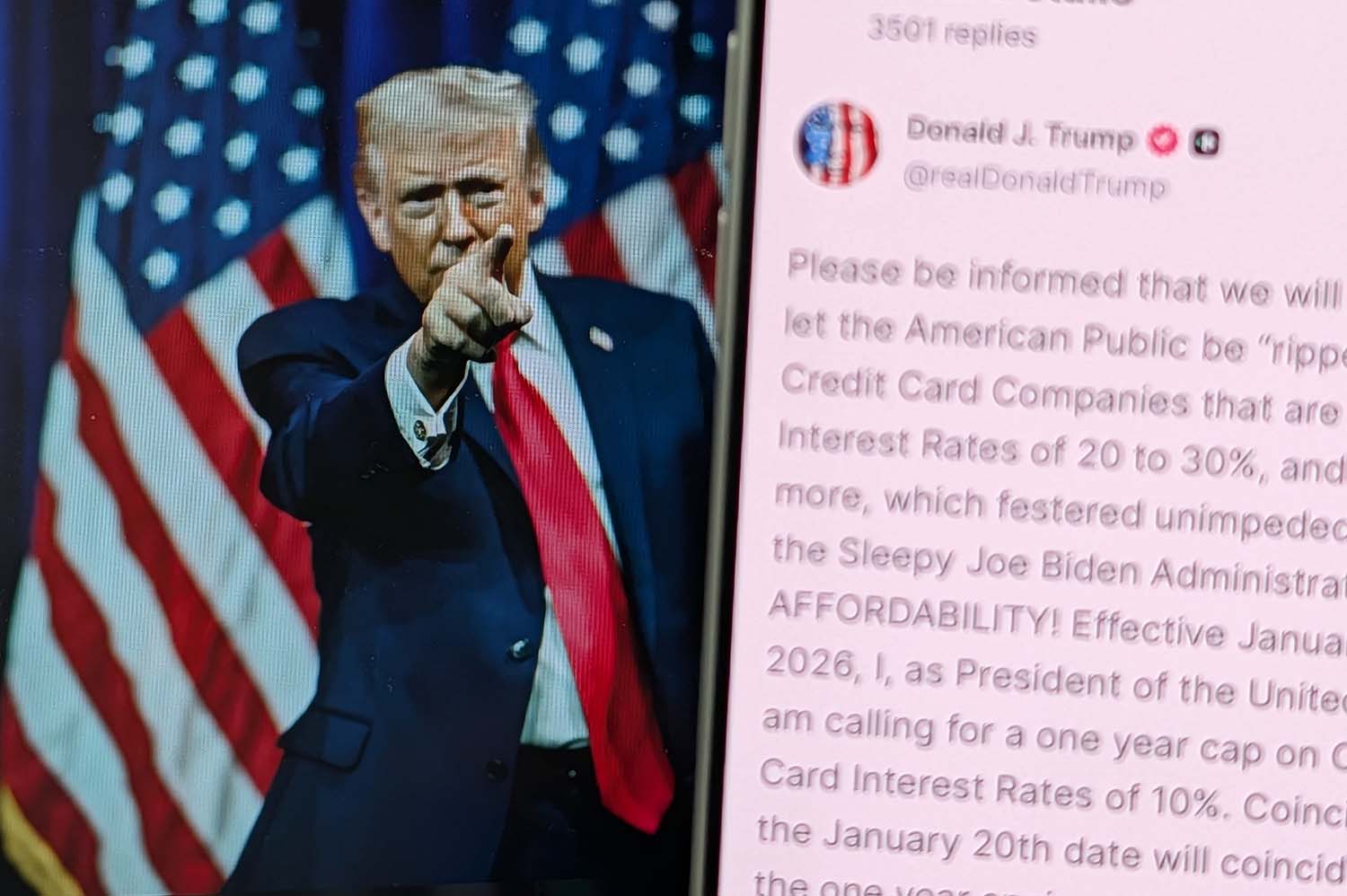盗まれる日本食ブランドを守れ マスカット、日本酒…偽装見破る「バイオ指紋」で鑑定

昨年12月、国連教育科学文化機関(ユネスコ)の無形文化遺産に日本酒などの「伝統的酒造り」が登録された。日本の「食」の魅力が海外で知られると同時に、銘柄などのブランド偽装被害も後を絶たない。背景には知的財産権に対する日本人の認識の甘さがあり、商標登録の徹底や原産地表示の保護、偽装を見破る技術開発という官民一体の取り組みが急務だ。
訪日客が交流サイト(SNS)で発信している効果もあり、世界は空前の日本食ブームだ。2023年度食料・農業・農村白書によると、農林水産物・食品の輸出額は18年の9068億円から23年に1兆4541億円となり過去最高を更新した。
しかし、特許庁の調査によると、20年の世界での模倣品被害額は食品で741億円、日本企業の輸出額の約9・6%に上った。日本酒などアルコール飲料の416億円と合計すると被害額は1157億円に上る。
日本で育成された高級ブドウ「シャインマスカット」は苗木が流出し、中国で栽培が拡大した。東南アジアでも「中国産」「韓国産」として流通。生産量から推計した許諾権料の損失だけで年間100億円とされる。
日本ブランドを冠した日本産ではない商品も「もぐらたたき」のように出現している。電子商取引(EC)サイトに出される米国産の牛肉が「KOBE BEEF」と表示される事例もある。日本酒の業界関係者は「本数の少ない有名な地酒など希少で高額な銘柄がターゲットになっている」と話す。ネットオークションにも日本産ウイスキーの偽物と疑わしい商品が出回る。
農林水産省は23年度、世界の179のECサイトを検索し、不正な「日本産」商品1242件を発見。サイト管理者に削除を要請し、翌年2月までに611件を削除した。
政府は1995年に酒類で、2015年6月からは農林水産物で「地理的表示(GI)」の制度を創設した。「名称から産地と特性を特定できる場合」にGIとして登録するもので、他の産地や特性の商品はその名称を名乗れない。GIに登録されているのは酒類で「灘五郷(清酒)」「和歌山梅酒」など昨年12月現在で27カ所。農林水産物では「京賀茂なす」「神戸ビーフ」など、今月18日現在で計161産品。
GIは協定を結んだ外国との間で、相手国の商品とともに相互に保護される。現地では権利者が無断栽培を差し止め、損害賠償を請求できる。農水省の担当者は「在外公館や民間と協力し、不正があった場合は現地当局に情報提供して対応を働きかけている」と話す。
苗や種の流出などに対して政府は法規制を強化しているが、生産者や企業もGIなどの商標登録の徹底が急務だ。同白書は「(日本では)農業分野における知的財産としての価値に対する認識や知識が十分ではなく、無断流出につながっている」と指摘する。
ブランド保護は海外ビジネスを成功させる鍵でもある。日本大の下渡敏治名誉教授(国際フードシステム論)は「食品の産地や生産方法について特に欧米の消費者は厳しく、企業はきちんとした情報公開でブランドを確立しなければ商品を売れない」と話す。
フランスの日本酒コンクール審査員や日本の酒蔵関係者らの交流会で並べられた日本酒や焼酎=2023年2月、東京都千代田区数百メートル離れた土でも違う同位体元素
GIなどの商標登録を行っても、海外で栽培が広まってしまったシャインマスカットのような事例では、本物かどうかをDNAで見分けることができない。日本酒などがラベルを貼ったままびんの中身を入れ替えられた場合も同様だ。
近年はIT技術を駆使した対策が進む。商品に付けられた2次元コードや近距離無線通信(NFC)タグにスマートフォンをかざすと、生産者情報を確認できる。酒のびんの首に付けたNFCは開封するとクラウドに記録され、中身の入れ替え防止に役立つ。
しかし、2次元コードやNFCタグでも書き換えることが可能で、偽のサイトに誘導される事例が実際に生じている。
株式会社の日本流通管理支援機構(東京)はダイヤモンドの鑑定技術を応用。果実や酒に含まれる水や養分を、同位体(同じ元素でも中性子の数が異なる)の分析など複数の手段で確認することで、その地域にしかない「バイオ指紋」をつくる。数百メートル離れた畑でも土に含まれる同位体元素が異なり、酒蔵ごとに水の同位体が違ってくる。
同社の佐野正登社長は「バイオ指紋をデータベース化すれば、世界のバイヤーや消費者が買おうとしている農産物や酒を分析し、本物を扱っているのかを確認できるようになる」と話す。
ただ同社の場合、同位体解析は1商品50万円~150万円と高額。農林水産省所管の農林水産消費安全技術センター(FAMIC)も同位体解析を手掛ける。政府が民間と連携して、偽装対策を科学的側面から進めることも課題となっている。
フランスワインのAOC、柔軟性に課題も
GI保護制度の元祖は、欧州有数の農業国フランスだ。ワインで偽装が横行していたことから、1935年に「原産地呼称統制(AOC)」が創設された。55年にチーズを対象とする法律が制定され、90年にその他の加工品や水産物、畜産物に対象が拡大した。
生産者が組織する団体などが申請し、国立原産地名称研究所(INAO)が審査。その後、産地関係者以外で構成する委員会でさらに審査し、全国委員会で最終判断を下す。申請から認可まで5~10年かかるほど厳しい基準が適用される。
特にワインは気候や土壌、醸造の仕方などで特徴がさまざまに変わるため、ワイナリーの個性を守るためにAOCが適用されている。たとえば「シャンパン」は北東部のシャンパーニュ地方で伝統的な製法でつくられた発泡性ワインに限定した呼称とされる。
ただ長い時間がたつうちにAOCが適用されるワインの品質が必ずしも維持されなかったり、AOCの範囲外のワインで良質なものが生まれたりするといい、現状を踏まえた柔軟な運用の必要性も指摘されている。(牛島要平)