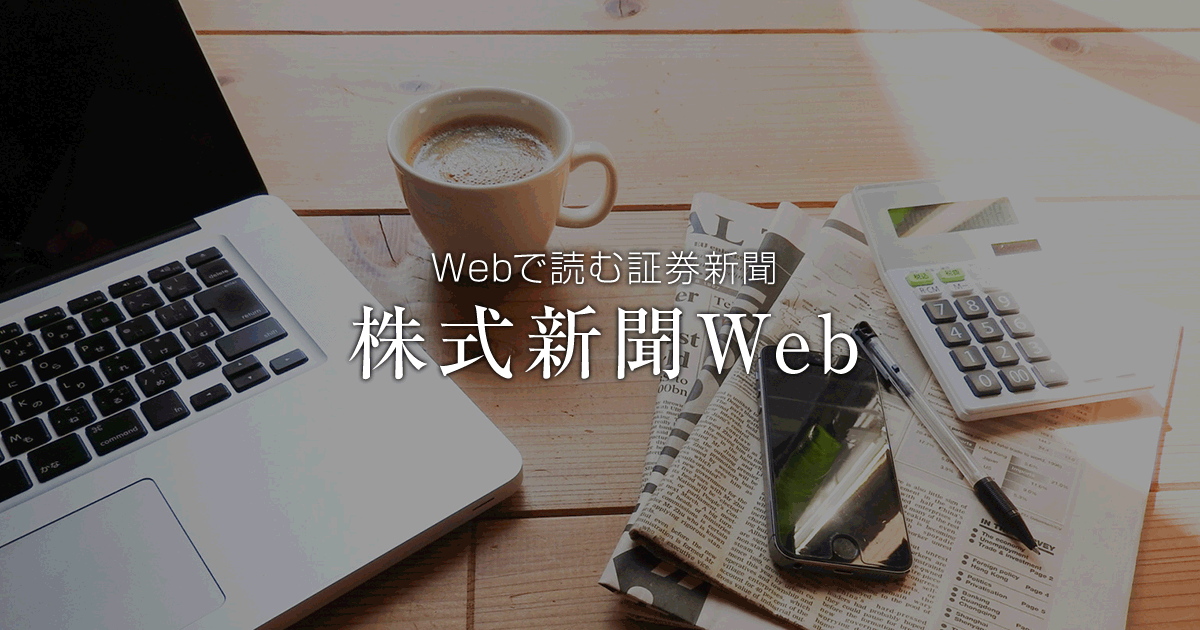コラム:利上げが円高を招く条件とは、日銀決定を巡る論点整理=内田稔氏

[東京 28日] - 1月24日、日銀はマイナス金利解除以来、3度目の利上げに踏み切った。これで政策金利は0.5%となり、2008年以来17年ぶりの水準に達した。記者会見で植田和男総裁は「実質金利が極めて低いことから、引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和度合いを調整していく」考えを示した。このように今後とも日銀の利上げが見込まれる一方、その妥当性を巡り、様々な声が聞かれるほか、利上げが円高をもたらす効果や程度についても為替市場での評価は分かれている。本稿では日銀の利上げに関するいくつかの論点を整理した上で、利上げが円高を招く条件を整理しておきたい。
<消費低迷下での利上げの妥当性>
昨年来、個人消費に弱さがみられる中で、利上げを疑問視する声が根強い。しかし個人消費低迷の一因は実質賃金の前年割れにあり、それは交易条件の悪化、すなわち過度な輸入物価上昇の結果である。従って消費テコ入れには、歴史的な円安と輸入インフレを抑える必要があり、利上げはその一助となるはずだ。また植田総裁も発言した通り、利上げ後もインフレ率を差し引いた実質政策金利は大幅なマイナス圏にとどまり、緩和的な金融環境が続く。
テレビ東京と日本経済新聞社が27日に発表した世論調査によると、「処理して欲しい政策課題」の筆頭に「物価対策」が挙げられたほか、日銀の追加利上げを「評価する」との回答が54%と、「評価しない」の34%を上回った。家計において、「利上げやむなし」との見方が広がっている可能性がある。
<住宅ローン金利上昇への対処法>
利上げに関する報道の中で、変動金利型住宅ローンの借り入れコストの増加を理由に、景気への悪影響を懸念する声が多い。しかし、昨年9月時点における家計の金融資産は約2179兆円であり、住宅ローンを含む負債額の392兆円を大幅に上回る。家計全体でみれば、金利上昇はむしろ受取利息の増加につながる。もちろん、一般的に言えば預金金利よりも住宅ローン金利の引き上げ幅の方が大きい。また、金融資産がシニア層に偏在する一方、住宅ローンを抱えているのは多くの場合、現役世代であり、利上げの恩恵には世代間格差もみられよう。その場合、例えば住宅ローン減税の拡充といった財政面での対応を組み合わせることで、日銀は物価情勢にフォーカスした金融政策運営を進めやすくなるはずだ。
<コストプッシュ型インフレにも利上げが必要>
輸入インフレのようなコストプッシュ型のインフレに対する利上げの妥当性を問う声も少なくない。ただ、結論を言えば、その場合でも利上げで対応せざるを得ないだろう。これはインフレの理由がどうであれ、インフレを許せば、各経済主体の中銀に対する信認が低下し、インフレ期待がさらに膨らむためだ。その結果、消費や投資が前倒しで実施され、自己実現的なインフレを招く危険性も高まる。
既に、生鮮食品を除く消費者物価の総合指数は物価安定目標である2%を33カ月続けて上回っており、市場のインフレ期待であるブレークイーブン・インフレ率(10年物の国債と物価連動債の金利差)は1月27日、1.6%台に達し、過去最高を記録した。日銀の「生活意識に関するアンケート調査(調査期間11月7日─12月3日)」でも、「1年後の物価は現在と比べ、何%程度変化すると思うか」との問いに対する回答の平均値が11.5%、中央値も10.0%と、ドル/円が160円を超えていた時期に実施された前々回の調査時に再び並んだ。「日本銀行を信頼しているか」の問いに対しては、「信頼している」が前回調査から3.9%ポイント低下した。コストプッシュ型のインフレでも、ここ数年の海外中銀同様、日銀も基本的に利上げで対応せざるを得ないだろう。
<円安抑制策としての利上げ>
今回の利上げ判断を円安、すなわち為替レートに背中を押されたものとして、批判する声もある。実際、利上げを見送った昨年12月会合において植田総裁が利上げに向けて「もうワンノッチほしい」と慎重な見方を示したことから、市場は3月利上げとの見方に傾斜しつつあった。従って、今回の利上げの背景に年明け以降、一時159円に迫ったドル/円の上昇があるかも知れない。しかし、多くの食料やエネルギーを輸入に依存する日本において金融政策と為替レートを切り離して考えることの方がむしろ不自然でさえある。植田総裁も「過去と比べると為替変動が物価に影響を及ぼしやすくなっている面がある」と発言した。今後とも日銀が円安の加速に背中を押されて、利上げ判断を迫られる場面があってもそれほど不思議ではない。
<利上げの天井は1%程度なのか>
植田総裁は、「先行き次第だが、実質金利が極めて低い水準にあることを踏まえると(中略)引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整していくことになる」と発言した。日銀は今後も利上げを続ける構えであり、利上げの最終的な到達地点(天井)に関心が寄せられる。その点、24年9月12日、田村直樹審議委員が講演の中で、その水準として「1%程度」と示した。短期の中立金利に関し、「経済・物価に対して中立的な実質金利の水準である自然利子率に、予想物価上昇率を加えたもの」と、フィッシャー方程式を用いて説明したものだ。
現在、日本の自然利子率はマイナス1.0%からプラス0.5%とされ、これに日銀の物価安定目標である2%を加えると政策金利の天井は最低でも1.0%となる。今後のインフレ次第だが、早ければ今年度中にも日銀はあと2回の追加利上げを行うだろう。ただ、24年同様、実質金利がマイナス圏にとどまる限り、円安と輸入インフレ圧力が残る可能性がある。その上、ホームメードのインフレを示すGDPデフレーターが8四半期続けてプラスを示している通り、輸入インフレが幅広いモノやサービスのインフレへと波及しつつある。この為、利上げの天井が「1%程度」よりも高くなる可能性にも十分、留意すべきである。
<利上げが円高を招く条件>
最後に、24年の動きを踏まえ、利上げが円高を招く条件を整理しておく。まず、利上げが続いた場合でも、実質政策金利がマイナス圏にとどまる限り、円の反発力は鈍いだろう。このため、円高が進むとすればインフレ率よりも高い水準まで政策金利が引き上げられる場面だ。もっとも、そうした金融引き締めに至るには、政府によるデフレ脱却宣言が必要とみられ、現時点でそのハードルは高いと考えられる。
次に、日銀が利上げを続ける一方、海外中銀が利下げを重ねる場合でも、それに長期金利の動きが連動しない限り、円高とはなりにくい。例えば昨年の場合、年終盤にかけてトランプ政権の財政拡張策が意識された結果、米国の長期金利が上昇し、日本を含む多くの長期金利上昇に影響した。従って、円高には金融緩和と歩調をそろえた海外の長期金利低下が求められる。とは言え、米国の長期金利は依然としてインフレ期待やタームプレミアムの双方による上昇圧力を受けやすく、円高を阻みそうだ。
最後に、為替相場が相対比較である点も重要だ。円高の条件がそろわない場合でも、他通貨が下落すれば相対的な円の持ち直しに通じる。前回のコラムで指摘した通り、米経済の急失速やフランス国債の格下げがあれば、ドル安やユーロ安を支えに円が相対的な強さを取り戻す。引き続き単なる金融政策の方向の違いだけではなく、幅広い視点で円相場を展望する必要がある。
編集:宗えりか
(本コラムは、ロイター外国為替フォーラムに掲載されたものです。筆者の個人的見解に基づいて書かれています)
*内田稔氏は高千穂大学商学部教授、株式会社FDAlco外国為替アナリスト、公益財団法人国際通貨研究所客員研究員、証券アナリストジャーナル編集委員会委員、NewsPicks公式コメンテーター(プロピッカー)。慶應義塾大学卒業後、東京銀行(現・三菱UFJ銀行)に入行し、マーケット業務を歴任。2012年からチーフアナリストを務め、22年4月から高千穂大学商学部准教授、24年4月から現職。J-money誌東京外国為替市場調査では2013年より9年連続個人ランキング1位。国際公認投資アナリスト、日本証券アナリスト協会認定アナリスト、日本テクニカルアナリスト協会認定テクニカルアナリスト、経済学修士(京都産業大学)。YouTubeチャンネル「内田稔教授のマーケットトーク」では解説動画を公開している。
*このドキュメントにおけるニュース、取引価格、データ及びその他の情報などのコンテンツはあくまでも利用者の個人使用のみのためにコラムニストによって提供されているものであって、商用目的のために提供されているものではありません。このドキュメントの当コンテンツは、投資活動を勧誘又は誘引するものではなく、また当コンテンツを取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。当コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供せず、また、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません。このドキュメントの使用は、資格のある投資専門家の投資助言に取って代わるものではありません。ロイターはコンテンツの信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、コラムニストによって提供されたいかなる見解又は意見は当該コラムニスト自身の見解や分析であって、ロイターの見解、分析ではありません。
私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」, opens new tab