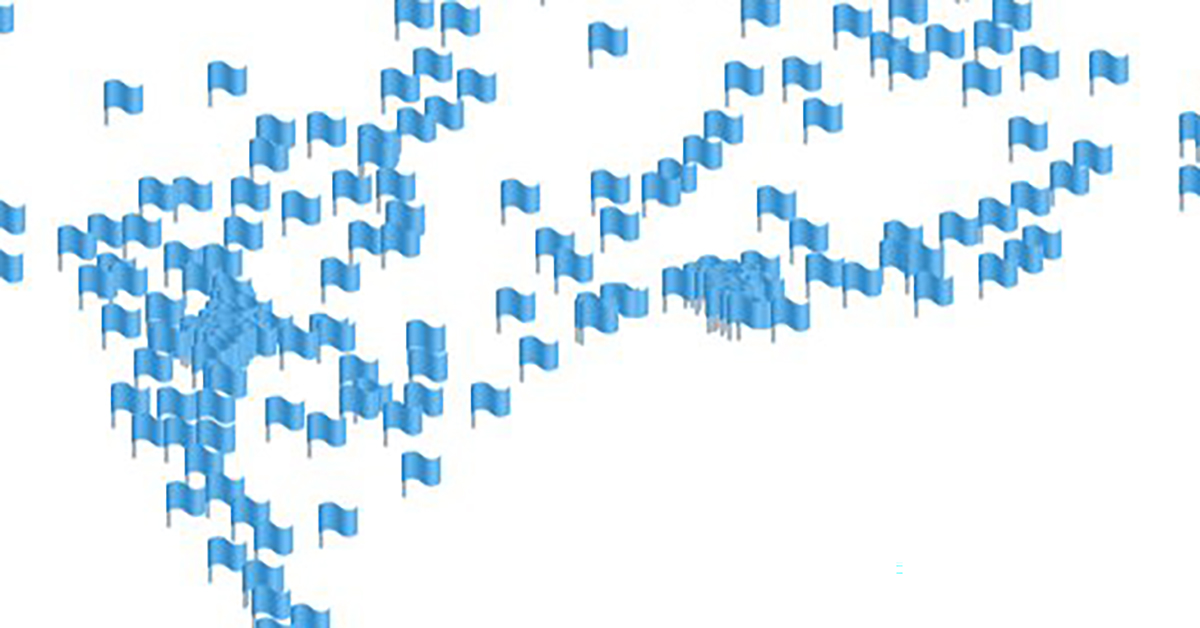血糖値を下げるには3度の食事よりこれが大事…糖尿病専門医が真っ先に見直しを命じる食べ物と飲み物の種類 極端な炭水化物制限は死亡率を上げる
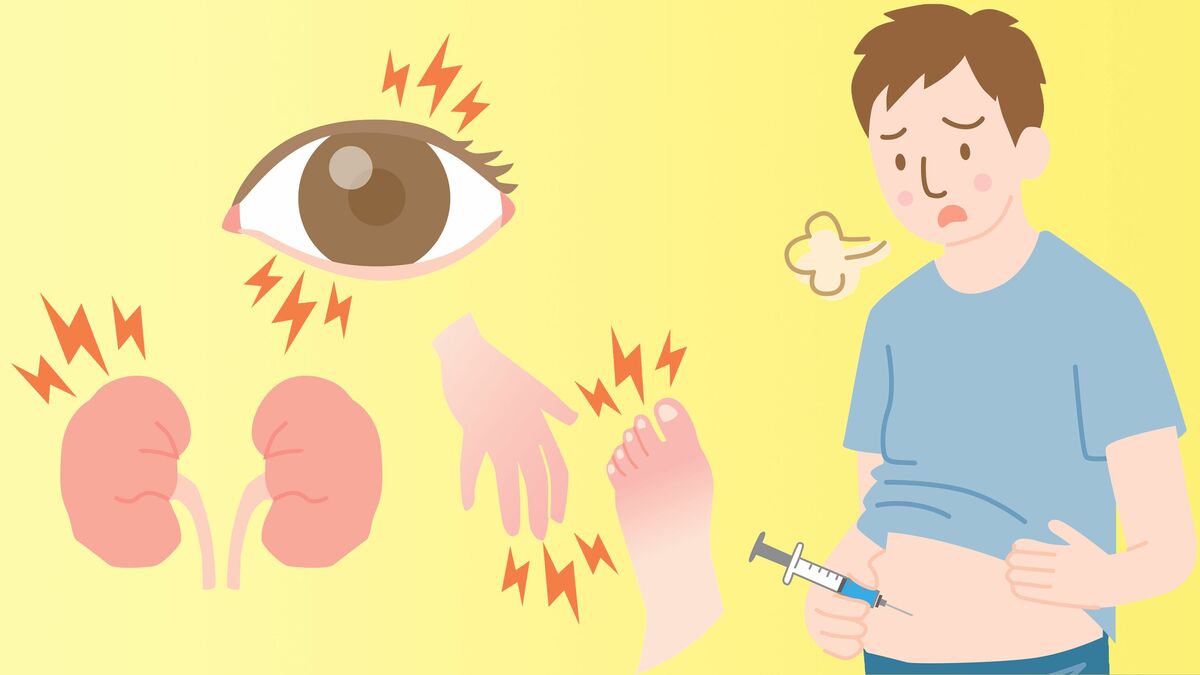
さまざまな合併症を引き起こす糖尿病。予防するにはどうすればいいか。鳥取大学病院内分泌代謝内科で糖尿病専門医の大倉 毅医師は「食事に気をつけるのも大事だが、その前に取り組むべきことがある」という――。
※本稿は、鳥取大学医学部附属病院広報誌『カニジル 18杯目』の一部を再編集したものです。
写真=iStock.com/simpson33
※写真はイメージです
糖尿病増加の背景にライフスタイルの変化
糖尿病患者が著しく増えている。
「日本人のだいたい5人に1人が、糖尿病かその予備軍だと考えられています。成人も子どもも含めての話なので、成人だけに限れば4人に1人。
糖尿病有病率の変化と見事に比例しているのが、コンビニの店舗数、外食産業の市場規模、一人世帯の割合、そして自動車保有台数などの増加。24時間365日、いつでも好きなものを食べて飲めるようになったこと、そして運動不足が原因だと思われます」
糖尿病増加の背景にはライフスタイルの変化があると指摘するのは、とりだい病院内分泌代謝内科の医師であり、糖尿病専門医の資格を持つ大倉 毅だ。
厚生労働省が2019年に行なった調査によると、糖尿病患者が1000万人、予備軍を含めると2000万人と推計している。この数字は年間15万人ペースで増えており、今も継続していると思われる。
そもそも、「糖尿病」とは何か――。
インスリンという膵臓でつくられるホルモンがある。私たちの身体は僅かな血糖値の変動を察知すると、膵臓からインスリンを分泌して血糖値を一定に保っている。
糖尿病とは、インスリン不足、あるいはインスリンに対して身体の反応が鈍くなる「インスリン抵抗性」が原因で起こる。
Page 2
糖尿病の治療薬にはいくつか種類があり、一人ひとりの症状に適したものを選択して使用する。中でも比較的新しい薬である「GLP-1受容体作動薬」はインスリン分泌を促進し、高い血糖値改善効果がある。
「GLP-1受容体作動薬は痩せる効果が強いので、最近まで美容目的のダイエット薬としても出回っていました。専門医の指導のもとで適切に使用しないと副作用の懸念があるため、健康被害が社会問題になっています。現在は処方が規制されているものもありますが、ネットなどで入手して安易に使用するのは非常に危険」
薬物療法で十分な改善が見られないとき、あるいは1型糖尿病の患者にはインスリン注射が必要になる。
毎食前と寝る前に、患者自身で毎日4回ほどインスリンの皮下注射を打つ。最新のインスリンポンプという医療機器では、装着したセンサーで血糖値を測り、必要な量のインスリンを自動で調整してくれる機種も出ている。問題は高額なため導入できる人が限られる場合もあることだ。
「初期は自覚症状に乏しいのが糖尿病の特徴です。血糖値が上がっていても、ほとんどの場合は無症状。糖尿病は早期発見、治療をすれば、必ずよくなる病気です。定期健診を受けて、早めに治療を開始することが大事」
数値の目安は血糖値と、過去1~2カ月間の血糖値の平均を示すヘモグロビンA1c(HbA1c)という値である。
健康診断では見つかりにくい「かくれ糖尿病」を発見する検査
また、健康診断では見つかりにくい「かくれ糖尿病」(食後高血糖)を発見するためには、ブドウ糖負荷試験がある。
鳥取大学医学部附属病院広報誌『カニジル 18杯目』
これはブドウ糖を溶かした飲料を飲んで、その直後の血糖値の変動を測定して診断する。日本人は遺伝的にインスリン分泌が少ない人が多いため、早期発見にはこの検査は非常に有効だ。
しかし、こうした検査の受診には専門医の知見が必須だ。
「もし検査で血糖値に異常が見つかったときは、症状がないから大丈夫と自己判断をしないで、早めに糖尿病専門医を受診していただきたい」
糖尿病になったとしても、合併症が出るまでには5年から10年。自分の体の状態を正確に知り、軽いうちから治療を開始することで、病気の進行を抑えて合併症を予防することができるのだ。
(取材・文=西村隆平)