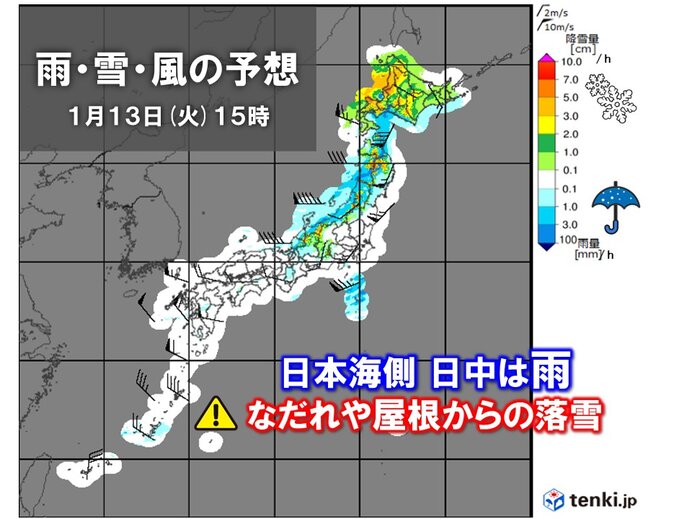路線バスに本物のスイッチやハンドルを備えた「こども運転席」…乗りたくなる工夫で地域の足守る

人口減少による利用者減や運転手不足で苦境に立たされているバス。しかし、長年愛されてきた地域の足を守ろうと、各地でさまざまな工夫や努力が重ねられている。バスの楽しさを未来へとつなごうと奮闘している現場を追いかけてみた。
アイデア路線 各地で運行
「発車しまーす」「右に曲がりまーす」
楽しそうにバスの車内で合図を出すのは、乗っている子ども。席の前にはなぜかハンドルが用意され、いろんなスイッチも付いている。
この「こども運転席」がある路線バスが走るのは千葉県山武市。「京成バス千葉イースト」成東営業所が運行する。
席の前にはモニターが取り付けられ、バス前方にあるカメラのリアルタイム映像を映し出す。ハンドルは本物の運転席同様、角度がなだらかで、スイッチ類も本物と同じものを使うこだわりよう。用意された子ども用の帽子をかぶることもできる。
4月下旬に乗車した、同市の小学1年生の女児(6)は「本当に楽しかった。また乗りたい」と笑顔だ。「子連れでバスに乗るのは何となくハードルを感じるが、こういう座席があると歓迎されているようで利用しやすい」という感想が保護者から寄せられたという。
バスはJR成東駅から山武市役所、病院などを周回し、住民の暮らしを支えている。「海岸線」という名前の通り、途中に海水浴場もあって、観光客も利用する。平日は1日9便、週末などは8便運行されるが、赤字路線で運行費を市が補助する。
そうした中、利用促進のアイデアとして、「バスの運転士体験」を同市の中学生が提案したことをきっかけに、2024年5月に「運転席」が設けられた。
営業所長の今井明彦さんは「混み合う路線ではないので、親子で写真を撮影したりして楽しめる。バスと触れ合うきっかけになれば」と期待する。
猪目窓がある「宇治茶バス」=京都京阪バス提供設備を工夫するバスはほかにも。「京都京阪バス」は、茶室のような「宇治茶バス」を京都府の宇治地域で運行している。
ハートのような形をした 猪目(いのめ) 窓が有名な寺院「正寿院」付近と京阪宇治駅を結ぶ路線で、バスの窓を猪目窓にしたほか、座席を畳張り風にし、手すりは竹を模している。土日祝日にこの路線を2往復し、観光客などを楽しませている。
岡山県内などで運行する「両備ホールディングス」は「宇宙一面白い公共交通」を目標に掲げ、乗って楽しいバスを数多く運行してきた。
コロナ禍で落ち込んだ22年に取り組みを始め、車内の天井をプラネタリウムにした車両や、押し放題の降車ボタンや取り放題の整理券発行機を取り付けた車両などを走らせてきた。取り組みの成果で、4割ほど客足が増えたバスもあったという。
現在は地元企業と協力し、余った布で子どもたちが作ったアート作品やヘッドレストカバーを使った車両を運行。乗ることで持続可能な開発目標(SDGs)を学ぶことができる仕掛けだ。
同社乗合バス統括部長の平本清志さんは「普段は車を運転する親がバスに乗れば、子どもとゆっくり話ができるなど、有意義な時間を車内で過ごすこともできる。乗ることを目的にしてバスを楽しんでもらいたい」と力を込める。
道路も線路も走れる 観光客に人気のDMV
線路を走るDMV(阿佐海岸鉄道提供)珍しい「バス」を走らせているのは、徳島・高知両県の海岸線を走る阿佐海岸鉄道だ。
見た目はおしゃれなマイクロバスだが、車体の下部にある鉄の車輪を出せば、そのまま鉄道の線路を走ることができる。「デュアル・モード・ビークル(DMV)」と呼ばれ、バスと鉄道車両が一体化している。乗客が乗ったまま切り替えが行われるため、何もしなくても二つの乗り物が楽しめる。
同鉄道によると本格的に営業運行しているのは世界中でも珍しいという。休日には満席になることもあり、9割以上が観光客だという。専務の大谷尚義さんは「新たな人の流れが乗り物で生まれている。次世代の公共交通にぜひ乗ってほしい」と話す。