シリーズ「がん新時代」① 発生と再発の元凶「がん幹細胞」とはなにか
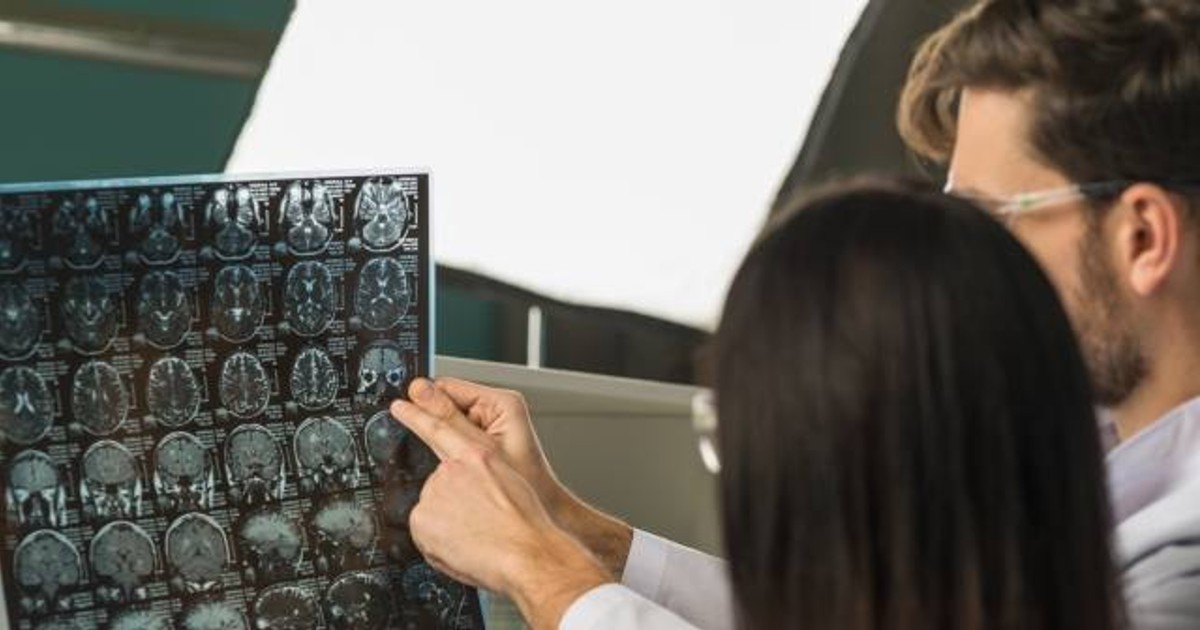
日本人の2人に1人が罹患し、死因第1位を占めるがん。最新研究により、そのがんの「正体」はだいぶ明らかになり、治療法も進歩している。そのがんと、がん治療の「現在地」を追う新シリーズ。第1回は、なぜ体のなかにがんが生まれるのか。その仕組みを解説する。
がんは、誰にとってもきわめて身近な病だ。親や友人をがんで亡くした、あるいはかつて自分自身ががんを患ったという人もいるだろう。日本人の2人に1人ががんに罹(かか)り、4人に1人ががんで亡くなる(※1)。がんは、日本人の死因の第1位であり続けている。
取材中に、ある医師はこう語った。
「約50年前は、がんの5年生存率は30%でした。それが現在は、70%に近づいています。がんは誰もがなり得るものですが、治る病気に変わりつつある。それなのに『がんです』と告知されると、いまだにみんな頭が真っ白になってしまう。でも早期発見すれば治療してすぐに社会復帰、家庭復帰できるわけです。海外旅行するのと同じ感覚で少しのあいだ休んで、現実社会に戻ってくることが可能です。とにかく、がんに対するイメージが悪すぎる」
がん研究や治療が、日進月歩を遂げているのは間違いない。アメリカのがん研究の第一人者マサチューセッツ工科大学のロバート・ワインバーグ博士は1999年刊行の著書『がん研究レース』(岩波書店)で、こう綴(つづ)っている。
「がんはどのようにして生ずるのか? 二〇年前、われわれはこの問いに対する明快な答えを持っていなかった。がんが、われわれの体の正常な組織から生じた無統制に増える細胞であり、放射線、化学発がん物質、がんウイルスなどがその原因となり得ることはわかっていたが、それ以上はまったくのミステリーだった」「一九八〇年代半ばに至るまでの一〇~二〇年の間、抗がん剤やその他のがん治療法は、ほとんど改善されなかった。それは、抗がん剤を探し求める研究者たちが、発がんのメカニズムに関する正確な知識を持ち合わせていなかったがために、ただやみくもに手探りするしかしようがなかったためである」。がんの大家をして「ミステリー」「ただやみくもに手探りするしかなかった」と言わしめる時代が、がん治療にあったことは事実だ。
それと比較すればいまは、ゲノム解析技術によりがんは遺伝子レベルで解明できるようになってきた。また抗がん剤の種類も増え、分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬など、治療の選択肢も広がっている。
しかし、それを理解したうえでなお、冒頭の医師の言葉に違和感を抱く人は多いのではないだろうか。何事もなかったように、社会復帰を果たしている人もいる。しかしその一方でたび重なる再発に苦しむ人も、がんに全身を侵されて命を落とす人もいる。その紛れもない現実が、そこには厳然と横たわっている。
◇臓器により難治度が異なる
私たちが、がんと向き合うために必要なこととは、なんだろう。それはがんを敵視して「闘う」のではなく、「がんとはなにか」を知ることだ。その素性を把握することだ。現代社会の格差のひとつは情報量と質であり、それをどう受け取り、人生に活(い)かすかという情報リテラシーが問われる時代になっている。
「確かに、がんは以前のような不治の病ではなくなっています。ただし、がんの種類によって怖さがまったく異なります。すべてのがんを一緒にしないほうがいいでしょう」
そう話すのは『がんが気になったら読む本 生きぬくための最新医学』(毎日新聞出版)の著者であり、藤田医科大学腫瘍医学研究センター長・佐谷(さや)秀行先生だ。肺がんや肝臓がん、膵(すい)臓がんや食道がんは、たとえステージ2であろうとも、生存率が低い。膵臓がんに至っては、ステージ2で10年生存率わずかに約12%。「こういった悪性度の高いがんというのは再発の可能性が高く、残念ながら多くの患者が2、3年のうちに亡くなってしまう」と佐谷先生は言う。その一方で、救命率の高いがんもあることに気づくだろう。甲状腺がんの10年生存率は、ステージ4でも約73%。女性の乳がんも、ステージ2までであれば85%以上という極めて高い生存率となっている。
「たとえば乳腺で育ったがん細胞と、大腸で育ったがん細胞は性質が違う。それぞれの臓器の環境のなかで生きることを許されたがん細胞が、その環境に最適化する形で育っていくわけです。わかりやすくいえば、それぞれ家が違うから、そこで育つ子どもの性格も異なるということです。
そのなかでも悪性度の高い肝臓や膵臓は人間が生きていくうえで欠かせない臓器です。また食道の壁はとても薄く、リンパ管が多く走っているので、がん細胞が浸潤すると他の臓器にまで広がりやすい。肺は大きくて奥深い臓器なので、小さな腫瘍を見つけにくく、難治がんになりやすいという側面があります」
ではそもそも、がんはなぜ発生するのだろうか。
すべての細胞には、寿命がある。ある程度増殖するとやがて止まり、死んでいく。それと入れ替わるように新しい細胞が生まれて、やはり増殖し、死ぬ。「役目が終わった」と判断する、あるいはDNAなどが損傷すると、自らを安全に処理するアポトーシスという仕組みがある。それは、細胞の「計画的な死」であり、アポトーシスはギリシャ語の「apo-(離れて)」と「ptosis(下降)」に由来し、すべての多細胞生物にプログラムされているものだ。たとえアポトーシスを逃れても、体のさまざまな免疫機能が働き、そういった細胞を退治してくれている。
◇がん幹細胞が源になっている
しかしがん細胞はこのルールを破り、生まれた場所で、異常に増殖していく。そのうち生き続ける新たな場を求めて周辺の組織に浸潤し、血管を破り、血液とともに移動し、他の臓器へと入り込み、転移を起こす。その増殖が一定のレベルを超えると、正常な細胞が機能不全となり、臓器に障害が出て、死へと至る。
とりわけ近年、注目されているのはがん幹細胞の存在である。
「がん幹細胞仮説は60年代から提唱されていました。その後、97年にはトロント大学のジョン・E・ディック博士が実際に人の白血病細胞のなかにがん幹細胞があることを初めて証明した。以来、研究が続けられて、現在のがん幹細胞理論はかなり成熟したものになっているといっていいでしょう」(佐谷先生、以下同)
自らも膀胱(ぼうこう)がんを患ったジャーナリストの立花隆氏は2009年、NHKスペシャル「立花隆 思索ドキュメント がん 生と死の謎に挑む」で日米のトップ研究者たちにがん取材を敢行、この番組は大反響を呼んだ。その内容をもとにした著書『がん 生と死の謎に挑む』(文春文庫)の宣伝文には、こうある。「『知の巨人』ががん研究の最先端に立ち向かう」。その著作のなかには、「がんの本質的理解の仕方として、これまで必ずしも主流ではなかったがん幹細胞説が正しいと認められるようになり」と、がん幹細胞について、そう綴られている。
「私が研究を始めたころもそうですが、以前はがん細胞は2個から4個、8個、16個と単純に分裂を繰り返して増えるものだと考えられていました。でもそれだと、抗がん剤や放射線によってすべてのがん細胞をなぜ完全に退治できないのかは説明がつかない。私がアメリカで研究していた92年、がんの悪性化に深く関わるCD44ⅴという分子を発見しました。CD44は、もともと細胞の表面にあるたんぱく質ですが、CD44vはエクソン(遺伝子のパーツ)が余分にくっついてしまった変異型です。それに関する論文は当時、権威ある医学誌『ランセット』にも掲載されました。
◇なぜ抗がん剤でも退治できないか
そこで私たちはCD44ⅴを検出できる抗体をつくり、それでがん細胞を染めてみたのです。でも、全部のがん細胞が染色されるわけではなかった。がん細胞を識別できる方法をやっと見つけたと思ったのに、と本当にがっかりしたものです。でも、その染まっていないものは、じつはがん幹細胞だったのだと20年後になってようやくわかった。それが明らかになり、がん治療の難しさも理解できるようになったのです」
1㌢のがんが発見されたとき、そこには10億個ものがん細胞が集まっている。がんの種類や進行度によっても異なるが、治療前の大腸がんや胃がんや肺がんなどでは、がん幹細胞はがん組織のうち、数%から10%程度を占めると考えられている。
では、果たしてがん幹細胞とはなんなのだろうか。じつは幹細胞そのものは、がん以外の細胞にも存在している。体の組織はすべて、幹細胞から生まれた細胞によってできているのだ。幹細胞が前駆細胞になり、そこからより分化が進んで、最終的には胃、大腸、皮膚といった特定の機能を持つ最終分化細胞へと至ることになる。
「その幹細胞の特徴というのは、増殖の速度が遅いということです。1カ月のうち2回ほどしか分裂しません。それが前駆細胞になると途端に速度が上がり、1日約1回の割合で分裂し、増殖していく。
たとえば皮膚であれば、細胞が角質層へと上がって剝(は)がれ落ちるまで28日かかります。私たちの皮膚細胞は1カ月ほどで全部きれいに入れ替わっているわけです。それが腸だと数日から10日ですべて新しい細胞になります」
加えてがん幹細胞の大きな問題は、遺伝子に複数の変異が入っているため細胞がなかなか老化して脱落せず、持続的に増殖すること。つまり、寿命がとても長いのである。
◇CTにも写らず再発の原因となる
ここで、どのようにがん幹細胞が誕生するのか、見てみよう。
「正常な幹細胞が、がん幹細胞へと変化するケースは、それほど多くはありません。がん幹細胞が生まれる大きな理由と考えられているのが、体のなかの慢性炎症です。慢性炎症はウイルスや細菌の感染、肥満や糖尿病、飲酒や喫煙といった生活習慣、機械的な刺激が原因となります。炎症が起こると、組織が傷つく。その損傷した部分を補おうと、新しい細胞の増殖が盛んになります。組織の再生が活発に繰り返されるようになると、どうしてもミスコピーが起きやすい。その細胞の増殖と炎症が長期間続くうちに、正常だった細胞が少しずつがん細胞へと変わっていく。がん幹細胞はさまざまな傷が無数に入り、それが積み重なることで生まれます。だから性質も複雑で、治療も厄介なのです」
それと同じ理由で、増殖性が高い細胞は、やはりがんの種を生みやすい。乳腺や前立腺など性ホルモンに関連している器官はホルモンの影響により増殖が旺盛になり、その過程で遺伝子の変異が起きやすいのだ。
「最近の研究でわかってきたのは、がん幹細胞は一般的ながん細胞と比べて、治療に対して高い抵抗性があるということです。抗がん剤、放射線、分子標的薬などの治療を行っても、なかなか退治できません。治療によって排除できるのは働き蜂のがん細胞ばかりで、がん幹細胞である女王蜂は生き残ってしまう。そのためしばらくすると、生き残った女王蜂から再び働き蜂が生まれてくる。それが、がんの再発なのです」
治療後に、CTなどにがんは写っていなかったが、その後に再発したというのは、このがん幹細胞が見えない形で体のなかに残っていたことにより、やがてがん細胞が再び増えた状態を指すのである。
次回は、がん幹細胞と細胞のがん化の仕組みを、より詳しく見ていく。
取材・文/本誌・鳥海美奈子
※1 厚生労働省 令和5年(2023)・人口動態統計
サンデー毎日11月9,16日号表紙 北山宏光


