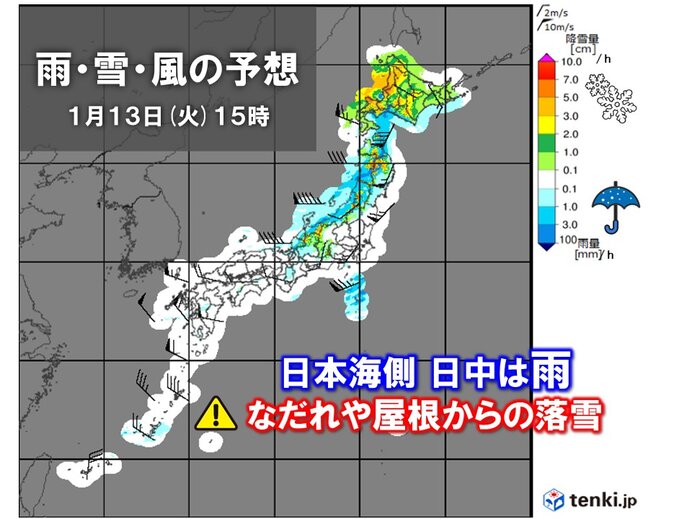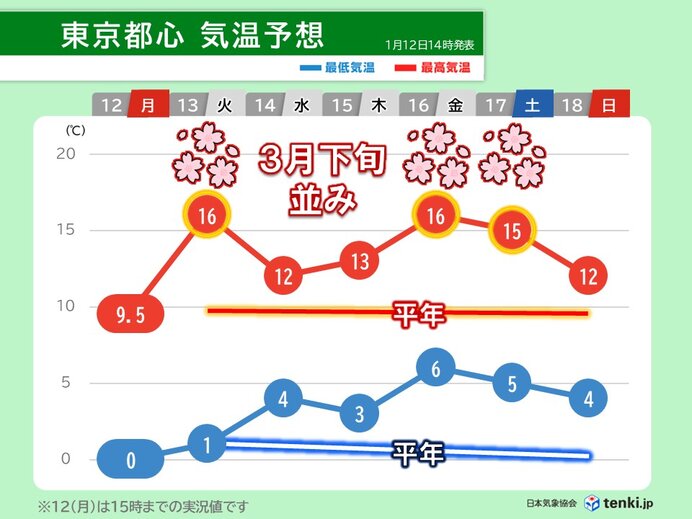旧江戸川に浮かぶ、東京23区では珍しい自然島…工場群と「まるで海外」リゾートが融合

東京都江戸川区と千葉県浦安市との都県境を流れる旧江戸川に長細い中州が見える。23区では珍しい自然島「 妙見島(みょうけんじま) 」だ。仏パリ・セーヌ川のシテ島や、米ニューヨーク・ハドソン川のマンハッタン島と同じように川の中で土砂が 堆積(たいせき) してできた島だという。島には工場地帯が広がる一方で、リゾート気分を味わえるエリアもあるとか。一体どんな島なのだろうか。現場を訪ねた。(江原桂都)
1953年に撮影された妙見島。「流れる島」と呼ばれていた(江戸川区郷土資料室提供)東京メトロ東西線浦安駅(浦安市)から徒歩約10分。旧江戸川にかかる浦安橋に設置された階段から、島に下りた。大きさは南北に約700メートル、東西に約200メートルで、広さは8ヘクタールほどだ。
島内を北に向かって進むと島名の由来となった「妙見神社」の赤い鳥居があった。北極星を神格化した妙見菩薩は、14世紀半ばに一帯を治めていた下総国の豪族・千葉氏の守り神だったという。島は、江戸時代に滝沢馬琴が著した伝奇小説「南総里見八犬伝」に、戦場の一つとして登場する。
小島雄二さんかつては千葉県だったが、1895年に東京に編入され、現在の住所は江戸川区東葛西だ。区教育委員会教育推進課文化財係の小島雄二さん(56)は、「今はコンクリートで囲われて軍艦島のようだが、昔は『流れる島』と呼ばれていた」と話す。
明治時代の地図上では、現在よりも100メートルほど上流にある。川の流れによって北端が削られ、土砂が下流の南側に堆積。少しずつ形を変えながら、下流側に移動していた。1979年に護岸工事が完了し、移動は止まったという。
西野哲造さん区側の対岸で生まれ育った地元・長島町会副会長の西野哲造さん(75)は、「父が漁師で、子どもの頃は島周辺はシラスなど漁が盛んで、船が行き交い、ノリや貝の製造・加工場もあった」と懐かしむ。60年代頃から水質が悪化し、漁は下火に。船で大量の資材や原料を運搬できるメリットなどから、工場の進出が進んだ。
小菅洋慈さん現在の島内は、産業廃棄物処理場や道路整備会社、建設会社などが立ち並ぶ。島の北端にあるマーガリンなど食用加工油脂を製造・販売する「月島食品工業」の小菅洋慈・人事総務部長(53)は、「昔は20社ほどあったが、今は13社に減っている」と教えてくれた。同社は、島内の企業でつくる「妙見島親睦会」で事務局を務めている。
かつて、島内の産廃処理場などから出る粉じんや砂ぼこりなどは、地元住民を悩ませることも多かったそうだ。長島町会と島内企業は距離を取る時期もあったが、近年は「防災」を軸に、新たな関係性の構築が進んでいる。
江戸川区の7割は海抜ゼロメートル地帯で、ハザードマップでは大半が「赤色」に染まる。護岸工事などの対策が取られている妙見島はマップ上は安全とされる「白」。災害への強さと、船舶で被災者や支援物資を運べる利点を生かし、地元・長島町会と妙見島親睦会は2月末、大規模水害が発生した際の協定を結んだ。協定に基づき、地域住民は島内の企業の施設に避難できるようになり、西野さんと小菅さんは「地元住民と企業とで助け合い、協力していきたい」と話す。
工場が多い島内で、まるで海外のような景色と雰囲気を味わえるのが、島北側にある会員制マリンクラブ「ニューポート江戸川」の一角だ。
釣りなどのレジャーに使うプレジャーボートが40隻ほど並ぶ。1950年に造船所として創業し、81年に転業してマリーナの経営を始めたそうだ。3代目社長の浅見洋史さん(54)は「一年で一番盛況なのが、今の時期のお花見クルージング。秋には東京湾での海釣りの利用者が多い」と話す。年間の利用者は1万人ほどだそうだ。
大塚裕子さん同クラブの建物の2階にあるレストラン「マリーナ・レストラン・トリム」は、天井が高く、店内から船を望める開放的な空間だ。店長の大塚裕子さん(50)は「間近にたくさんの船を見ながら食事を楽しめる場所は都内にも少ない。日常を離れて癒やしになる場として楽しんでほしい」と話す。
【地図】妙見島