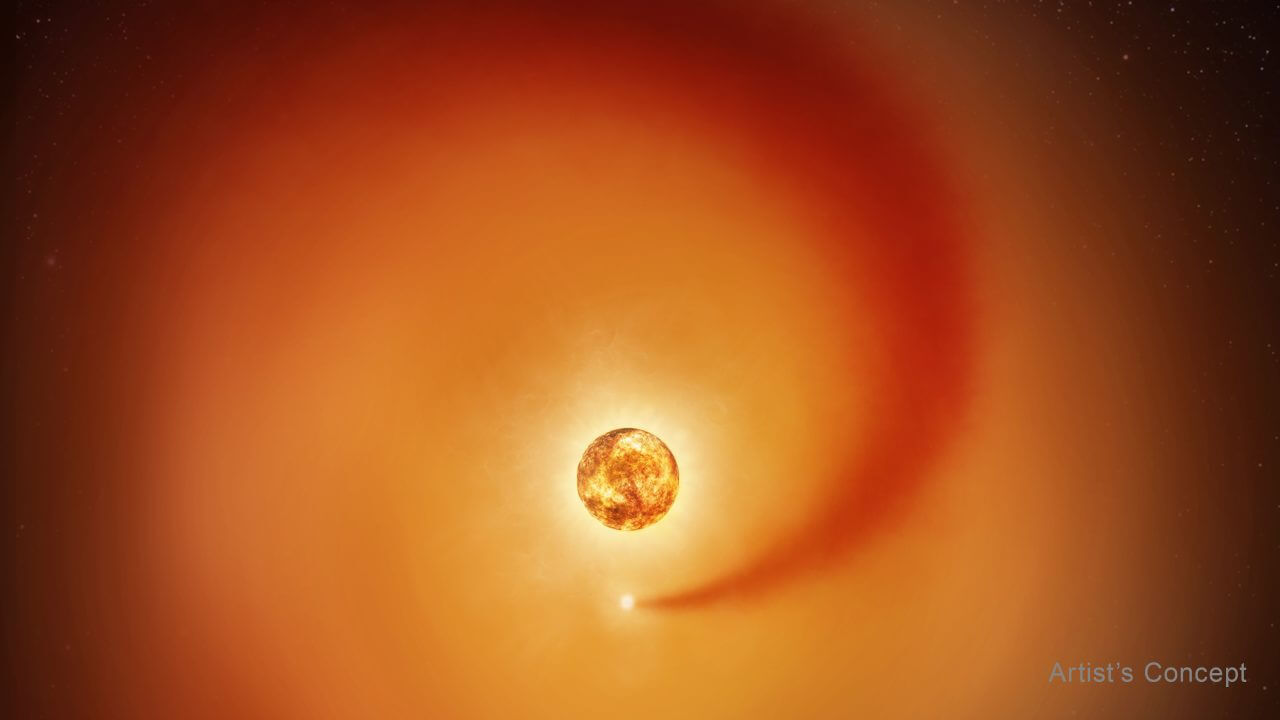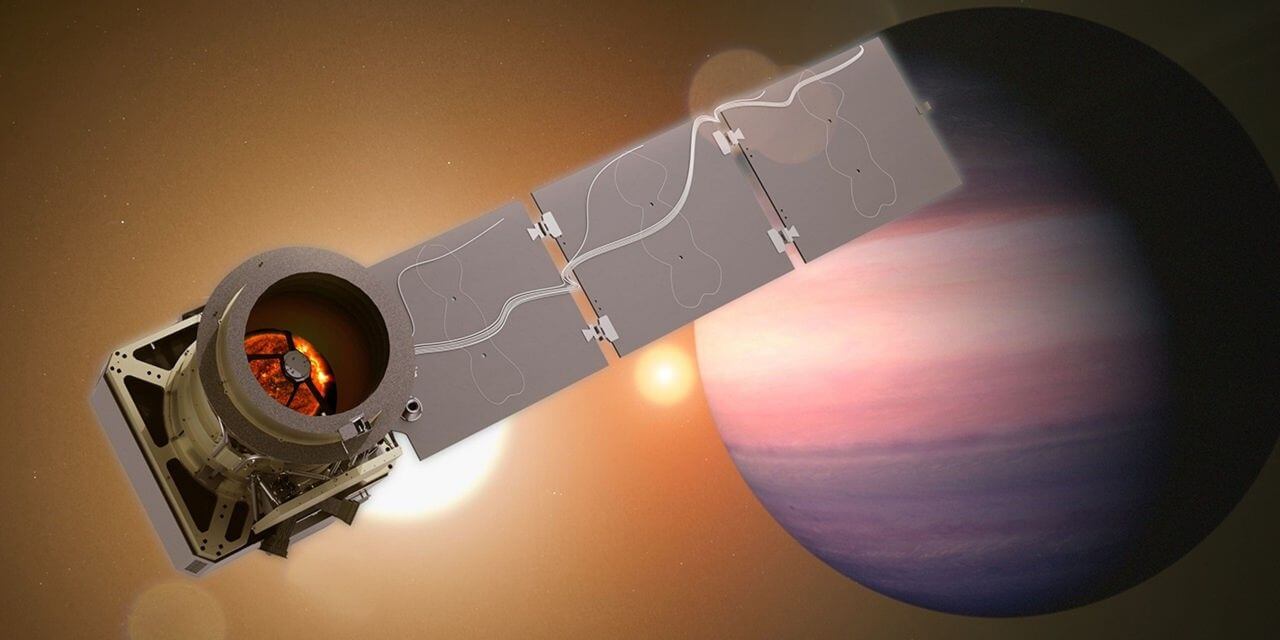1万2000基以上の人工衛星で星が見えない…。それでも企業はスルー

地球の周りを飛行している運用中の人工衛星の数は、1万2000基以上。ここ3年で急増しており、その数はほぼ2倍になっています。今後も増え続けていきそう。
人工衛星増加に頭を悩ませているのは天文学者。望遠鏡で宇宙を観測する際、人工衛星が明るくて空や星が見えないのです。天文学画像に人工衛星の軌道が映り込むこともしばしば。以前から人工衛星企業へは苦言が呈されており、対策が検討されていました。
が、最新調査でわかったのは、多くの人工衛星企業は天文学への光害なんて気にしていないということ…。
輝度を考慮するのは1社だけ
国際天文学連合の空の暗さと静けさを守るプロジェクト「CPS(Center for the Protection of the Dark and Quiet Sky)」が定めた、高度550キロ以下で周回する人工衛星の推奨輝度。これを守っているのはたったの1社だけという皮肉な調査論文が公開されました。
ほぼすべての人工衛星が、推奨される等級最大値+7をオーバー。つまり、天文学に影響を及ぼす明るさになってしまっているのです。なかでも特に輝度が高いのがテキサス州スタートアップのAST SpaceMobile。BlueWalker衛星軍の等級は+2です。(*等級は数字が大きいほど暗い)
国際天文学連合の推奨
地球低軌道状への人工衛星は、宇宙への安価なアクセス手段として、昨今、急成長中のビジネス。そこで2022年、夜空を守るため国際天文学連合が専門部署(CPS)を始動、推奨輝度を定めたわけですが…。
8000基の人工衛星を、地球軌道上で運用するSpaceXのStarlinkは、光害最大の懸念の1つ。ただ、国際天文学連合をはじめ天文学会と協力して、輝度を抑える対策も実施しています。初期のStarlink衛星の等級が+3だったのに対し、現在は+5から+6にまで暗くすることに成功しています(推奨等級には届いていないものの…)。一方で、人工衛星のサイズにも変化があり、Starlink最新世代Gen 2 Miniは、前モデルの4倍。飛行高度は450キロで、輝度対策も虚しく夜空で目立つ存在に…。
CPSガン無視でもっとも明るいのは、前述のAST SpaceMobileの人工衛星BlueWalker。その等級は+3.3と非常に明るい上に、地球低軌道状で最大の通信設備であり、羽をすべて広げると64平方メートルにもなります。しかも、AST SpaceMobileは今後、100基の人工衛星からなる衛星軍を計画中。
一方で、CPSの推奨等級を唯一守っているのは、ロンドンを拠点とするOneWeb。現在、地球軌道状に652基の人工衛星を運用しており、その等級は+7.85、また高度は1200キロメートル。
論文はarXixにて読むことができます。