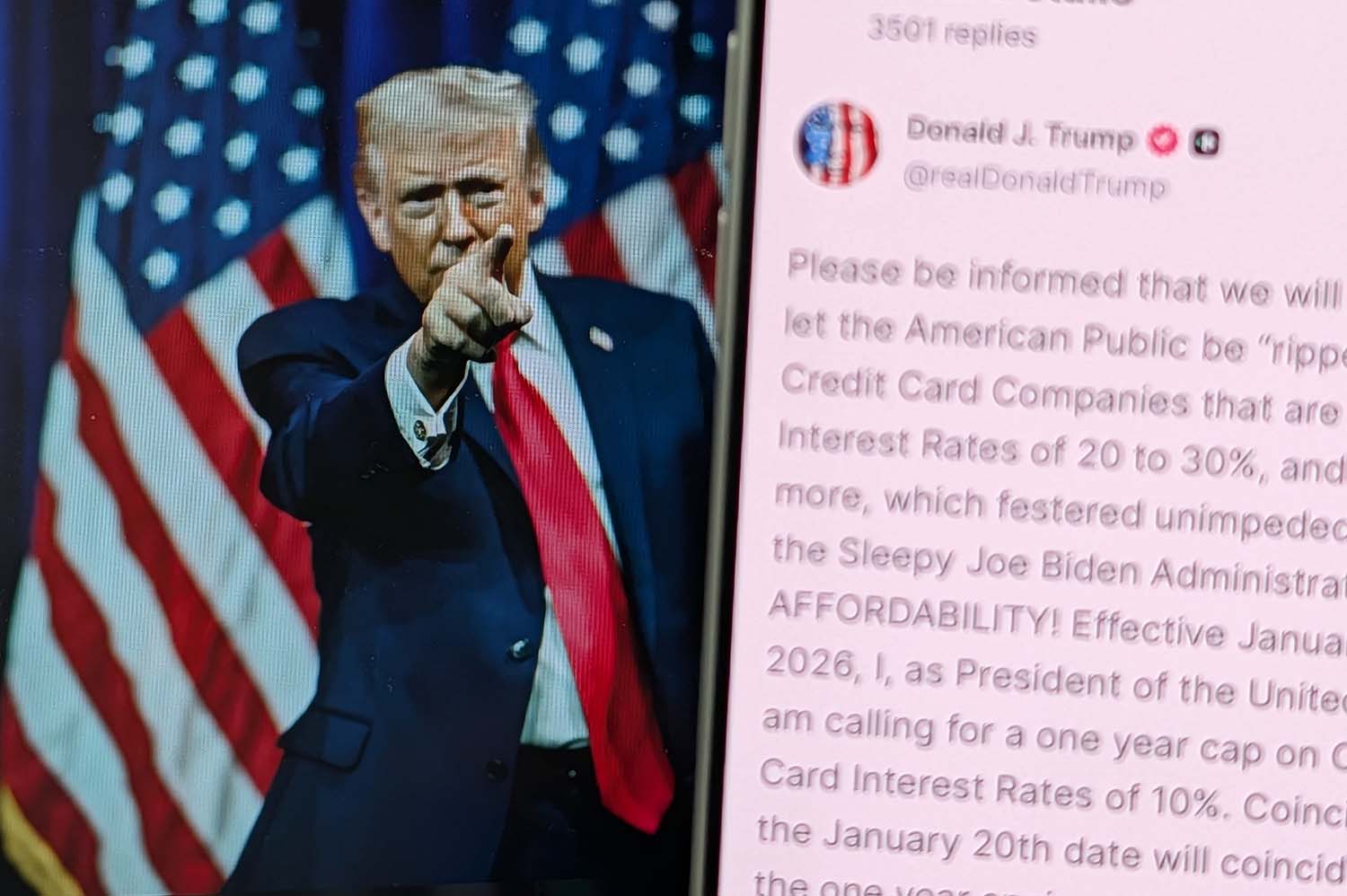米国債に代わる逃避先、日本や欧州が浮上-トランプ時代の構造転換か

金融市場で数年ぶりに質への逃避が加速する中、米国債以外にも信頼できる代替資産が出てきたとの認識が投資家の間で広がりつつある。
米10年債利回りは年初来で約40ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下。最近では一時4%を割り込んだ。背景には、トランプ米大統領の関税政策がリセッション(景気後退)リスクを高めるとの見方がある。
一方、欧州と日本の10年物国債利回りもリスク回避の影響で低下しているものの、年初来ではなお上昇している。国防支出拡大に伴う国債増発見通しから、独10年債利回りは足元で2.67%程度。長年ゼロ近辺に張り付いていた日本の10年債利回りも、日本銀行の利上げ観測から1.25%程度に切り上がっている。
いずれの利回りも米国債と比べるとかなり低いが、ドル建て資産を購入する際に為替ヘッジを行う欧州や日本の投資家にとっては、米国債よりも魅力的に見える水準にある。そのため、政策見通しがより安定している本国市場に資産配分をシフトさせる投資家が増える可能性がある。
ドイツ銀行の米金利分析責任者、マシュー・ラスキン氏は「トランプ政権のさまざまな政策が米国債に対する外国勢からの需要を損なう恐れがあるとの見方がじわり浸透しつつある」と話す。
これは「米国例外主義」がもはや市場の支配的なテーマではなくなりつつあるとの見方を改めて浮き彫りにするもので、長期的に重大な影響をもたらす恐れがある。ドイツ銀行は「ドルへの信認危機」を警告する一方、UBSグループは世界の通貨におけるユーロの地位向上につながり得ると指摘している。
もっとも、実際にそうしたシフトが実体化するまでは慎重な姿勢で臨む必要がある。2023年半ばにも独連邦債が現在と同じように妙味を増したかに見えたが、激しい売り浴びせで米10年債利回りが5%まで跳ね上がると、金利差における欧州の優位性は失われた。米国の関税政策がインフレを再燃させれば、米国債利回りが再び上昇することもあり得る。
一方で、7日に米国債が大きく下落したことは、米国債が持つ「安全資産としての魅力が薄れつつある」兆候だとの見方も出ている。
シティグループのG10金利トレーディングデスク部門ストラテジスト、ベン・ウィルトシャー氏は「米国債が売られたことは、もはやリスクオフ局面で米国債は世界の国債における資金の逃避先ではなくなるという、いわば構造的な転換を示す兆候なのかもしれない」と述べる。
注目すべき点として、外国勢による米国債保有の大部分は長期債に集中していることが、政府データから分かっている。そのため外国人投資家の需要が低下すると、米国のイールドカーブのスティープ化につながる可能性があると、バンガードの国際金利部門責任者、アレス・カウトニー氏は話す。つまり、短期金利に対して長期金利が相対的に上昇することになる。
世界的な利回りの変化に投資家がどう対応しているかを知る上で、初期の手掛かりが近く得られるかもしれない。日本では新会計年度が始まったばかりで、企業は通常、この時期に資産配分戦略を見直すことが多い。日銀による長年の超低金利政策を受けて、日本の投資家は高い利回りを求めて国外市場に資金を振り向けてきた経緯があり、日本勢は世界の債券市場において重要な存在だ。
ファイブスター投信投資顧問の下村英生シニアポートフォリオマネジャーは、欧州の金利の方が魅力的なので、日本の投資家の資金フローに変化が生じるかもしれないと指摘。「一般的にはそうなっていく可能性はもちろんある」と述べた。
一方で、トランプ政権下の政策は不安定な印象を与えており、米国債の魅力を損なう恐れがある。BNPパリバのシニアマルチ戦略アナリスト、マーク・ハワード氏は「どのような原則が支持され、それが将来の想定リターンの確実性にどのような影響を与えるのか、国際市場は困惑している」と指摘する。
「より国家主義的な投資プロセスへの段階的回帰」を予想する同氏は「欧州や日本での利回り上昇が、そうした国家的な志向を満たすだろう」と述べた。
原題:The World Is Finding a Plausible Alternative to Treasuries (1)(抜粋)