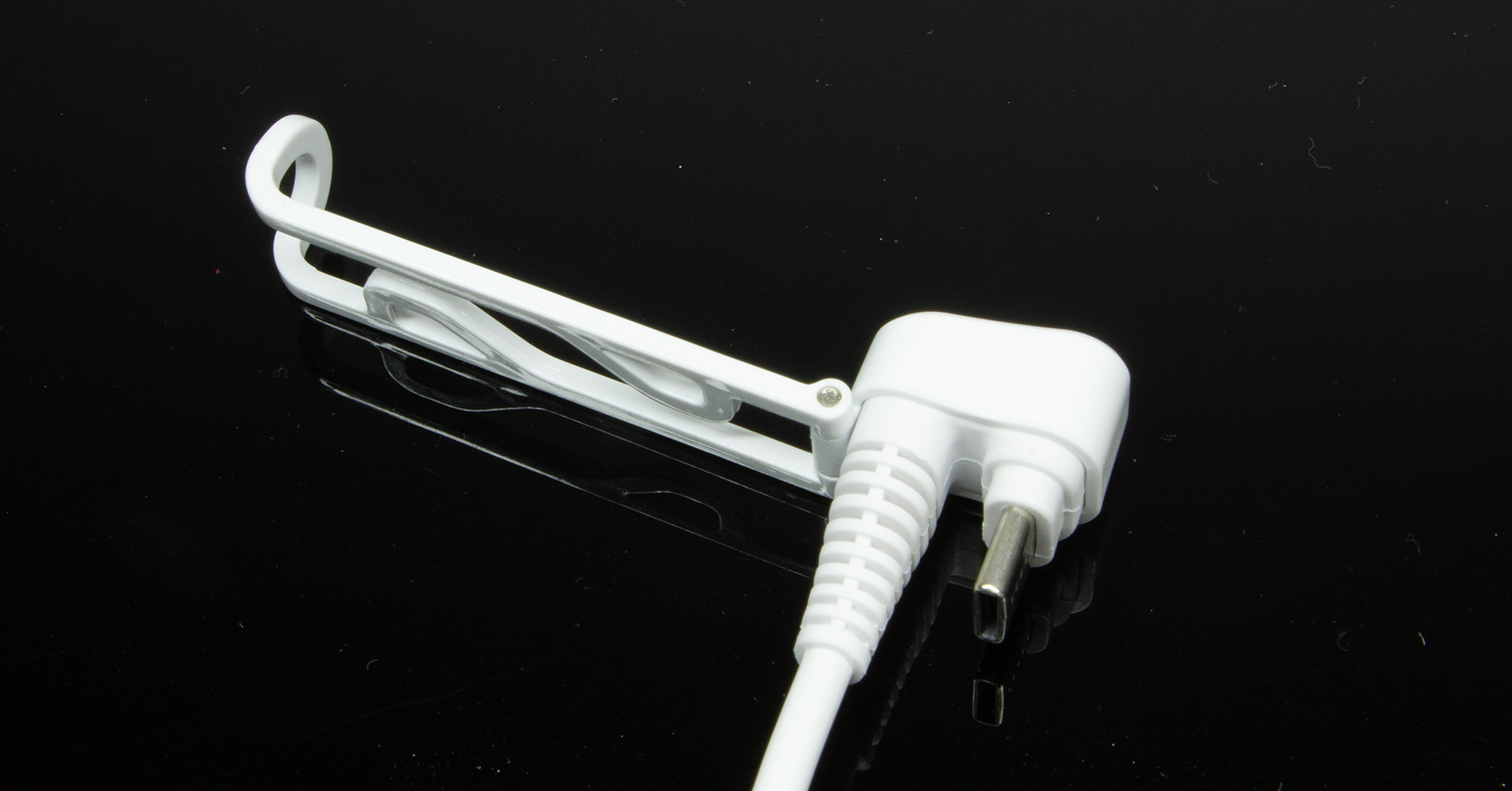楽天モバイルは本当に“最強”か? 「Rakuten最強プラン」 3GB・1078円をワイモバ・ドコモ・povoと比較する

Rakuten最強U-NEXTの開始を前に、料金据え置き宣言をした楽天モバイル。わざわざ記者会見を開いたことから、他社に合わせて値上げすると思いきや、料金プランはそのままというフェイントをかけてきた格好です。
ただ、あくまでこの宣言は値上げをしないというもの。逆に、一部のデータ容量で値下げを考えているのでは……と思わせる発言もありました。
楽天モバイルの会長の三木谷浩史氏は、3GB以下で1078円になる段階制をやめないのかを問われた際に、「今のところはないですね」と即答。これに続けて、「むしろ、もっとアグレッシブに行くかというのはあるし」とコメントしています。この発言を文字通りに捉えると、3GB以下の低容量でより攻めるかもしれないと示唆している形になります。
では、なぜ楽天モバイルは低容量帯でアグレッシブなことを検討しているのでしょうか。競合他社の低容量プランと比較すると、必ずしも「Rakuten最強プラン」が“最強”ではないことが見えてきます。その中身を見ていきましょう。
楽天モバイルのRakuten最強プランは、3GB以下の料金が1078円です。家族で2回線以上契約すると「最強家族プログラム」で110円の割引が入り、968円まで料金が下がります。
さらに、13歳から22歳の場合や、65歳以上の場合には、「最強青春プログラム」や「最強シニアプログラム」も重ねて適用でき、料金は858円に。12歳以下は「最強こどもプログラム」で538円まで金額が下がります。
子供を除くと、 一般的なユーザーの場合には858円~1078円の間で3GBまで使える料金プラン と言えるでしょう。1000円前後で3GBというのは、かつてのMVNOと同水準。あまり使わないユーザーがこの金額で収まるのであれば、確かに安いと言えます。一方で、最強かというと、必ずしもそうではありません。
楽天モバイルが3GB以下の料金を1078円に設定したのは、21年の「UN-LIMIT VI」導入時。1GB以下を0円にするアグレッシブすぎた料金体系はその後改定されましたが、 3GB以下の金額である1078円は5年弱変わっていません 。その間、他社は小容量プランの金額やデータ容量を大きく変えてきており、当時とはやや状況が異なっています。
直近で料金プランを改定したキャリアでいうと、ソフトバンクの ワイモバイルでは、「シンプル3」のSプランをこれまでの4GBから5GBに改定したうえで、各種割引適用後の料金を1078円に据え置いています 。
また、PayPayカードゴールドで料金を支払った場合には「PayPayカード割」が適用され、料金は858円まで下がります。
1078円や858円という金額は、楽天モバイルの3GBと同額。一方で、データ容量は5GBになっており、より多くのデータ通信を使うことができます。
また、11月からは「PayPay使ってギガ増量キャンペーン」が実施され、PayPayでの決済が10回以上の場合には1GBが追加されます。ここまで加味すると、楽天モバイルと同額でちょうど2倍のデータ容量が使える計算になります。
ただし、ワイモバイルの1078円なり858円なりは、あくまでも割引後の金額。「おうち割光セット(A)」がなければ料金は1650円上がりますし、PayPayカードがないと330円の割引を受けられません。 素の料金は3058円 になります。1回線から、何の割引もなく3GB、1078円になるのは楽天モバイルの強みです。
一方で、ソフトバンクの寺尾洋幸専務は、「実際には過半数を超えてもう少し高い比率でセットになっている」と話しており、かなりの規模のユーザーが最低料金になっていることを示唆しています。
少なくとも、この過半数を超えるユーザーにとってはワイモバイルの料金の方が、楽天モバイルよりもおトクということになります。
「irumo」の新規受付を停止したNTTドコモも、「ドコモmini」には4GBのデータ容量を用意しています。こちらの各種割引適用後の料金は880円。楽天モバイルで、最強家族プログラムを適用したときよりも料金は安く、かつデータ容量も1GB多くなっています。金額とデータ容量のどちらも、小容量であれば楽天モバイルよりおトクというわけです。
こちらも、ワイモバイル同様、割引の条件は多め。大きいところでは、「ドコモ光セット割」か「home 5Gセット割」が必要になり、これがない場合には料金が1210円上がります。また、ドコモminiから「ドコモでんきセット割」が新たに設けられており、これが適用されないと110円高くなります。
3つ目はdカードお支払い割。通常のdカードだと220円、dカードGOLD以上(dカードGOLD Uを含む)だと550円の割引になり、ワイモバイルのように、最適料金で使う際にはクレジットカードの種類もゴールド以上にする必要があります。
ただし、現在はキャンペーン中で、通常のdカードでも550円の割引を受けることができます。 割引なしの料金は2750円 ですが、ドコモも光回線などの付帯率は高くなっています。
ドコモminiの適用率といった直接的なデータはありませんが、5月にドコモの前田義晃社長は旧料金プランのeximoでは、半数のユーザーにすべての割引が適用されていると語っていました。一部の割引だけにすると、その率は9割を超えているといいます。
ドコモminiでは割引条件が増えているため、全適用の率は下がっているものとみられますが、それでもかなりの数のユーザーが楽天モバイルより安く、かつ、より多いデータ容量を使えている可能性があります。
大手3キャリアの中で唯一楽天モバイルより金額が高いのは、KDDIのUQ mobile。こちらは、「トクトクプラン2」で5GB以下だった場合の割引適用後の料金が1628円になります。
ただし、ワイモバイルやドコモより条件は緩めで、「自宅セット割」は光回線だけでなく、電気サービスも対象になります。「au PAYカードお支払い割」も220円と安め。割引の比重は2社よりやや低くなっています。
メインブランドの小容量プランや、サブブランドの料金プランの場合は、いわば“割引前提”ですが、1回線から安い料金を求めるのであれば、オンライン専用ブランドを選択する手もあります。
こちらは、ソフトバンクのLINEMOが 「LINEMOベストプラン」で3GB以下の場合、990円 。楽天モバイルの3GB以下である1078円よりもわずかながら安くなっています。
ただし、LINEMOには家族割引のようなサービスがなく、Rakuten最強プランに最強家族プログラムを適用した場合、料金は逆転します。いずれにしても、その差はわずかしかないので、LINEMOはほぼ同容量を同価格帯で提供しているとまとめてもいいでしょう。
同様に、KDDI傘下のKDDI Digital Lifeが提供している povo2.0も、3GB(30日間)のトッピングを990円 で提供しています。povoの場合、3GB(30日間)トッピングにのみ、自動更新の仕組みを用意しており、月額料金を払う一般的なキャリアに近い感覚で利用できます。また、10月には5GB(30日間)や60GB(365日)を新設しています。
後者の場合、まとめ買いをすることで1カ月あたりの料金は1100円まで下がります。金額を見れば分かるように、Rakuten最強プランの1078円とほぼほぼ同じ。22円高いだけで、データ通信を2GB多く使える計算になります。
このように、各社ともに3GBより上の4~5GBといったデータ容量を強化しているため、3GBに閾値を設定しているRakuten最強プランがやや割高になってきていることが見て取れます。
もちろん、Rakuten最強プランには、他社の小容量プランにはないSPUの4%や、海外ローミングが2GBまで無料(ワイモバイルは26年夏以降に提供予定)、さらにはRakuten Linkで音声通話も無料といった特典もあり、これらのユースケースに当てはまるユーザーは、他社より料金が安くなることがあります。
一方で、データ容量と価格という単純な比較では、必ずしも“最強”と言えなくなっているのも事実です。
各社のサブブランドがユーザー獲得の要になっていることからも分かるように、大手キャリアは比較的安い料金でユーザーを増やし、そのユーザーを上位プランやメインブランドに移行させていくというのが基本的な戦略。
Rakuten最強プランは、そのステップを1つの料金体系にまとめたものと捉えることができます。低容量は、ユーザーを獲得するための武器になるというわけです。
三木谷氏が、「むしろもっとアグレッシブに」と発言したのは、こうした市場環境を踏まえてのこととみられます。
さすがに、かつてUN-LIMIT VIで導入したような1GB以下0円はアグレッシブすぎて廃止してしまいましたが、最低金額で使えるデータ容量を増やすような改定は検討しているような気もします。値上げの話が続く中、同社のアグレッシブな施策には期待したいところです。