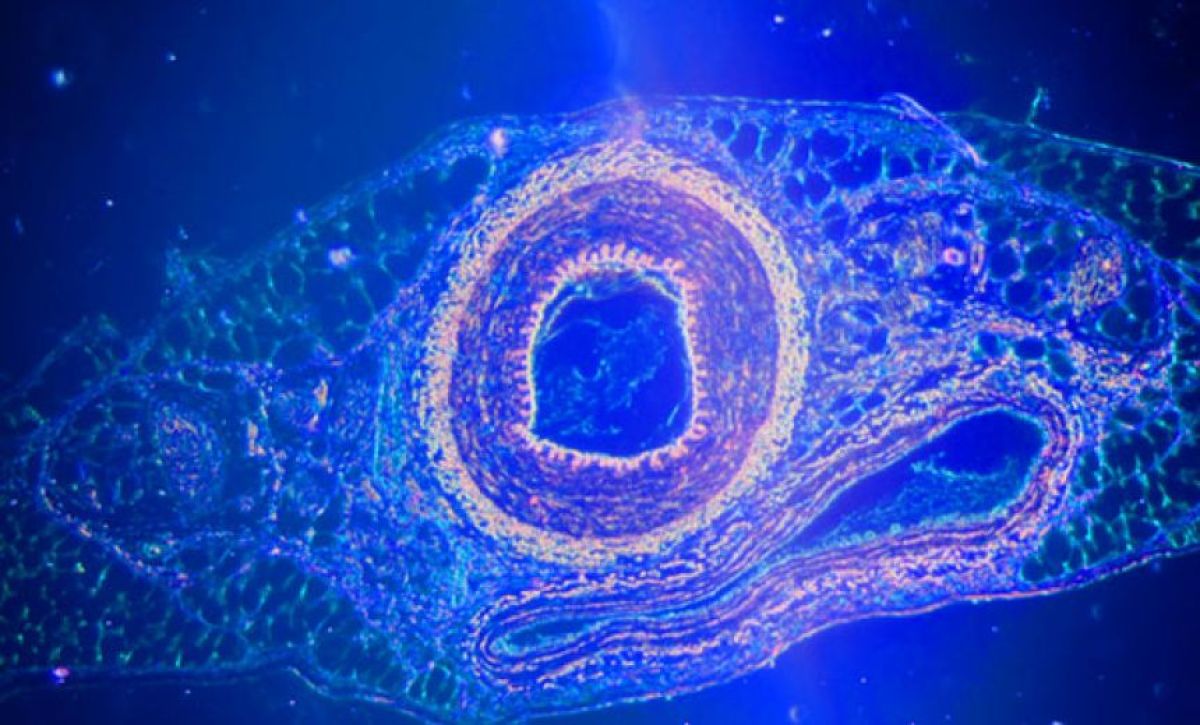「A氏が犯人なら犯行時刻に犯行現場にいた。しかし、その時刻、A氏は離れた場所にいた」矛盾を導くことで証明する「背理法」という考え方(現代ビジネス)

なぜ、その解法を思いつくのか?数学ができる人とできない人の差はどこにあるのか? 数学者の芳沢光雄さんが『いかにして解法を思いつくのか「高校数学」』(上・下)を執筆する背景にあった「数学における13個の考え方」と「発見的問題解決法」という着想をもとに、「数学の土台となる考え方」を身につけるための思考法を紹介します。この記事では「13個の考え方」から「背理法」について高校数学の問題をもとに考えていきます。 【図版】矛盾を導くことで証明する「背理法」という考え方
本稿では、筆者が発見的問題解決法と考える13項目のうち、「背理法を用いる」について高校数学の演習を視野に置いて述べよう。ちなみに以前の記事では、それぞれ「帰納的な発想を用いる」、「類推する」について述べている。なお、ネットの記事では文字の制限がある関係で、数式ワープロを使わない点をお許しいただきたい。 大学教員人生45年間で、入学試験問題に関して生涯忘れることができないものがある。筆者が東京理科大学理学部に勤めていたときの2002年度の理学部数学科一般入試問題である。 「背理法とは何かを20字以上100字以内で説明せよ」という記述式の問題で、いろいろなエピソードを思い出す。とくに、その問題が朝日新聞の一面にも取り上げられたことが忘れられない。 そもそも背理法とは、仮定から結論を導くために、結論を否定して推論を積み重ねて矛盾を導いて、結論の成立をいう証明法である。 本稿では、2つの例題を背理法によって考えてみよう。
例題1:50人が参加したあるあるパーティーについて、ある人は次のように話した。50人のうちの23人は「自分はちょうど20人と知り合いである」と言っている。また、残りの27人は「自分はちょうど15人と知り合いである」と言っている。誰かが嘘を言っていることを説明せよ。 例題1を考えるとき、試しに、もっと人数が少ない以下のような状況に「特殊化」して考えてみよう。 下図は、次のことを示す図である。 ここに5人:A、B、C、D、Eがいて、AはBの1人だけと知り合いで、BはA、C、Dの3人だけと知り合いで、CはBとDの2人だけと知り合いで、DはB、C、Eの3人だけと知り合いで、EはDの1人だけと知り合いである。そして、互いに知り合いの関係の2人を線で結んでみた図である。 上図で線の本数は5本である。そして、 アはAからの1本とBからの1本を意味している。 イはBからの1本とCからの1本を意味している。 ウはBからの1本とDからの1本を意味している。 エはCからの1本とDからの1本を意味している。 オはDからの1本とEからの1本を意味している。 ここで、各人が知っている人数の全員ぶんの合計を考えると、 Aからの1人+Bからの3人+Cからの2人+Dからの3人+Eからの1人=10人 となる。 上の計算においては、 アに関してはAからの1人とBからの1人の合わせて2度カウントしている。 イに関してはBからの1人とCからの1人の合わせて2度カウントしている。 ウに関してはBからの1人とDからの1人の合わせて2度カウントしている。 エに関してはCからの1人とDからの1人の合わせて2度カウントしている。 オに関してはDからの1人とEからの1人の合わせて2度カウントしている。 上で述べたことを「一般化」すると、次の定理を証明できるのではないだろうか。
Page 2
定理:人間の集団があって、そこでは任意の2人について、「互いに相手と知り合いである」か「互いに相手を知らない」のどちらかが成り立っているとする。このとき、各人が知っている人数の全員ぶんの合計は偶数になる。 証明:人間の集団にはn人がいて、P1、P2、P3、…、Pn(注:1~nは下付き文字)と名付けられているとする。また、互いに知り合いの関係は全部でm個あって、それらもE1、E2、E3、…、Em(注:1~mは下付き文字)と名付けられているとする。 このとき、上の例で説明したことから、次のことが分かるだろう。 P1が知っている人数+P2が知っている人数+……+Pnが知っている人数 は E1に関しては2度カウントして、E2に関しても2度カウントして、……、Emに関しても2度カウントしている。 したがって、 各人が知っている人数の全員ぶんの合計=2×m が成り立つことになる。 (証明終わり) ここで、例題1の説明をしよう。もし結論を否定して、誰も嘘を言っていないとすると、上の定理より 20×23+15×27 は偶数でなければならない。ところが、 20×23+15×27=460+405=865 であるので、これは矛盾である。したがって誰かが嘘を言っているのである。 ちなみに上の考察で用いた「特殊化」と「一般化」も、筆者が考える「発見的問題解決法」13個のうちの2つである。それらについても、適当な機会に詳しく述べるつもりである。
次に、例題2を考えてみよう。 例題2:有理数とは(整数/整数)の形で表せる実数のことである。2つの有理数a、bの和と積が整数ならば、aとbはともに整数であることを証明せよ。 解説:背理法を用いて示す。すなわち、2つの有理数a、bの和と積が整数で、aとbの少なくとも1つが整数でない場合を仮定して矛盾を導こう。 いま、aとbのどちらか1つだけが整数でないならば、(a+b)は整数ではないので、この状況はあり得ない。そこで、aとbはともに有理数であるが、ともに整数でない、として議論を進めよう。 ここで、中学数学で学んだ「√2は無理数である」ことの背理法による証明を思い出そう。筆者がよく示す証明法は、 √2=n/m(nとmは整数)……(*) であるとして、 2×mの2乗)=nの2乗 を導いて、上式の両辺を素因数分解したときの、それぞれの素数の個数を考える。 m、nを素因数分解したときの素数の個数をそれぞれs、tとすると、左辺の素数の個数は奇数個(2s+1)で、右辺の素数の個数は偶数個(2t)である。これは矛盾であるという方法である。 一方、学校教科書に載っている証明法は、(*)における「nとmは互いに素(共通の素因数はない)」という仮定を設けて矛盾を導く方法である。以下、これを参考にするのである。 例題2に戻ると、「aとbはともに有理数であるが、ともに整数でない」としたことから、 a=n/m(nとmは互いに素な整数、mは2以上) b=t/s(tとsは互いに素な整数、sは2以上) として議論を進める。「互いに素」という強い条件が加わったことに留意したい。 a+b=(ns+tm)/(ms)……(ア) ab=(nt)/(ms)……(イ) の両方が整数であるので、(ア)より、mはns+tmの約数である。よって、mはnsの約数となるので、mはsの約数になる。また(イ)より、sはntの約数となるので、sはnの約数になる。 したがって、mはnの約数となって、矛盾である。 以上で例題2の証明は終わるが、よく知られている2次方程式の根と係数の関係を用いて、以下のように示す方法もある。