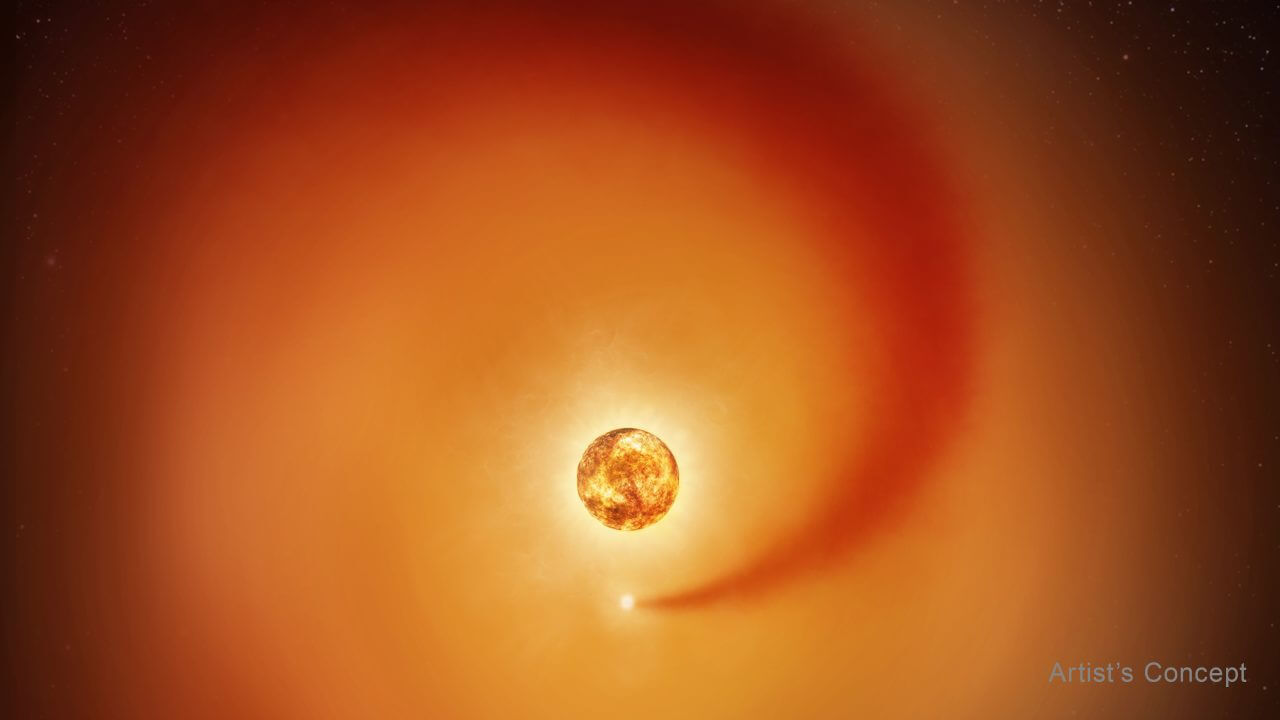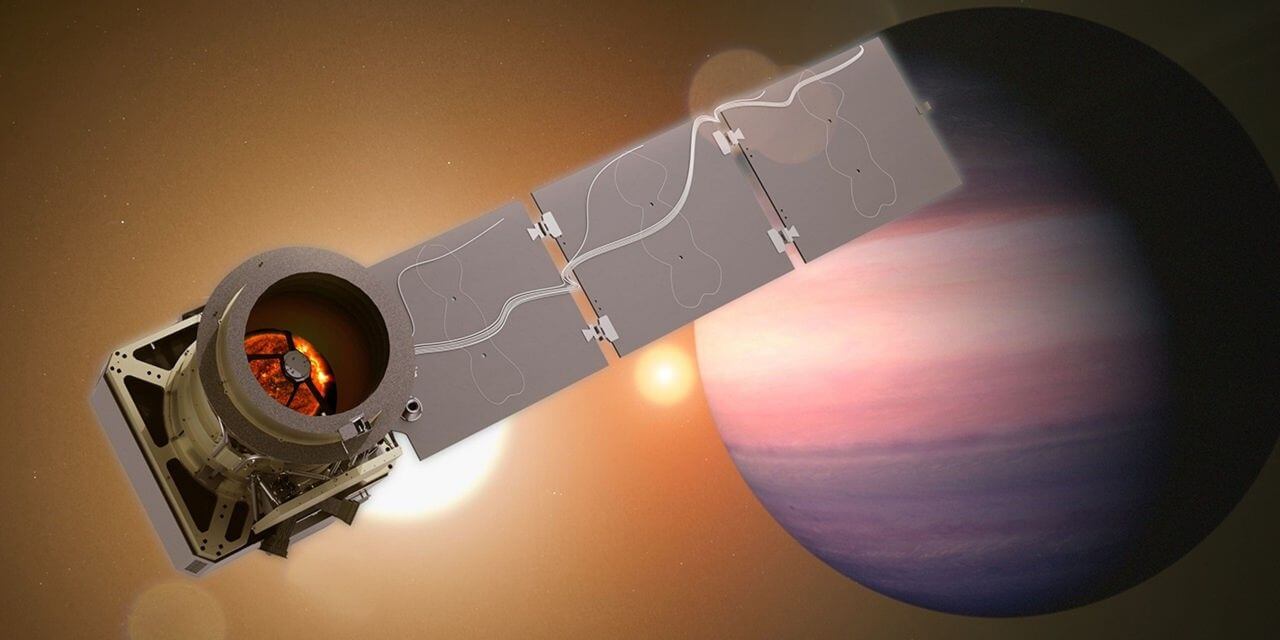未来シナリオとしての「社会資本主義」の提唱

ipopba/iStock
2025年七夕の日に、京大と日立製作所は共同研究の成果の一つとして、「AIを活用した、持続可能な日本の未来に向けた政策提言」(以下、政策提言グローバル版)を行った。
このグループは、地球社会の現在と未来に関わる294指標を抽出して、因果モデルを作成し、2050年に向けた2万通りのシミュレーションを実行し、図1のような7つのシナリオを作成した。
図1 地球社会の未来シナリオと分岐構造 (出典)京都大学成長戦略本部(2025年7月7日)発表資料による
シミュレーション次第でどのような未来も描き出せる
一般的にいえば、simulation(dissimulationも含む)は現状分析以上に未来予測には不可欠の手法ではあるが、大きな陥穽にはまる危険性が共存する。どうしても研究者にとって問題意識に合うようなデータを選びたがる傾向があるからである。
「地球温暖化」論で多用されるsimulation(シミュレーション)について、かつて私は、本来の意味としては「そうでないのに、そうであるふりをする」ために、多用されていると解釈したことがある。
反面、dissimulation(ディスシミュレーション)は、「そうであるのに、そうでないふりをする」場合に使われる。これは英語辞典、たとえばOxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English所収の、simulation関連の英文“the act of pretending that something is real when it is not”でもよく分かる。
WordReference.com Language Forumsの例文
さらにネットで公開されているWordReference.com Language Forumsによれば、
They both involve pretense. Simulation is pretending that something which is not there does exist or is present.
Dissimulation is pretending that something which is there does not exist or is absent.
このシミュレーション関係の英文から、シミュレーションに大きく依存した50年後や100年後二酸化炭素濃度の予測値などは、入力データ次第で変動するし、そのデータ分析も科学的合理性があるとは限らないという自分なりの結論に到達した。
望ましい未来像とはいえないシナリオ
2万もの指標を使ってシミュレートした結果、7通りの分岐構造を示した図1では好ましいシナリオが2種類得られたが、残りの5つは「望ましい未来像とはいえない」(政策提言グローバル版)シナリオと判断された。
確かに
シナリオ4:ウェルビーイング・環境配慮不足シナリオ シナリオ3および5:気候・紛争ダブル危機シナリオ シナリオ6:経済成長至上シナリオ
シナリオ7:二極化シナリオ
などは、望ましくないであろう。
好ましいシナリオは2種類
一方で、政策提言グローバル版で高い評価がなされたシナリオは、
シナリオ1:地域分散・成熟シナリオ シナリオ2:グリーン成長・協調シナリオ
であった。
まずシナリオ2については、「経済・環境面での比較的良好なパフォーマンスの反面、先進国内の格差や国際紛争などの課題が残る社会像」であるから、「国際的な協力行動が特に重要な鍵となる」としている。
もう一つのシナリオ1では、「経済の成熟化を是認した上で、地球上の各地域が分散しつつ一定の自律的均衡や環境保全そして平和と安寧を実現していくような姿」が予想された。それはローカルな地域レベルでの経済循環や持続可能性を重視しつつ、ナショナル、グローバルへと積み上げていく未来像である。私もこのような動向に「ローバル時代」や「ローバリゼーション」と命名して、注目してきた。
ローバル時代(The Lobal Stage)
ここでいう「ローバル時代」とは、周知の、
glocal = global + local 【Think Globally, Act Locally.】
にヒントを得て、私が
lobal=local + global 【Think Locally, Act Globally.】
として再構成した概念である。
20世紀の終盤あたりから、グローカルという表現が定着したが、すでに現在では<glocal = global + local>という等式ではなく、むしろ時代はローバル<lobal=local + global>に急速に移行しているように思われる。
広井による説明の問題点
京大・日立製作所合同のレポート「政策提言グローバル版」での解説はやや簡単なので、もっと詳しい説明をこのプロジェクト責任者であった広井が行っている(広井、2025)。これに沿って、7通りのシナリオ全体を概観したうえで、いくつかの問題点を指摘してみよう。
まず最初に「好ましくない」とされた「二極化シナリオ」(シナリオ7)の理由は、「先進国が地球全体の資源・環境の主要部分を独占する」(同上:4)だからである。
これを避けるには、
- 先進国が化石燃料使用量や一人当たりエネルギー消費量の削減など、環境重視の対応を早急に進めること
- 途上国における一人当たりGDP増加や社会インフラ整備など、途上国の経済発展を促すような対応を積極的に行うこと
を並行して広井は挙げている。
二酸化炭素地球温暖化論者の理由と酷似
しかしこの両論併記では新鮮さに欠け、かねてからの二酸化炭素地球温暖化論者の理由と酷似しており、説得力を持っていない。
なぜなら、先進国が環境重視に転換してかりに二酸化炭素の排出量を削減しても、途上国のGDP増加、インフラ整備、経済発展を促すのであれば、それまでの先進国と同じように化石燃料使用量や一人当たりエネルギー消費量が地球全体では増加するからである。
この両論併記は、少なくとも地球全体の環境重視の策とはいえない。
「地域分散・成熟シナリオ」(シナリオ1)にも課題が残る
京大・日立製作所「政策提言グローバル版」でも広井の説明でも「シナリオ1」への期待が大きいが、それは「経済面では成長が鈍化する一方、地球全体のCO2排出量などは良好なパフォーマンスを示す」ことが期待されたからである。その反面、「国際的な紛争」が「大きく減少する」し、「先進国・途上国」の格差が縮小するからでもある。
しかし広井の説明では、「紛争の減少」や「国際格差の縮小」に至る道は示されておらず、単なる希望の表明でしかなく、希望的観測(wishful thinking)がのべられたにすぎない(同上:4)。
「グリーン成長・協調シナリオ」(シナリオ2)について
この「シナリオ2」も、広井は「先進国・途上国ともに経済発展が持続するとともに、地球全体のCO2排出も減少し、・・・・(中略)先進国・途上国間の国際格差は減少する」とみており、高い評価をしている。この条件としては「国際的なレベルでの協力的意識・行動が際立って重要である」(同上:5)とものべている。
ただここでも「国際的なレベルでの協力的意識・行動」を促進する方法については皆無であり、国際的なコンフリクトが無くなる方法がいくらかでも示されないと、その先に議論は進まない。
「ローマクラブ」の手法に新しい要因を加えたシミュレーション
1972年の「ローマクラブ」の手法と比べて、2025年の「政策提言グローバル版」で加えられた新しい要因とは、地球温暖化、経済と格差、先進国と途上国、ウェルビーイングを含む社会的側面などの指標を意味するが、AI活用といえども解決できない根本問題が残っているように思われる。
「政策提言グローバル版」のメンバーの一人である嶺によれば、使用した社会指標は149、それらの間の因果関係数は333になった(嶺、2019:2)。
これらを踏まえて、AI活用グローバル版の更なる深化に必要な課題を2点に絞ってまとめておこう。
「GDPと二酸化炭素の排出量が正の相関」を受け止めたシナリオか
一つは、図2で示したGDPと二酸化炭素の排出量が正の相関を示すことにどのように対処するかである。
この最悪の見本はシナリオ6「経済成長至上シナリオ」ではあるが、「経済・環境面での比較的良好なパフォーマンス」や「経済の成熟化」でも、GDPと二酸化炭素の排出量の間には正の相関があることを忘れてはいけない。
その意味で、「シナリオ2」を評価する理由とされた「先進国・途上国ともに経済発展が持続するとともに、地球全体のCO2排出も減少」などはありえないと考えられる。かりに地球上全体で経済発展が持続するのであれば、自然法則として地球全体のCO2排出も必ず増大するとみておきたい。
シナリオ6への批判
広井は「経済成長至上主義シナリオ」(シナリオ6)への批判として、「先進国・途上国ともに高い経済成長を果たすが、地球全体のCO2排出がもっとも増加するなど環境悪化が進む」(同上:5)とした。それならば、図2のGDPと二酸化炭素の排出量間の正の相関は分かるであろう。
図2 GDPと二酸化炭素の排出量 (出典)『平成23年版 環境白書』:19
(注) 国連統計部資料及びOECDfactbookより環境省作成
意味不明な「脱成長」という訳語
図2は、1990年から2007年までの折れ線グラフであるから、高い経済成長と増大したCO2の関連は一目瞭然なのではないか。いつの時代でも両者間に正の相関があることは自明である。経済成長を目指しGDPを増やそうとすれば、必ず二酸化炭素の排出量は増大する。「シナリオ6」はまさしく図2の延長線上に存在する。
しかし、IPCCの論理やそれを受けた大手の出版社や新聞社では、途上国における石炭火力発電による経済成長政策は放置して、G7などの先進国での経済成長を止め、degrowthやdécroissanceを意味不明な「脱成長」と訳したりしてきた(金子、2023)。さらにG7などが経済成長を止めたら、途上国支援のためのODAが激減することを忘れたかのような議論が横行してきた。
「国際的な協調性」は簡単ではない
「シナリオ2」では「国際的な協調性」が重要な鍵としてされてはいるが、G7では軒並み高齢化が進行しているので、今後はODAの増額よりは内政の主要分野である「社会保障」からの圧力が高まるので、ODA総額の伸びは期待できない。これで困るのはもちろん途上国であろう。
ウクライナ侵略戦争やイスラエルのガザ地区攻撃に見られるように、国連の安保理の無力が証明された世界情勢では、「国際的な協調性」は簡単には得られそうもない。「国際的なレベルでの協力行動が特に重要なカギとなる」(同上:5)ことは自明だが、AIおよび政策提言グローバル版そして広井はどのような「国際協調案」をまとめるのだろうか。
人口変動への対処
2点目の課題は先進国と途上国あるいはグローバルノースとグローバルサウスでもいいのだが、人口変動への積極的な着眼を行うことにより、「老化の波」(age wave)と低出生数による人口減少への具体的対応を描いておきたい。
確かにシナリオグループ解釈の際には、それらの社会指標を人口、財政、地域、環境・資源、格差、健康、幸福の8つの観点で評価したとある(嶺、前掲論文:4)。ただし、表1で人口データの何を使ったかはこの説明では不明であった。
表1 シナリオ解釈結果(出典)嶺、2019:4.
2052年における各シナリオグループの社会指標を人口,財政,地域,環境・資源,雇用,格差,健康,幸福の8つの観点で評価した。2018年と比較し,数値が向上・好転している指標を○,低下・悪化している指標を×,変化が少ないものを△で表現した。
出生率を下げるだけでは済まされない
地球的レベルでは、ワイズマンのいうような「死亡率を上げることには誰もが反対する以上、人口を減らしたければ、選択肢は一つしかない。出生率を下げることだ」(ワイズマン、2013=2017:270)かもしれないが、この総論だけでは済まされない。
なぜなら、G7に象徴される先進国で人口減少が進めば、途上国へのODAをはじめとした借款やさまざまな支援が廃止もしくは減額される可能性が予想できるからである。
世界全体のODA総額は2237億ドル(暫定値、約34兆2000億円)
その代表はODAであり、経済協力開発機構(OECD)は11日、2023年の世界の政府開発援助(ODA)実績が22年比2%増の計2237億ドル(暫定値、約34兆2000億円)だったと発表している(外務省ホームページ)。
また、上位のランキングは図3の通りである(同上)。また、国民負担額では図4のようになっている。単位はドルだが、31カ国からのODAが途上国に出されているのである。
図3 援助国のODA実績の推移(支出総額ベース)
図4 DACメンバー(EU除く)における政府開発援助実績の国民1人当たりの負担額(2023年)
ODA総額は減少
アメリカやオーストラリアを除く31カ国の大半が少子化によって人口減少に直面しているのだから、地球全体での出生率の低下が特効薬だとは思われない。世界的にみれば高齢化率が高まり、社会保障財源確保の選択肢が優先されて、ODA総額は減少する一途をたどるはずである。それぞれの国が置かれた立場を考慮したうえでの「未来シナリオ」を作成して、人口政策や家族計画の実践しかとる道はないであろう。
国際協調の道筋が示されないまま、人口減少と高齢化に直面する先進国の経済的停滞により、ODA総額の伸びはもはや期待できない時代になっていると思われる。
経済の成熟化とは何か
広井は「地域分散・成熟シナリオ」(シナリオ1)を高く評価して、「地球上の各地域が分散しつつ一定の自律的均衡や環境保全そして平和と安寧を実現していくような姿」(同上:6)として、「地球社会の未来像」を描いた。
私もまた「シナリオ1」が理念レベルでは一番優れていると感じるが、「成熟化」を前提とした「地産地消」ではどの程度のCO2の排出量が好ましいか。あるいは「脱成長」した先進国のCO2の排出量の制限や、先進国へ追いつくために途上国のCO2排出量増大への基準が示せるのかといえばそれはかなり困難だと感じる。
さらに「グリーン成長」や「脱成長」そして「定常型社会」でも、経済成長しない政策を続けるだけでは、その維持すらも不可能になってくるという現実も想定される。
万人のための地球
「シナリオ1」の視点は正しいが、そこでは人類の宿痾としてのAgesim(年齢差別)、Racism(人種差別)、Sexism(性差別)への正しい認識と解決への絶え間ない努力が求められる。そのきっかけの一つが貧困からの脱出である。そのためにもdegrowthやdécroissanceを「脱成長」ではなく「非成長」「衰退」「衰微」と正しく訳すことである。
元来‘de’は下降、反対、剥奪、分離、除去、否定、強意、悪化などを意味する接頭辞なのであり、「脱」という訳語にはならないと考えるからである。そこからのみ‘Giant Leap’への道筋が見えてくるのではないか。
第2節 「社会資本主義」提唱の意義
「社会資本主義」
このように、京大・日立製作所が発表した「地球社会の未来シナリオ」(図1)は、多方面からの賛否両論を含む建設的な議論を引き起こすものである。私もまた2023年に、「資本主義終焉のその先」を「社会資本主義」という用語に託して「未来シナリオ」を提唱したので、その観点から図1「地球社会の未来シナリオと分岐構造」への論点を提示してみたい。
「社会資本主義」とは、様々な領域で破綻が目立つようになった現在のグローバル資本主義の課題を克服し、より持続可能で公正な社会を目指す新しい経済社会システムを指す概念とした。
「社会資本主義」の三本柱
具体的には三本柱として、「治山治水」を含む「社会的共通資本」、人とのほどよい関係がもたらす「社会関係資本」、政府の「こども真ん中政策」に呼応した家庭と近隣での子育てから作り出される「人間文化資本」の3つの資本を融合させ、世代間の協力や社会移動が可能な開放型社会を目指すものである。
それにより、経済社会システムは使用可能な手持ちの社会資源を最大限活用して、機能面で「適応能力向上」(adaptive upgrading)を維持することができるとした。
歴史的背景
この「社会資本主義」は、従来の資本主義が抱える問題、例えば、格差の拡大や環境問題、将来不安などを解決するために、新しい資本主義のあり方を提示することが期待される。
そこに至る経緯は金子(2023:第5章)に詳しいが、マルクス、ウェーバー、高田保馬、パーソンズらの社会学古典に導かれながら、資本主義の終焉後の到達点として、「社会資本主義」を新しく造語したのである。なぜなら、「脱」や「後」の表現では目標地点が分からないからである。
「次」や「脱」ではイメージが収斂しない
かつての「ポストモダン」論や現在の「資本主義の終焉」論の領域でも、「その後」「その先」という以上に表記が進まず、この傾向は残念ながら今日まで続いている。
たとえば「次」や「脱」の名称が明記された経済社会学的研究には、ベル「脱工業社会」(1973=1975)、ハーヴェイ「ポストモダニティ」(1990=1999)、サター「減成長」(2012=2012)、ラトゥーシュ「脱成長」(2019=2020)、斎藤幸平「脱成長コミュニズム」(2020)、カリスほか「脱成長」(2020=2021)などたくさんある。
しかしいずれも「次」や「脱」のあとに控える目標地点として、経済社会システムの名称の具体的な表現がなされてこなかった。
同じく社会学の領域からも、「世界史的な視野から見れば、現代資本主義の将来はきわめて不透明である」(プラマー、2016=2021:130)という指摘がなされ、経済学でも社会学でも「新しい資本主義」の将来像が鮮明にはなっていない。
行く先の港のない船にはどんな風も役に立たない
ただアーリのいうように、いくら移動型社会(アーリ、2016=2019)になっても、個人も社会システムもその目標地点が不明であれば、どこを目指していいのか分からない。
『エセー』にいわれるように、「行く先の港のない船にはどんな風も役に立たない」(モンテーニュ、1588=1966:239)は時代を越えて真理である。なぜなら、経済社会システムを動かす「資本主義エンジン」(シュムペーター、1950=1995:176)や「経済エンジン」(ハーヴェイ、2014=2017:15)がいくら快調でも、「新しい資本主義」の進む方向が鮮明でないと、アイドリングのままで無駄に社会資源を消費してしまうからである。
京大・日立製作所政策提言グローバルグループの大谷がいうように、「『自分らしさ』を尊重し、おのおのが創意工夫した人生を織りなすことができる社会こそ、われわれがめざすべきポストコロナ社会の未来である」(大谷、2012:12)。ただし「ポストコロナ社会」ではせっかくの未来シナリオが鮮明にならないので、代わりに「社会資本主義」の活用を期待する。
さて以下は、AI による『社会資本主義』の概要であるが、著者が知らないうちにネットに掲載されていた。A4でわずか1頁に大変うまく要約されており、二重の意味でなんとも恐ろしいAI時代が到来したと感じている。
本稿で扱った京大と日立製作所は共同研究の成果の一つとして、「AIを活用した、持続可能な「日本の未来に向けた政策提言」もAI依存なので、AIによる『社会資本主義』要約もまたその内容の精緻化に有益であろうと考えている。私にはAIを使いこなす技術がないので、政策提言グローバル版をまとめられた方々には拙著の内容もそれにぜひ活用していただければと願っている。
「社会資本主義」とは、既存の資本主義の課題を克服し、より持続可能で公正な社会を目指す新しい経済システムを指す概念です。具体的には、「社会的共通資本」「治山治水」「社会関係資本」「人間文化資本」の3つの資本を融合させ、世代間の協力や社会移動が可能な開放型社会を目指します。
詳細:
「社会資本主義」は、金子勇氏によって提唱された概念で、従来の資本主義が抱える問題、例えば、格差の拡大や環境問題、将来不安などを解決するために、新しい資本主義のあり方を提示するものです。
3つの資本の融合:
教育、医療、福祉、インフラなど、社会全体の生活の質を支える基盤となる資本です。これらの資本を重視することで、持続可能な社会の実現を目指します。
地域社会のつながりや、人々が互いに信頼し協力し合う関係性を指します。この資本を育むことで、より活力ある社会を構築することを目指します。
個人の知識やスキル、教育、文化的な素養などを指します。この資本を重視することで、一人ひとりが成長し、自己実現できる社会を目指します。
「社会資本主義」の目指すもの:
環境問題や資源の枯渇といった課題に対処し、将来世代にも豊かな社会を残せるようにします。
格差を是正し、すべての人が安心して暮らせる社会を目指します。
地域社会のつながりを重視し、人々が主体的に社会に参加できる社会を目指します。
世代間の協力や社会移動が活発に行われる、変化に対応できる社会を目指します。
「社会資本主義」は、既存の資本主義を否定するものではなく、その課題を克服し、より良い社会を目指すための新しい視点を提供します。
【参照文献】
- Aghion,P.,Antonin,C., and Bunel,S.,2020,Le Pouvoir de la destruction créatrice, Éditions Odile Jacob.(=2022 村井章子訳 『創造的破壊の力』東洋経済新報社).
- Bourdieu,P.,1979,La distinction:critique social de judgement, Éditions de Minuit.(=2020 石井洋二郎訳『ディスタンクシオン1』[普及版] 藤原書店).
- 濱田康行,2025,『資本主義の次に来るもの』22世紀アート.
- Harvey,D,2011.The Enigma of Capital and the Crises of Capitalism, Profile Books.(=2012森田成也ほか訳『資本の(謎)』作品社).
- Harvey,D,2014.Seventeen Contradictions and the End of Capitalism, Profile Books.(=2017 大屋定晴ほか訳『資本主義の終焉』作品社).
- 広井良典,2001,『定常型社会』岩波書店.
- 広井良典,2025,「日本発の『政策提言AI』が警告!」『東洋経済オンライン』7月24日:1-7.
- 廣田尚久,2021,『共存主義論』信山社.
- 金子勇,2000,『社会学的創造力』ミネルヴァ書房.
- 金子勇,2014,『日本のアクティブエイジング』北海道大学出版会.
- 金子勇,2023,『社会資本主義』ミネルヴァ書房.
- 金子勇,2024,「『世代と人口』からの時代認識」金子勇編『世代と人口』ミネルヴァ書房:1-71.
- Kornai,J.,2014,Dynamism,Rivalry,and the Surplus Economy, Oxford University Press.(=2023 溝端・堀林・林・里上訳『資本主義の本質について』講談社).
- 間宮陽介ほか,2023,「もうひとつの資本主義へ-宇沢弘文という問い」『世界』no.970 岩波書店: 158-168.
- 松島斉,2023,「新しい資本主義、新しい社会主義」『世界』no.970 岩波書店:176-185.
- Michel de Montaigne,1588,Les Essais de Michel de Montaigne,(éd.) Pierre Villey,Paris,Felix Alcan.(=1966 原二郎訳『モンテーニュⅠ』筑摩書房).
- Milanovic,B.,2019,Capitalism,Alone,Harvard University Press.(=2021 西川美樹訳『資本主義だけ残った』みすず書房).
- 嶺竜治,2019,「持続可能な未来の実現に資する『政策提言AI』」 『日立評論』Vol.101 No.3:1-5.
- 宮本憲一,1967,『社会資本論』有斐閣.
- 大谷和也,2021,「AIと予測するポストコロナの未来」『ナレッジ&コラム』日立コンサルティング:1-13.
- Parsons,T.,1971,The System of Modern Societies,Prentice-Hall,Inc.(=1977 井門富二夫訳『近代社会の体系』至誠堂).
- Putnam,R,D.,2000,Bowling Alone:The Collapse and Revival of American Community,Simon & Shuster.(=2006,柴内康文訳『孤独なボウリング』柏書房).
- Plummer,K.,2016,Sociology: The Basics, Second Edition, Routledge.(=2021 赤川学監訳 『21世紀を生きるための社会学の教科書』筑摩書房).
- Schumpeter,L.A.,1950,Capitalism,Socialism and Democracy,3rd.(=1995 中山伊知郎・東畑精一訳『資本主義・社会主義・民主主義』(新装版)東洋経済新報社).
- Streeck,W.,2016,How Will Capitalism End?Essays on a Falling System,Verso.(=2017 村澤真保呂・信友建志訳『資本主義はどう終わるのか』河出書房新社)
- シュトレーク,2023, 「グローバル化と民主主義はどこへ」(インタビュー)週刊エコノミスト編集部編『週刊エコノミスト』第4792号 5月9日):25-27.
- Urry,J.,2016,What is the Future? Polity Press Ltd.(=2019 吉原直樹ほか訳『<未来像>の未来』作品社)
- 宇沢弘文,2000,『社会的共通資本』岩波書店.
- Weisman,A.,2013, Countdown: Our Last, Best Hope for a Future on Earth? Little Brown.(=2017 鬼澤忍訳『滅亡へのカウントダウン』(上下)早川書房).