本質を見抜く“観察力”を身につければ、人生も社会もさらに豊かになる─観察の達人クリスチャン・マスビアウが教える、物事を本当に「見る」方法(クーリエ・ジャポン)
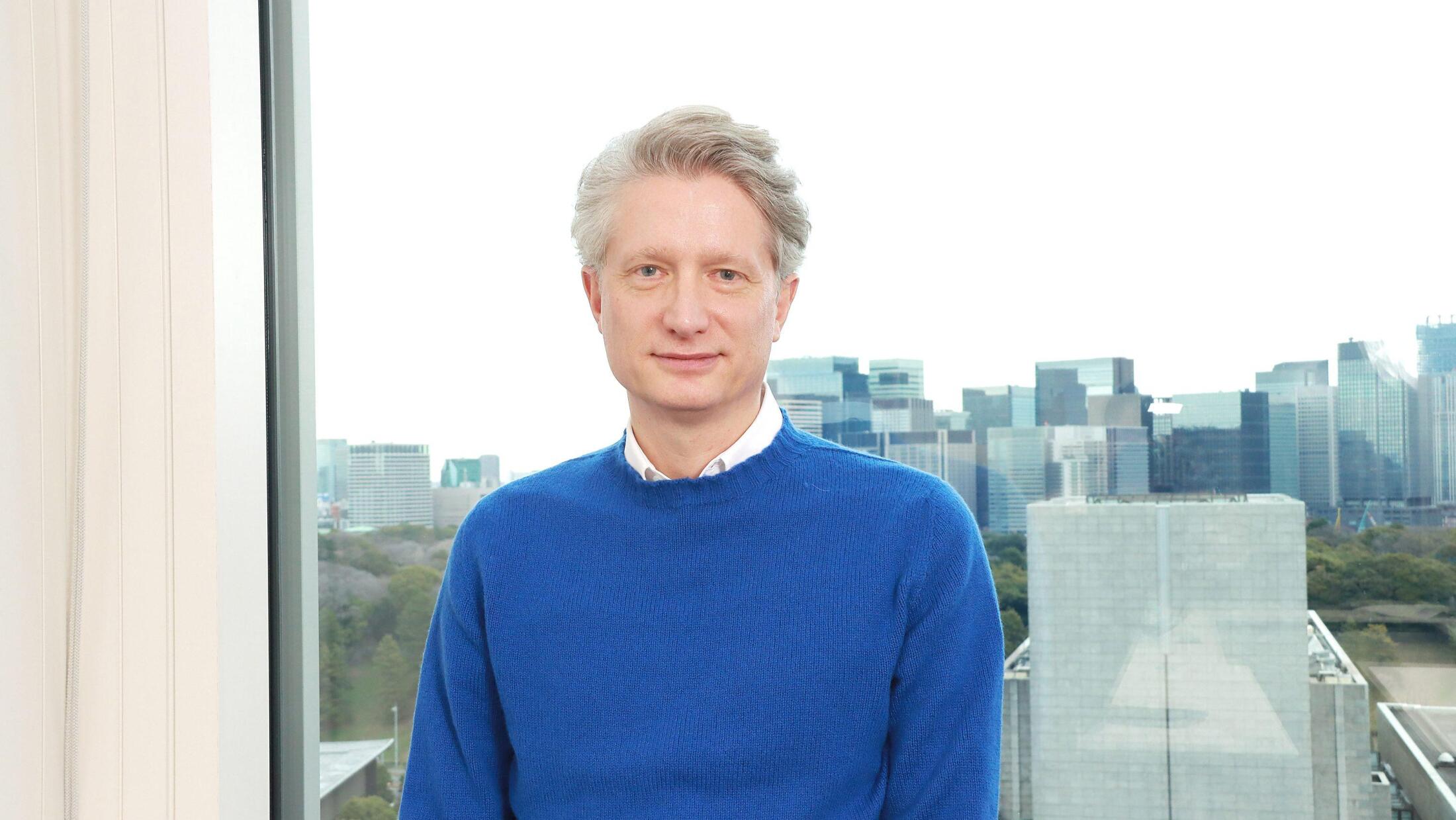
──マスビアウさんの前著『センスメイキング 本当に重要なものを見極める力』、そして新たに邦訳された著書『心眼 あなたは見ているようで見ていない』は、人文・社会科学は象牙の塔のなかだけではなく、実世界においてもっと価値を発揮できるという立場で書かれています。 また、マスビアウさんはその実践として、自ら設立された戦略コンサルティング会社「ReDアソシエーツ」にて、文化人類学、社会学、歴史学、哲学などの専門家を揃え、大きな成果を出しています。 人文科学や社会科学がとりわけビジネスの世界にもっと役立つはずだという確信に至ったきっかけは何だったのでしょうか。 私にとっては、それは自明のことでした。私は大学で哲学を専攻しました。哲学はまるで実世界から離れた純粋にアカデミックなものとして教えられることもありますが、噛み砕いてみると、きわめて実用的なものだと感じたのです。 せっかく大学でそのように実用的なツールを身につけたのですから、社会に出てそれを活用しない手はありません。 そもそも、一方には商業やものづくりの世界があって、他方には人文・社会科学のアカデミックな世界があるというように、わざわざ分ける必要がなぜあるのでしょうか。 人文科学や社会科学は、人の生活や人生について理解するためのツールです。そして人間を相手にする以上、それはどの業界にも応用できます。 メーカーが作ったものを買うのは人間です。病院の患者も人間です。メディアの読者も人間です。人間のことをしっかり理解できていなければ、真によいビジネスをおこなうことはできません。 もちろん、量的な測定やデータも重要ですが、それと同様に、数値や統計だけでは見えてこない質的なものを明らかにする人文・社会科学も、世界を理解する方法としてきわめて有効なのです。 ──マスビアウさんは、データなどの客観的知識だけでなく、主観的知識や五感で得られる知識も重要だとおっしゃっています。ところが最近、後者はますます軽視される傾向にあるようです。物事について自分で観察・体験したうえで考察してみようとするのではなく、データや数値から決まった結論を引き出そうとする姿勢が顕著になりました。これはまさに、現在急速に進化を遂げている生成AIの得意分野です。 何でも生成AIに聞こうとする現代の人々は、古代ギリシアでデルフォイの神託をこぞって聞きに行った人々に似ていると思います。すべての答えをマシンから得たいという欲求は、神からのお告げを受けたいという古代の欲求に通ずる、時代を超えたものなのではないでしょうか。 けれども私は、観察や思考を機械にアウトソーシングして、そこから答えを得るだけの人生は、おもしろくないのではないかと思います。 実はこれは、私が『心眼』を書こうと思ったきっかけのひとつでもあります。 私は米国の大学で教えているのですが、学生や私の周囲の若い人々があまり幸福に見えないなと思いました。特に、コロナ禍で他人や世界との関係が希薄になり、抽象的なものになっていくにつれ、この傾向も目立つようになりました。 私はそこに何らかの相関関係があると考えました。そうだとしたら、若い人たちが自分の人生をもっと楽しむには、世界を画一的な場所として抽象的に理解するのではなく、豊かで多様性に富む場所としてダイレクトに理解できるようになる必要があります。 そのためには、世界に注意を払い、見なければならない。では「注意を払う」とはどのようなことなのだろうか。それを考察しようと思ったのです。



