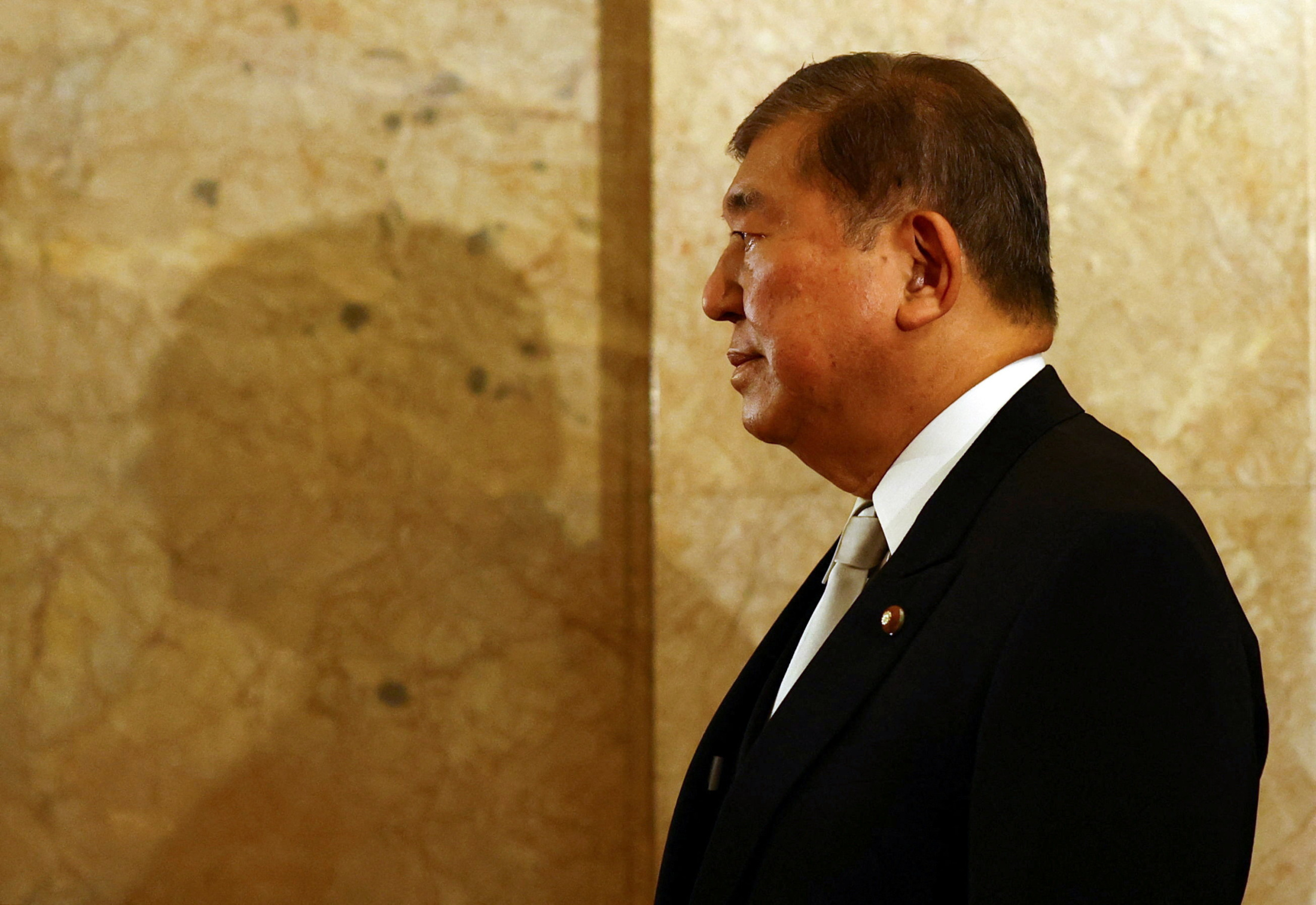絶滅した人類の近縁種の手の化石、「驚くべき」特徴が明らかに

パラントロプス・ボイセイは、長い親指とまっすぐな指によって、現代人がハンマーを握るような力強い握力を発揮できたと考えられる/Louise Leakey
(CNN) 絶滅した人類の近縁種として知られる、史上初の手の化石がケニアで発掘され、予想外に器用な手先とゴリラのような握る力を持つ種族の存在が明らかになった。頭蓋骨(ずがいこつ)や歯の化石と共に発見されたこの手の骨から、初期の人類が石器を使用していた可能性が示された。
「パラントロプス・ボイセイ」はこれまで、特徴的な頭蓋骨や、現生人類の最大4倍の大きさの臼歯がある巨大な歯によってのみ特定されていた。このため、パラントロプス・ボイセイの体の他の部分の形状や、環境との関わりについてはわかっていなかった。だが、そのあごに備わっていたであろう巨大な咀嚼(そしゃく)筋と食習慣について仮説が立てられ、これが「くるみ割り人形」というあだ名の由来となった。
驚くほど保存状態の良い手の骨は、長い親指と、まっすぐな指、可動性のある小指で構成されており、この種は現代人がハンマーを握るような強力な握力を発揮することができたと考えられる。指の骨の幅広さなど他の特徴はゴリラによく似ている。
この部分的な骨格はトゥルカナ湖の東端に位置するクービ・フォラ遺跡で発掘され、152万年以上前のものと推定されている。歯と頭蓋骨の化石は、これまで研究されてきたパラントロプス・ボイセイの標本と一致した。一方、手足の骨は、これまで研究されてきたホミニン(ヒト族)の中でも特異なものであることが判明した。
米ニューヨーク州立大学ストーニーブルック校の古人類学者で助教のキャリー・モングル氏は「パラントロプス・ボイセイを特定の手足の骨と確実に結び付けることができたのは今回が初めてだ」と述べた。モングル氏はネイチャー誌に掲載された論文の筆頭著者。
独マックス・プランク進化人類学研究所の人類起源部門のディレクター、トレイシー・キベル氏によると、この手の化石は「全く予想外のもの」だったという。
キベル氏は「これは明らかに人類の祖先の手だが、ゴリラと驚くほど類似した特徴も持ち合わせており、驚きだ」と述べた。
キベル氏は「我々が知る限り、これほどゴリラに似た手の形態を持つホミニンは他にいない。これは、人類の手の使用における進化史において何が『可能』なのかという視点を大きく広げてくれる」と述べた。キベル氏は今回の研究に関与していない。
重要な疑問
パラントロプス・ボイセイは130万年前から260万年前にかけて東アフリカに生息しており、少なくとも3種のホミニン(ホモ・ハビリス、ホモ・ルドルフエンシス、ホモ・エレクトス)と共存していた。
一部の研究者は、ヒト属の種だけが石器を作る能力を持っていたと仮説を立てていたものの、近年の発見によりその仮説は覆された。ケニアで発掘された290万年前の石器は、ホミニンの系統樹において、道具の使用がかつて考えられていたよりも広範囲に及んでいたことを示唆している。
ホミニンにはヒト属の種が含まれる。例えば、現生人類のホモ・サピエンスや、4万年前に絶滅したネアンデルタール人のような比較的最近絶滅した種、ホモ・エレクトスのような初期のヒト属の種、エチオピアで発見されたルーシーの骨格で知られるアウストラロピテクス・アファレンシスのような遠縁の種だ。
モングル氏は、パラントロプス・ボイセイの手の形状から判断すると、当時アフリカに生息していた他のヒト属と同様に石器を巧みに扱うことができただろうとの見方を示した。
米スミソニアン国立自然史博物館の古人類学者ライアン・マクレー氏はCNNに、「この論文はパラントロプスが道具を製作・使用したと断言せず、手の解剖学的構造にそれを妨げる要素が本質的に存在しないとしている」と述べた。「化石となった手から石器が発見されたという決定的な証拠、あるいは(1種の)ホミニンしか存在しない遺跡で発見された石器がなければ、誰がこれらの道具を作ったのか、誰が作らなかったのかを確実に知ることはできないかもしれない。だが今回の論文は『道具製作者はパラントロプス』という仮説にとって大きな一歩だ」。マクレー氏は今回の研究に関与していない。
論文によれば、ネアンデルタール人やホモ・サピエンスといった後世の人類は手首の構造が異なり、パラントロプス・ボイセイも同時代の人類と同様に、指を正確につまむことはできなかった可能性が高いという。
手の化石は、パラントロプス・ボイセイがゴリラと同様の握る能力を持っていたことを示唆しており、食べにくい植物をつかんで皮をむき、消化できない部分を手で取り除くことができたと考えられる。
力強い手は、この種が木登りに優れていたことを示唆する一方、足にはアーチがあり効率的な動きを可能にしていた。これは、この種が間違いなく二足直立歩行に適応していたことを意味するとモングル氏は指摘した。
マクレー氏は「手と足の形態学的な特徴を総合すると、この種は樹上生活(木登り)を行わなかった可能性が高いと著者は示唆している。ただし、ゴリラとの手の形態的な収れんは、硬い食物を処理するために手をどのように使用したかに起因する可能性が高い。これは理にかなっている」と述べた。
化石は、論文の共著者のルイーズ・リーキー氏が率いるチームによる2019年から21年にかけての発掘調査で発見された。1950年代、リーキー氏の祖父母である著名な古人類学者のルイス・リーキー氏とメアリー・リーキー氏は、現在のタンザニアで初めてパラントロプス・ボイセイの頭蓋骨を発見し、「くるみ割り人形」というあだ名を付けた。ただ、この種の歯の摩耗の痕は、ナッツのような硬い食物を割るのではなく、塊茎や根などの硬い食物をかみ砕いてすりつぶすことで生き延びていたことを示している。