「日本は遅れてなんかない」1000社以上のAI企業をみたシバタナオキが語る、アフターAI時代が“日本に好機”な理由 - エンジニアtype
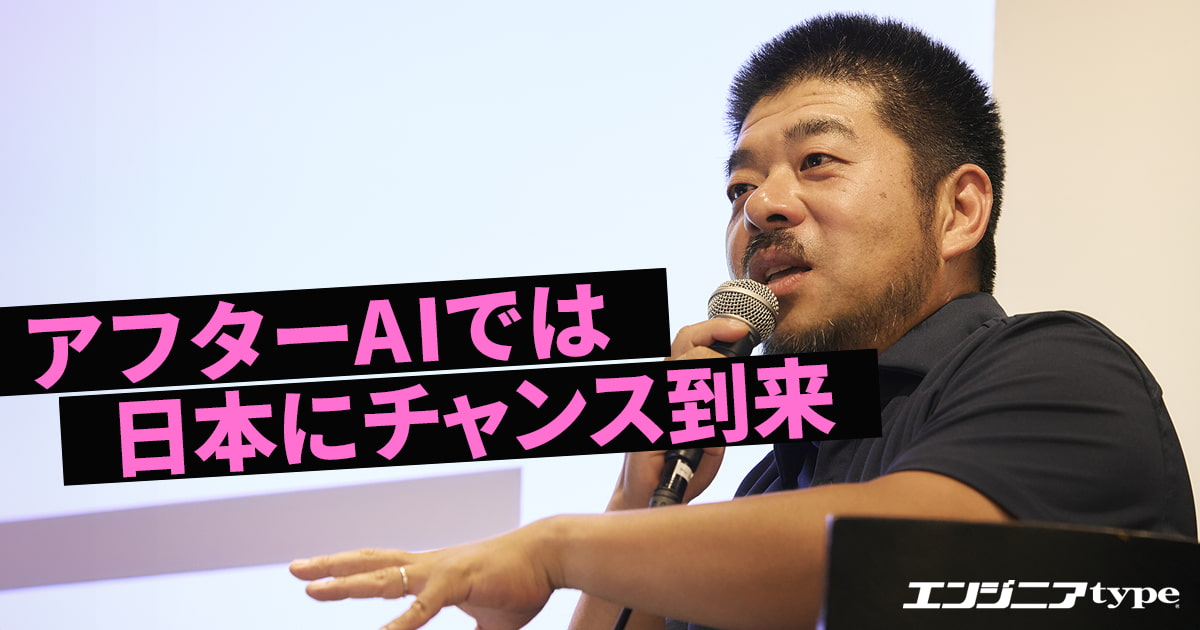
AI競争で日本は世界に遅れを取り、「もう手遅れ」「追いつけない」という声も一部では聞こえる。
だが、その意見に異を唱える人もいる。
楽天の社長室でキャリアを始め、シリコンバレーでAppGroovesを創業。世界最大級のASOツールを立ち上げ、10万社超に使われるまで育てた投資家・シバタナオキさんは語る。
「日本は遅れてなんかいない」
シリコンバレーを中心に1000社超の生成AIスタートアップを精査し、数十社へ投資してきまた彼が見つけた、“アフターAI”時代に日本が逆転できる理由とは——。
※本記事は、2025年9月5日に開かれた『アフターAI 世界の一流には見えている生成AIの未来地図』(著:シバタ ナオキ)刊行記念イベントの内容を一部抜粋・編集したものです。
『アフターAI』著者 シバタナオキ(@shibataism)
元・楽天株式会社執行役員(当時最年少)、東京大学工学系研究科助教、スタンフォード大学客員研究員。東京大学工学系研究科博士課程修了(工学博士、技術経営学専攻)。著書に『MBAより簡単で英語より大切な決算を読む習慣』『テクノロジーの地政学』(日経BP)がある
1000社以上のAI企業を見てきた
私は新卒で楽天に入社し、ほとんどを社長室で過ごしました。
TBSとの交渉、プロ野球参入。会社が急速に変化する現場を間近で見ていました。
20代後半にはインターネットやフィンテック領域の新規事業にも参加。「どうやってテクノロジーがビジネスを変えるのか」を肌で感じる日々でした。
その後、大学教員職を得てから、スタンフォード大学に研究員として2年滞在。帰国予定でしたが、カリフォルニアの気候と自由な空気に惹かれ、現地で起業しました。
アメリカで会社を立ち上げ、採用も解雇も資金調達も清算も、全て自分の手で行ったことは良い経験でしたね。
本格的に投資に携わるようになったのは2年前からです。エンジェル投資を経て、今はシリコンバレーで運営されているNSVウルフキャピタルで、生成AIスタートアップを中心に見ています。
私たちのファンドは、マイクロVCを通じて間接的に1000社以上へアクセスできる仕組みを持っています。
そのうちの約4割がAI関連。毎月20〜30社のスタートアップの投資検討をしているので、これまで見てきたAI企業は1000社を超えます。
プロダクトを作り、会社を経営し、今は投資家として俯瞰する。
そんな立場から見えてきた「アフターAIの世界」で、何が変わるのか。ここでは、私が最前線で感じている“兆し”を共有したいと思います。
企業競争は「何人雇えるか」ではなく、 「どれだけAIを動かせるか」へ
アメリカでは、ソフトウエアエンジニアの失業率が文系学部と同水準にまで上がっています。
つい数年前まで、最も安定した職業の象徴だったのに、です。
私は毎月20〜30社ほどのAIスタートアップと話をしていますが、そのほとんどが「コードの大半はAIが書く」前提で事業を設計しています。
エンジニアに求められているのは、もはや“手を動かす”力ではありません。大事なのは、AIをどう使い、どんな課題を解くのかを構想できる力です。
エンジニアリングの本質が、手作業から設計・編集へと移っている。
一見小さな変化のように見えますが、実際には「仕事」という概念を根本から問い直すような動きです。
この変化は、企業にもはっきり表れています。
私は投資家として毎日、米国上場企業の決算を見ていますが、データが語る変化は明確です。Google(Alphabet)やAmazon、MetaといったGAFAM5社のデータに目を向けると、変化の兆しが鮮明に見えてきます。
シバタさんがChatGPTで作成したGoogleの売上高と従業員推移
売上は毎年2桁成長を続けているのに、2022年を境に従業員数が減少。
これはGoogleに限った話ではなく、Apple、Meta、Amazon、Microsoftも同じです。人を増やさずに成長できる仕組みを手に入れたのです。
なぜそんなことが可能になったのか。
理由はシンプルで、LLMを「つくる側」として自社開発しているだけでなく、AIを「使う側」に回り、あらゆる業務に徹底的に組み込んでいるからです。
実際、GAFAMのR&D費とCAPEX(設備投資)はこの10年で倍増しています。GPUやデータセンター、モデル開発にどんどん資金を投じ、利益率を削ってでもAIを育てています。
Apple、Amazon、Google(Alphabet)、Meta、Microsoft、NVIDIA 、大手6社の設備投資額は売上高の15%に増加(10年前の8%から増加)出典: Trends – Artificial Intelligence, Bond Capital
AI収益化 – Microsoft / Amazon / Alphabet / Meta = 設備投資増加…フリーキャッシュフローマージンは低下 出典: Trends – Artificial Intelligence, Bond Capital
短期的な利益よりも、AIを動かすための資本力に賭けているのです。今の企業競争は、「何人雇えるか」ではなく「どれだけAIを動かせるか」で決まります。
この動きは、SaaS企業にも広がっています。最新の決算発表から読み取れる情報を整理してみます。
ServiceNow、HubSpot、Adobeなどは、営業や開発のプロセスにAIを組み込み、再び成長を加速させました。
HubSpotではAIが営業リードを自動抽出し、わずか1四半期で1万件の商談を設定。Cloudflareでは熟練営業の8割が目標を達成しています。
AIは人の仕事を奪う存在ではありません。人を倍速にするツールなのです。
私はよく「AIはコスト削減の道具ではなく、スピードを上げるための武器だ」と話しています。
AIを使えば、同じ仕事を半分の時間で終わらせることができる。
それができる人とできない人の差は、数年後に決定的になるでしょう。
企業にとっても、個人にとっても、スピードこそが競争力。AI時代の勝ち筋は、まさにそこにあると感じています。
AI時代、日本が秘める“逆転のアドバンテージ”
「日本はAI導入で遅れている」ーー。よく耳にする言葉ですが、私はそうは思っていません。
むしろ日本には、AIの時代にこそ発揮できる強みがある。
そう確信する理由の一つ目は、日本が課題先進国であることです。
少子高齢化、人手不足、地域格差、働き方改革。日本が直面する課題は、これから世界が必ず通る道でもあります。日本はその最前線に立っている。つまり、AIで解決すべき現場が最も多い国なのです。
例えば、医師と患者の会話をAIが聞き取り、診察後に電子カルテを自動生成するAIクリニック。医療従事者の残業を減らし、離職を防いでいます。 こうした動きが次々に出てくるのは、「現場の課題がリアル」だからです。
課題があることは、改善の余地があるということ。
現場起点で考える日本の強みが、ここで活きています。
アフターAIの世界で日本が強いと考える理由の二つ目は、「育成する文化」にあります。
私はよく「LLMは偏差値75の新人社員だと思って接しましょう」と話しています。IQは高く、知識は豊富でも、仕事のやり方は知らない。だからこそ、何を教え、どうフィードバックするかが鍵になります。
日本の企業には、新卒を採用し、研修をして、配属して、育てるという仕組みがあります。
世界的に見ても、珍しい“教育システムを持つ国”です。
これは、AIエージェントを作るうえで大きなアドバンテージです。
というのも、AIを業務に活かすには、「どんな知識を学ばせるか」「どんな判断をフィードバックするか」というプロセスが欠かせません。それはまさに、人を育てる仕組みと同じだからです。
AIを導入してもうまくいかない企業の多くは、「使う」に目が向きすぎていて、「育てる」視点が抜けています。
日本企業が持つ育てるノウハウをAIに応用できれば、業務を理解したAIエージェントを社内にたくさん生み出せるはずです。
課題が多いからこそ、解くテーマも多い。育成文化があるからこそ、AIを活かす土壌がある。日本は、遅れているどころか、AI時代に「必要とされる条件」をすでに備えている国なのです。
AIエージェントを“使う国”だけではなく、“育てる国”へ
AIが社会に広く浸透していく中で、私が強く感じているのは、「AIをどう使うか」よりも「AIをどう育てるか」がこれからの分かれ道になる、ということです。
成果を出している企業は、技術から入らない。
「どんなAIを使うか」ではなく、「どんな問題を解きたいのか」から始めている。
そして、AIがそれを理解できるよう、時間をかけて“教えている”のです。
医療、製造、法務……。どんな現場でも同じです。ChatGPTを入れただけでは成果は出ません。
だからこそ、人間の知恵や経験をAIに伝える力が問われるのです。
私はここに、日本の企業やエンジニアが活躍できる余地があると思っています。
AIが発達するほど、人間の感性や判断が重要になります。生成AIが文章や画像を生み出すことが当たり前になった今、「何をつくるか」「なぜそれをつくるのか」を決めるのは、やはり人間です。
AIがどんどん賢くなる時代だからこそ、人間が“頭”であり続ける必要がある。AIを恐れず、相棒として育てる。
日本が長年培ってきた“現場を理解し、人を育てる文化”をAIにも引き継ぐ。
それができたとき、日本は再び技術立国として世界に存在感を取り戻すはずです。
AIエージェントを“使う国”だけではなく、“育てる国”へ。
その転換こそが、アフターAI時代における日本の最大のチャンスです。
どんなAIを使うかではなく、どんなAIを育てたいか。
その問いに向き合う人たちが、この新しい時代をつくっていくのだと、私は考えてます。
【書籍紹介】 アフターAI 世界の一流には見えている生成AIの未来地図
生成AI時代の「ビジネス実装」が、この一冊で見える 生成AIは、もはやバズワードの時代を越え、実装の巧拙が企業価値を左右する段階へと突入しました。著者のシバタナオキ氏は、投資家としてシリコンバレーを中心に1000社超の生成AIスタートアップを精査し、数十社へ投資してきました。さらに本書には、日本企業の現場で生成AI導入に取り組むトップランナーたちの生の声が収録されています。
文・編集/玉城智子(編集部)
>>>詳しくはこちら
Page 2
転職サイトtypeは株式会社キャリアデザインセンターによって運営されています。
©CAREER DESIGN CENTER CO.,LTD. .ALL RIGHTS RESERVED.

](https://image.trecome.info/uploads/article/image/eacc2a79-b975-4126-9bb7-db51f72bbbca)

