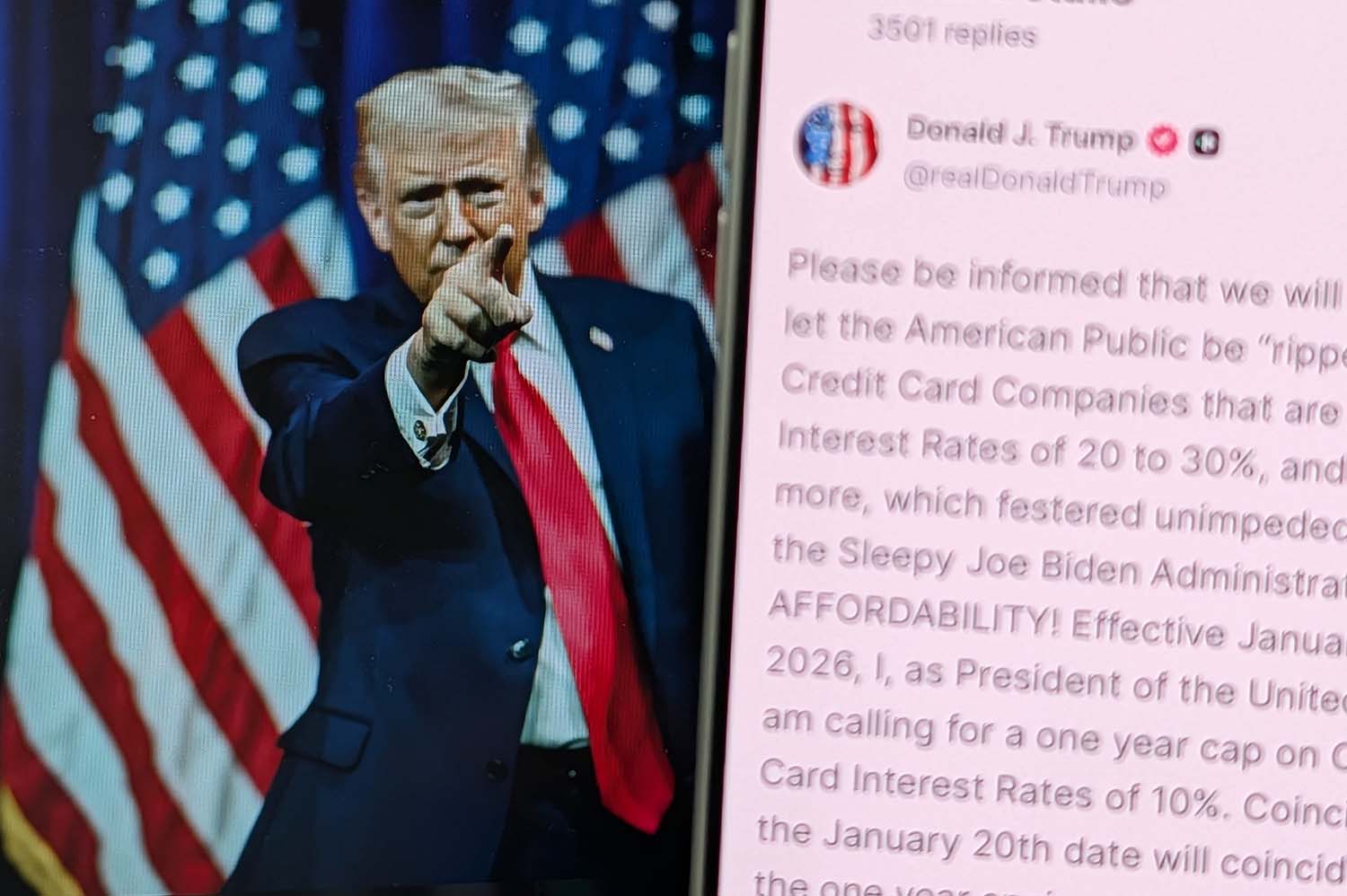【米国市況】国債利回り急伸、S&P500は9日続伸-ドル145円近辺

2日の米金融市場では、国債利回りが急伸。4月の米雇用統計が予想を上回る伸びとなったことに反応した。関税を巡る不透明感は雇用市場にまだ目立った影響を及ぼしていないことが示され、早期の利下げ観測が後退した。
国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率 米30年債利回り 4.79% 6.5 1.38% 米10年債利回り 4.31% 8.9 2.11% 米2年債利回り 3.82% 12.1 3.27% 米東部時間 16時54分米雇用統計では非農業部門雇用者数が17万7000人増となり、ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想を全て上回った。
関連記事:米雇用者数は堅調な伸び、不確実性は採用計画にまだ影響せず (3)
データ発表後、2年債利回りは一時14ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇。市場が織り込む年内の利下げ幅は81bpと、データ発表前の約90bpから縮小した。
市場では向こう数カ月における利下げの見通しも後退。次回の利下げは7月のみが織り込まれている。ゴールドマン・サックスとバークレイズのエコノミストは雇用統計を受け、米利下げ時期の予想を従来の6月から7月に後ずれさせた。
ブラックロックのポートフォリオマネジャー、ジェフリー・ローゼンバーグ氏は「米連邦準備制度理事会(FRB)は失業率の上昇といった何らかの影響が確認されるまで待たざるを得ない」とブルームバーグテレビジョンで発言。「今回の統計にはショックによる打撃は反映されておらず、それがデータに表れるのを見極める必要がある」と述べた。
先物・オプション市場では利下げ観測が後退。年内の金利決定として完全に織り込まれているのは、0.25ポイントの利下げ3回で、今週初めの段階では4回と見込まれていた。一方で、年内の利下げ見送りとなった場合に利益を得る取引が足元で人気を集めており、このポジションには雇用統計の発表を控えて再び買いが入っていた。
今回の雇用統計は、来週開催される米連邦公開市場委員会(FOMC)前に発表される最後の主要な経済指標となる。来週の会合では金利据え置きとの見方が支配的だ。一方、トランプ米大統領は統計発表後に改めて利下げをFRBに要求した。
みずほインターナショナルのストラテジスト、エブリン・ゴメスリヒティ氏は「4月の関税措置による労働市場への大きな影響は、これまでのところ見られていない」と指摘。「FRBは利下げを急ぐ状況にはない。政策不透明感が深まり、二大責務の両方にリスクをもたらす状況ではなおさらだ」と述べた。
株式
米国株は上昇。ウォール街のリスク志向が強まり、S&P500種株価指数は9営業日続伸となった。これは20年ぶりの長期連騰。米中外交の進展の兆しを受けて、4月に広がった関税ショックの傷は癒えつつある。
株式 終値 前営業日比 変化率 S&P500種株価指数 5686.67 82.53 1.47% ダウ工業株30種平均 41317.43 564.47 1.39% ナスダック総合指数 17977.73 266.99 1.51%S&P500種とナスダック100は共に1%を超える上昇。週間ベースでは2週続伸となった。
朝方発表された4月の米雇用統計では、労働市場が減速しつつも底堅さを維持していることが示された。これを受け、トランプ大統領の政策が経済に与える影響に対する懸念が和らいだ。また関税の応酬が続いていた米中の間にも雪解けの兆しが見られている。
カルミニャックの投資委員会メンバー、ケビン・トゼ氏は「政策を巡る不確実性はピークに達した可能性がある」と指摘。「協議は継続中であり、トランプ氏も政策の一部を弱めたように見受けられる。決算シーズンがかなり良好なことを加味すれば、全体的な背景はそれほど悪くない」と述べた。
相場は上昇しているものの、最悪の事態はまだ過ぎ去っていないと警戒する声もある。米国株の今年2月の最高値と4月の安値を予測したテクニカルス分析の第一人者、トム・デマーク氏によると、米国株は再び下落し、数カ月以内には弱気相場に陥る可能性が高い。
関連記事:米国株の弱気相場入りを予想、S&P500の上昇は停滞近い-デマーク氏
またPRSPCTVキャピタルのローレンス・クリアチュラ氏は「『解放の日』とその後の出来事を受け、多くの人は経済のアルマゲドンを予想した。それが起きないというのは良いニュースだ」とした上で、「時期尚早なだけかもしれない。懸念されている多くの現象は、まだデータに反映されていない」と続けた。
クリアチュラ氏は、企業の決算発表が3月末までの四半期を対象としている一方、トランプ氏が関税を発表したのは4月2日であることに言及した。
個別銘柄ではアップルが下落。1日に発表した1-3月(第2四半期)決算では、関税コストの急増や中国での成長鈍化など、主要な課題を巡る投資家の懸念は払拭されなかった。これを受け、ウォール街ではアップル株の投資判断を引き下げる動きが出ている。
関連記事:アップル株が大幅安、投資判断の引き下げ相次ぐ-関税の影響懸念 (1)
アマゾン・ドット・コムも値下がり。同社は、向こう数カ月間に予想される厳しい事業環境に身構えていることを明らかにした。1-3月(第1四半期)決算はまずまずの内容だったが、同社が示した4-6月(第2四半期)の営業利益見通しは市場予想に届かなかった。
関連記事:アマゾン、厳しい事業環境に身構え-利益見通しは市場予想下回る (2)
為替
外国為替市場では、ドルがポンドを除く全ての主要通貨に対して下落。中国が米国との通商協議の可能性を検討しているとの報道を受け、リスク選好が強まった。
為替 直近値 前営業日比 変化率 ブルームバーグ・ドル指数 1224.51 -5.47 -0.44% ドル/円 ¥144.88 -¥0.51 -0.35% ユーロ/ドル $1.1299 $0.0009 0.08% 米東部時間 16時54分クレディ・アグリコルのストラテジスト、バレンティン・マリノフ氏は4月の米雇用統計について、「景気後退への過度な懸念を和らげ、過度にハト派的な米金融政策予想を見直す契機になり得る」と指摘。「ドルは金利面で相対的な優位を持ちながらも大きく過小評価されており、今回の統計を受けてその金利優位がさらに強まれば、ドルは恩恵を受ける」と述べた。
円は対ドルで上昇。ニューヨーク時間の午前には一時1ドル=143円73銭を付けたが、その後は上げを縮めて145円近辺となった。
加藤勝信財務相は2日、日本が保有する米国債について、関税交渉のカードになり得るとの見解をテレビ東京の報道番組で示した。
関連記事:加藤財務相、カードとしてあると思う-関税交渉で日本保有の米国債
原油
ニューヨーク原油先物相場は反落。石油輸出国機構(OPEC)と非加盟産油国で構成する「OPECプラス」が大幅な追加増産を協議していることが明らかになり、売りが優勢になった。
OPECプラスは当初予定を2日前倒しし、3日に開催するビデオ会議で、6月に日量約40万バレルの追加増産を実施する方向で検討しているという。
関連記事:OPECプラス、日量約40万バレルの6月増産を協議-加盟国代表者
すでに中国の需要鈍化や、OPECプラス以外の産油国からの豊富な供給に圧迫されている原油相場は、さらに下落する可能性がある。今回の増産規模は前月の予想外の増産とほぼ同程度とみられ、過剰生産を続ける加盟国へのけん制という側面もある。
TDカウエンのストラテジスト、ダニエル・ガリ、バート・メレク両氏は「OPECプラスの決定はイラクやカザフスタン、ロシアなどの度重なる協定違反が背景にあるようだ」と顧客向けリポートで指摘。今後3四半期で在庫が約2億バレル増加する可能性があり、原油価格は50ドル台前半まで下落するリスクがあると述べた。
原油価格は今年に入り約19%下落し、先月には4年ぶりの安値を付けた。トランプ政権による関税措置でエネルギー需要が減退するとの懸念が背景にある。
価格下落はすでに、トランプ大統領が支援を約束した石油業界を圧迫し始めている。主要なシェールオイル企業の一部は年末までに掘削装置(リグ)を約4%削減する計画だ。シェブロンは2日の決算発表で、自社株買いを縮小する方針を示した。
ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のWTI先物6月限は前日比95セント(1.6%)安の1バレル=58.29ドルで終えた。ロンドンICEの北海ブレント7月限は1.4%安の61.29ドルで終了。
金
金スポット相場は4日続落。米雇用統計が堅調な雇用の伸びを示したほか、米中関係に雪解けの兆しが表れたため、安全資産としての金の魅力が弱まった。週間では今年初めて2週連続での下げとなった。
今週の下落にもかかわらず、年初来ではなお約23%上昇しており、先週には一時オンス当たり3500ドルを超え、過去最高値を記録した。ただ、その後は過熱感が意識され、やや値を下げている。
金スポット価格はニューヨーク時間午後2時27分現在、前日比9.72ドル(0.3%)安の1オンス=3229.48ドル。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物6月限は、21.10ドル(0.7%)高の3243.30ドルで引けた。
原題:US Treasuries Slide as Solid Jobs Market Gives Fed Room on Rates(抜粋)
Stocks Rise for Second Week as Tariff Shock Fades: Markets Wrap
Dollar Drops on China Tariff Talks Report: Inside G-10
Oil Falls as OPEC+ Weighs Another Major Production Increase
Gold Heads for First Back-To-Back Weekly Losses This Year(抜粋)