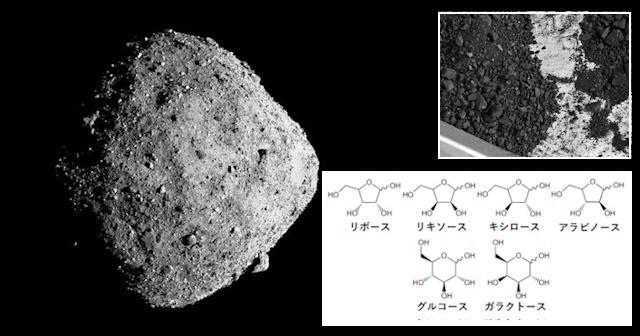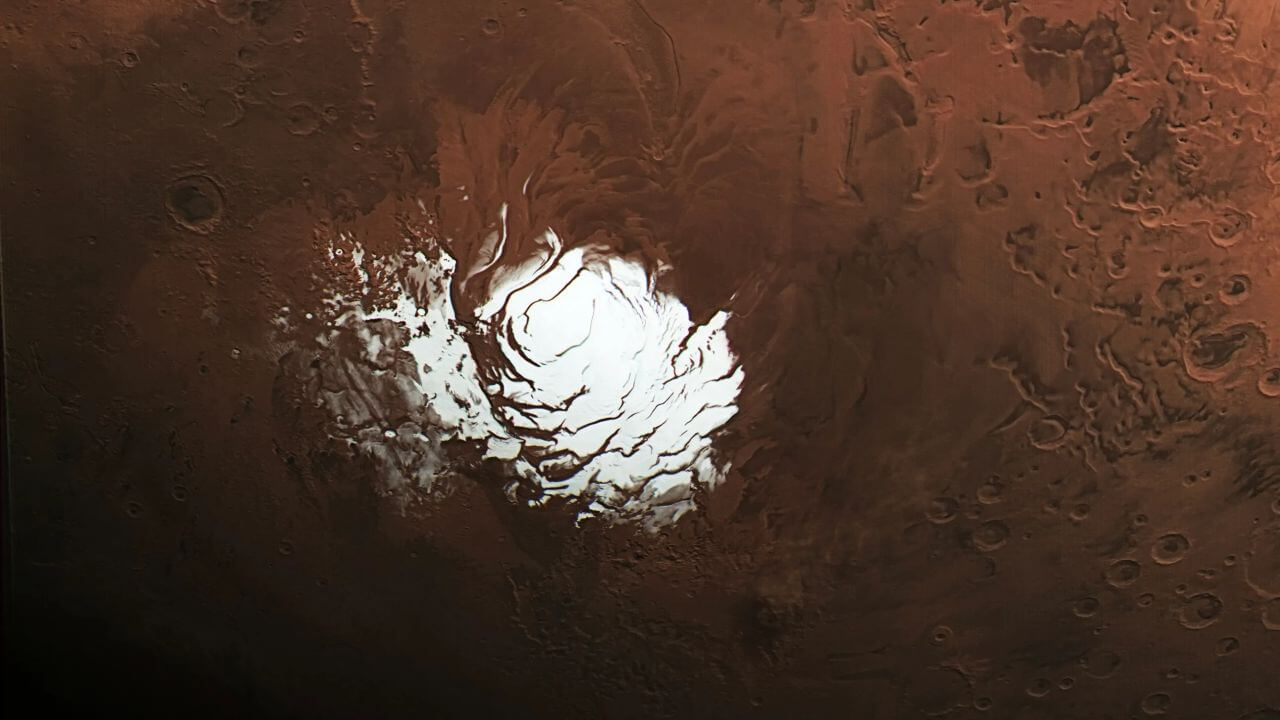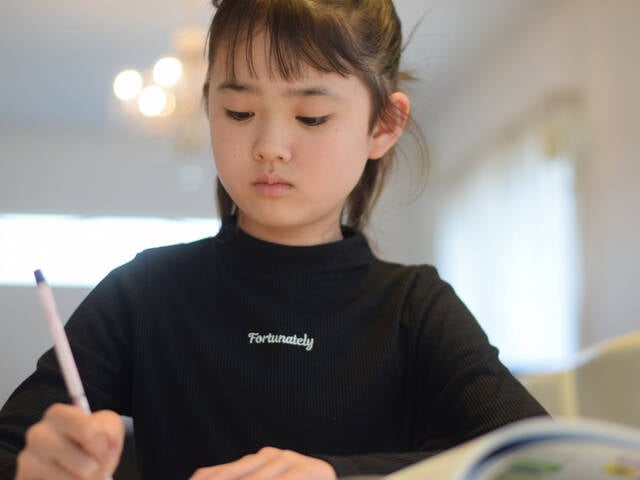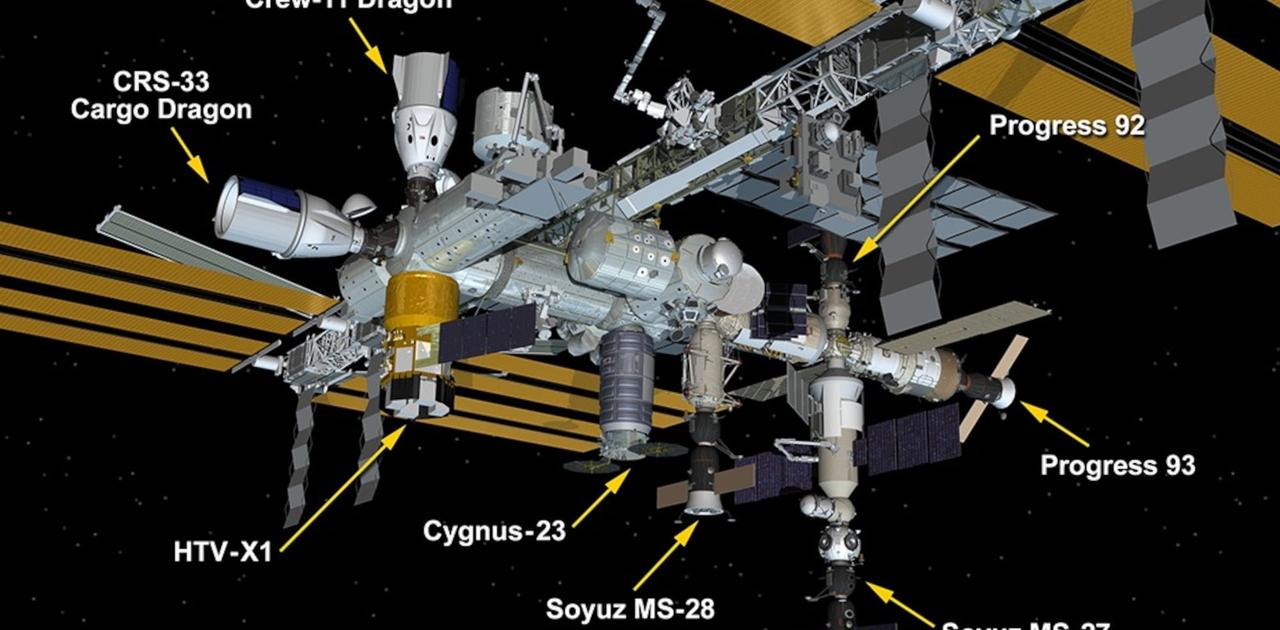未来のエネルギー源に!水素を生成する細菌が海洋生物の消化管で発見される

病原菌として知られるコレラ菌の仲間が、未来の水素社会のエネルギー供給を担うようになるかもしれない。
「マリン・ビブリオ」と呼ばれるビブリオ属の海洋細菌の中には、未来の燃料として期待される水素を作り出すものがいる。
北海道大学をはじめとする研究チームは、貝の仲間である「アメフラシ」の消化管に潜むマリン・ビブリオの遺伝子を分析し、その強力な水素生成パワーの秘密に迫っている。
その結果、20を超える遺伝子群が整然と並んだ美しきクラスターが発見されたそうだ。
今世界は、2050年までに「カーボンニュートラル」を実現するという共通の目標に取り組んでいる。
すなわち、温室効果ガスの排出が世界全体でプラスマイナス・ゼロになるような社会を構築するため、さまざまなエネルギー供給手段が模索されているのだ。
そうした手段の1つが、海の生物資源(マリン・バイオリソース)を活用したバイオ燃料生産技術だ。
たとえば、北海道大学の澤辺智雄教授らは、「マリン・ビブリオ」と呼ばれる海の細菌を利用して水素を生産する方法を開発している。
マリン・ビブリオとは海洋に生息する「ビブリオ属」の細菌のことだ。
この属の仲間には、感染すれば激しい下痢や嘔吐を引き起こす「コレラ菌」や、人食いバクテアと呼ばれる「ビブリオ・バルニフィカス」などがいる。
だが、危険な菌ばかりでなく、うまく利用すれば人間の役に立ってくれそうな仲間もいる。
たとえば、貝の仲間であるアメフラシの消化管に潜む「ビブリオ・トリトニアス」という種は、水素の生成が大得意であることが知られている。
だがなぜ水素を作り出すのか? 澤辺教授らはその謎を解明するために遺伝子に探りを入れている。
昆布粉末を発酵させてギ酸を再導入し、水素を生成するビブリオ菌の培養その結果、「ポーテレシエ」と名付けられたビブリオ菌の仲間は、水素を作り出す能力に特化した美しい遺伝子クラスターを持っていることが明らかになったという。
これらの遺伝子は、発酵を通じて水素を生成するために使われる「FHL複合体」という装置を作るために必要なもので、20種類以上の遺伝子群が一か所にまとまって並んでいる。
さらに水素が作られるプロセスでできる「ギ酸」という物質に注目したところ、これを再回収する量が多いほど、細菌の水素生成能力が高いことも判明した。
研究チームによると、マリン・ビブリオの多くはこうした水素を作り出すための遺伝子を失っているか、その機能が変化しているという。
だが、発酵が起きやすい海洋動物の消化管や海底堆積物などに潜むものは、そこで生成されるギ酸を解毒し、細菌内のpHを保つために、水素を作り出す力を維持してきたと考えられるそうだ。
こうしたマリン・ビブリオは大腸菌の1.5倍の水素生成能力があり、海水内でも効率的に水素を作り出すことができる。この力をうまく利用すれば、水素生成システムのインフラ開発に役立てられるかもしれないとのことだ。
この研究は『Current Microbiology』(2025年3月25日付)に掲載された。
References: Link.springer.com / Global.hokudai.ac.jp / Fish.hokudai.ac.jp
本記事は、海外メディアの記事を参考に、日本の読者に適した形で補足を加えて再編集しています。