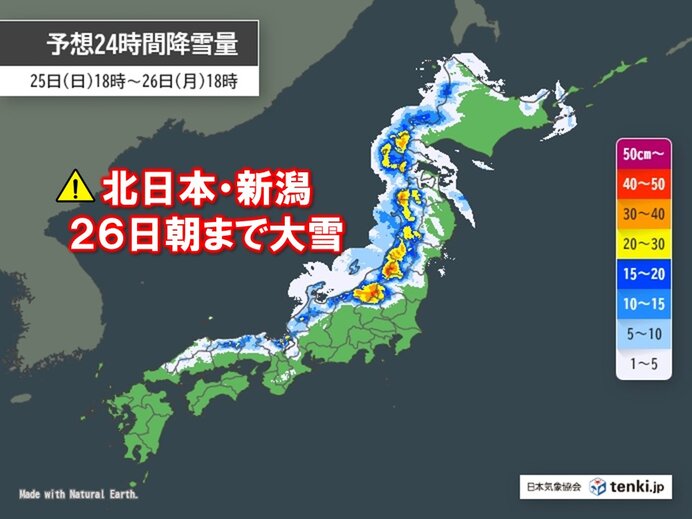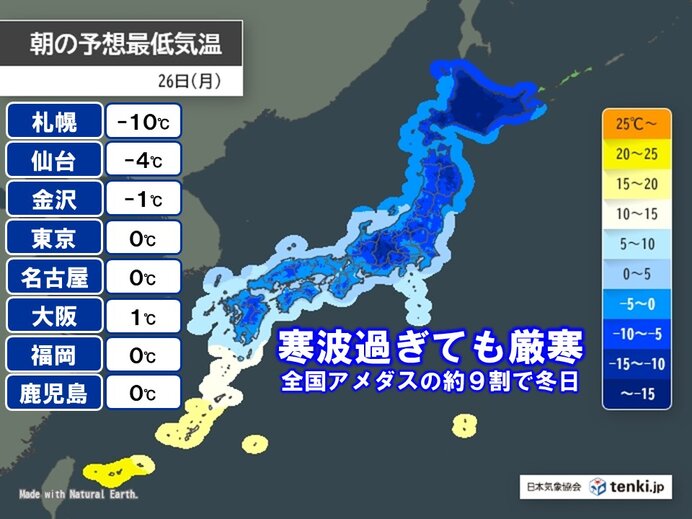コラム:西側諸国は脱米国で連携強化を トランプ政策の混乱生かせ

[デルフィ(ギリシャ) 13日 ロイター BREAKINGVIEWS] - 欧州連合(EU)や日本、英国、カナダなど西側は米国への依存を減らす必要があり、だからと言って中国に依存するようでもいけない。このことはドルからの脱却、貿易と防衛における協力関係の強化、さらにインドなど新興経済国との関係構築が進むことを意味している。
トランプ米大統領が世界の貿易体制を破壊し、同盟国いじめを繰り広げていることから、他の先進国は米国抜きの新たな枠組みを作る必要がある。協力し合えばより強くなれる。カナダのカーニー首相はそうした考えを示唆している。
トランプ氏は米国に対抗するような国際的な枠組みには嫌悪感を示すだろう。既にカナダやEUに対して、自ら混乱している「トランプ関税」に共同で対応しないよう警告を発している。トランプ氏は先週の大規模な通商政策の転換で国際的な立場が弱まったが、それでも手強い存在であることに変わりはない。従って他の西側諸国はトランプ氏をいたずらに刺激しないよう細心の注意を払うのが賢明だ。
<「王座」から退位するドル>
トランプ氏は世界の貿易体制を破壊するだけでなく、外貨準備の58%を占めるドルの信認も揺るがせている。
ミラン大統領経済諮問委員会(CEA)委員長は、ドルは世界の基軸通貨であるため慢性的に過大に評価されていると批判。これを是正する手段として同盟国に対し米国が提供する安全保障の傘の代価として、保有する米短期国債を100年物国債に転換するよう提案している。
これは西側諸国にとって脅威であると同時にチャンスでもある。EUにとって外貨準備の20%を占めるユーロをより強化する機会になるからだ。ユーロの国際的地位が上がればEUはドルが持つ特権の一部を手に入れることができる。そうなればEUの借入コストが下がり、米国による「金融面の脅迫」を弱めることにもなる。
Chart breaking down composition of world's reserve currencies 2016-2024EUは自前の債券の発行を増やすことでユーロの地位を強化できる。債券発行が増えれば市場の流動性が増し、金利が下がる可能性もある。ドイツのようにユーロ圏共同債にアレルギーを持つ加盟国を説得しなければならないが、調達した資金を軍備増強に使えば「二重のうまみ」を得ることができる。EUは自衛できない限り、米国やロシアの圧力にさらされ続ける。
他の西側諸国と連携し、効率的な国境を越えた防衛産業を築くのが理想的だ。こうした形での軍備投資は景気後退を防ぐ効果も期待できる。
<他地域との連携>
EUの経済規模は世界首位の米国に次ぐ。EUは「米国以外の西側諸国」クラブの核となるべきだ。第一歩は英国との新たな関係を築くことだろう。これに続く優先課題は、オーストラリアやカナダ、日本、韓国など、利益と価値観を共有する他の主要な西側経済国との連携になろう。国際通貨基金(IMF)のデータによると、EU域内とこれら主要西側諸国を合わせた経済規模は昨年、世界総生産(GDP)の30%を占め、これは米国(27%)や中国(17%)を上回っている。
この拡大版の西側諸国クラブは次にブラジル、インド、メキシコ、トルコ、ASEAN5カ国などの大規模な新興経済国との関係を築くことができる。これらの国は昨年世界の経済の11%を占めた。
Pie chart of breakdown of Global GDP by country and groups of countries西側諸国と「グローバルサウス」諸国が貿易や投資の障壁を減らせば減らすほどほど、トランプ氏の政策による衝撃を緩和することができる。
もちろん既得権益の反発があるため、貿易障壁を取り除くのは容易ではない。しかし危機こそが政治家に難題に取り組む勇気を与えるものだ。EUはすでにメキシコや南米関税同盟「メルコスル」との貿易協定締結に近づいており、インドやアラブ首長国連邦(UAE)との交渉も視野に入れている。
<二重依存からの脱却>
西側諸国が自らの協力関係を強化し、新興国との連携を進めるほど、中国に依存するリスクは低くなる。実際、オーストラリアはすでに「米国に対抗するために手を組もう」という中国の申し出を断った。日本、韓国、インド、ASEAN諸国の多くも中国の影響力を脅威に感じている。欧州もまた間接的にリスクに晒されている。中国はウクライナに侵攻したロシアの最大の支援国だからだ。
中国は高率のトランプ関税の影響で新たな輸出市場を探しているが、各国は自国の産業を守るため反ダンピング関税を課すことで自国の産業を守ることができる。しかし、選択を慎重にするのが賢明だろう。例えば、中国が米国への輸出を大幅に制限した希土類(レアアース)を今のうちに大量購入するのは理にかなっている。欧州や日本は、中国製太陽光パネルを大量に購入して再生可能エネルギーの導入を加速させることで、米国産天然ガスへの依存を減らすことができるだろう。
先進国はトランプ氏が「でっちあげ」と主張する気候変動のような問題では中国と協力する余地があるかもしれない。しかし多くの分野では中国と距離を置くべきだ。脱米国と脱中国を同時に行うには時間とコストがかかるが、それを怠れば将来、後悔することになるだろう。
(筆者は「Reuters Breakingviews」のコラムニストです。本コラムは筆者の個人的見解に基づいて書かれています)
私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」, opens new tab
筆者は「Reuters Breakingviews」のコラムニストです。本コラムは筆者の個人的見解に基づいて書かれています。
Hugo Dixon is Commentator-at-Large for Reuters. He was the founding chair and editor-in-chief of Breakingviews. Before he set up Breakingviews, he was editor of the Financial Times’ Lex Column. After Thomson Reuters acquired Breakingviews, Hugo founded InFacts, a journalistic enterprise making the fact-based case against Brexit. He then helped persuade the G7 to adopt a plan to help the Global South accelerate its transition to net zero. He is an avid philosopher.