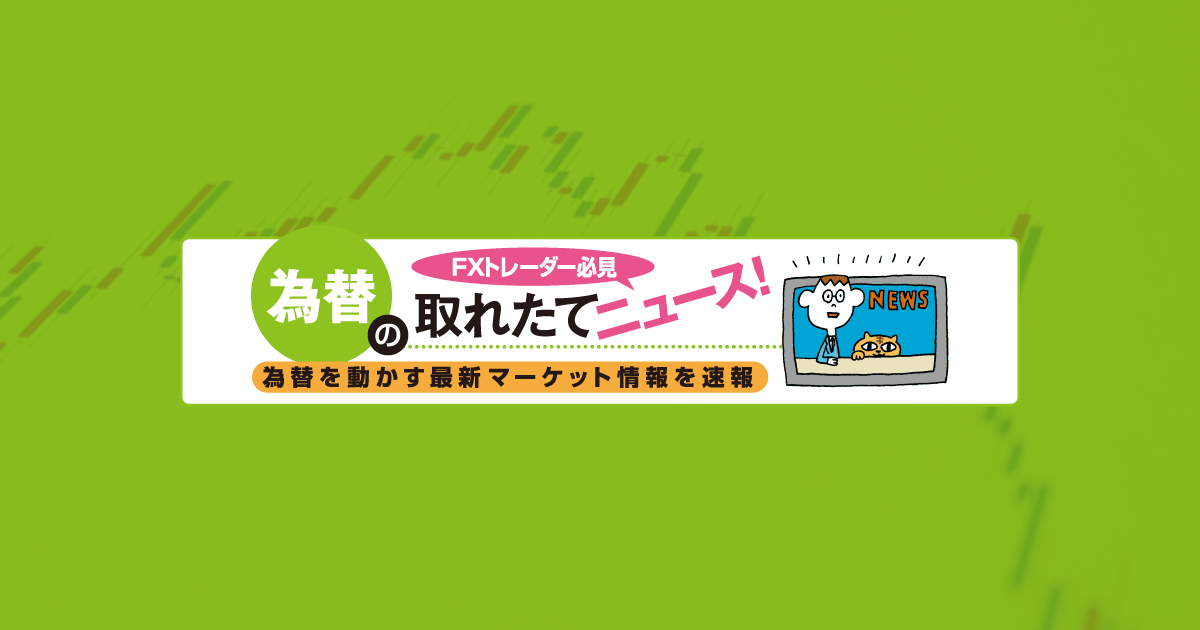失速するAI主導の米国株高、ドットコムバブル破裂の歴史をほうふつ

革命的な新技術が登場し、無限とも思える可能性に投資家たちが夢中になる。そんな陶酔感が株式相場のラリーに拍車をかける。やがて相場は過熱し、株価がとんでもない水準にまで高騰する。そして、全てが崩壊する。
聞き覚えがあるのではないか。
それが起きたのは、今からちょうど25年前だ。約5年間続いたインターネット株バブルがはじけ、何兆ドルもの投資損失を残した。S&P500種株価指数が2000年3月24日に付けた最高値水準に再び戻ったのは07年になってからだった。S&P500種の高値更新から3日後にハイテク株の比重が高いナスダック100指数も最高値を付けた。だが、その後15年余りにわたり高値更新はなかった。
1995年8月に上場したネットスケープ・コミュニケーションズの新規株式公開(IPO)の大成功から始まった熱狂的な上昇相場は、2000年をピークに幕切れを迎えた。S&P500種は00年3月の最高値までにほぼ3倍に、ナスダック100指数は718%も上昇した。その後、02年10月までに、ナスダックの時価総額は80%余り失われ、S&P500種はほぼ半値となった。
その時代の反響が今、聞こえる。今回のブームを引き起こした新技術は人工知能(AI)で、S&P500種は22年10月の底値から先月のピークまで72%も上昇し、その過程で株式時価総額は22兆ドル(約3300兆円)余り増えた。だが、問題の前兆が見え始めている。ナスダック100指数は10%余り下落し調整局面入りとなった。S&P500種も一時的に調整局面に入った。 こうしたシンメトリーが四半世紀前の恐ろしい記憶を呼び起こしている。
ベンチャー・キャピタリストでインターネットブーム期の立役者であり、現在のブームでもそうした役割を担っているコースラ・ベンチャーズの共同創業者ビノッド・コースラ氏は「投資家には二つの感情がある。恐怖と強欲だ」と述べ、「われわれは恐怖から強欲へと移行したのだと思う。強欲になると、見境のない評価を行うことになる」と話す。
規模の違い
ドットコムバブル期とAI時代の主な違いは、その規模だ。最近のブームは目を見張るものがあるが、ネット株バブルの極端さには及ばない。
「インターネットは非常に大きなアイデアで社会やビジネス、世界に大きな変革をもたらした。そのため、安全策を取る人は総じて取り残されてしまった」とAOLの元会長兼最高経営責任者(CEO)のスティーブ・ケース氏は指摘。「その結果、取り残されないよう大規模投資に重点を置くことになるが、一部は成功するものの多くは失敗する」と付け加えた。
ケース氏はAOLの株価が高騰していたバブルの絶頂期である00年1月にタイム・ワーナーを買収し、ドットコムブームの象徴となった人物だ。このため、うまくいかないテクノロジー投資を多少なりとも理解している。
この買収は理論的には理にかなっても、現実にはそうではなく、それはケース氏自身も認めている。両社統合で誕生したAOLタイム・ワーナーの株価は収益悪化で下落。09年にAOLはタイムワーナーから分離された。
ウォール街が今、懸念しているのはこういう事態だ。
ノーベル経済学賞受賞者でマサチューセッツ工科大学(MIT)教授のダロン・アセモグル氏は、「インターネットから収益を得るためのビジネスモデルが確立されるよりもずっと前から、インターネットには多くの過剰な前宣伝がなされていた」と指摘。「それがインターネットブームとネット株バブルを生み出した理由だ」と述べた。
一方で、AIブームに関わる企業は、ドットコム時代を席巻した企業とは大きく異なる。ネット株バブルを形成したのは利益の出てない新興企業が中心で、熱狂に便乗しようと株式公開するために社名に「.com」を付ける企業もあった。一方、AIを巡る熱狂はアルファベットやアマゾン・ドット・コム、アップル、メタ・プラットフォームズ、マイクロソフト、エヌビディアといった世界で最も収益性が高く、財務的に安定したテクノロジー企業の一握りのグループが中心だ。
バーンレート
フィッシャー・インベストメンツのケン・フィッシャー会長はネット株ブーム期を振り返り、「時価総額トップ200社中、膨大な数の企業がマイナスのバーンレート(資金の回転率)を示していた」と指摘。「バブルをバブルたらしめているのは、マイナスのバーンレートだ。2000年当時、企業はインターネットのおかげで『今回は違う』という考え方があった」と述べた。
熱狂をあおる企業にこうした違いがあるため、株価収益率(PER)のような従来の指標では、二つの時期のバリュエーション(株式評価)を比較することは難しい。1999年にネット株ブームの企業の大部分が採用されていたナスダック総合指数のPERは当時の予想ベースで約90倍だったが、現在は約35倍だ。
しかし、実際には、最も注目されていた企業の多くが利益を上げていなかったため、ネット株バブル期にはPERで評価する考え方自体が時代遅れのように思われた。そのため、ウォール街では「マウスクリック」や「ウェブページの訪問者数」といった新しい評価基準まで考案された。
今となれば常軌を逸していると思えるかもしれないが、当時多くの投資家は気にも留めていなかった。インターネットの成長見通しに織り込まれた無限の未来に賭けていたし、株価がさらに上昇し続けたからだ。
やがて、さまざまな要因が重なりネット株バブルは崩壊した。連邦準備制度は株式市場の過熱を抑制する目的もあり、利上げを開始。日本は不況に陥り、世界的な景気減速への懸念が高まった。株式相場が過去最高値を更新する中、投資家は突然、利益を生みだしていない企業の株式に対して懐疑的になった。
今の投資家にとってのリスクは、同じシナリオが繰り返される可能性だ。AIは生活のあらゆる側面でコンピューター化されたパーソナルアシスタントが関与する夢を喚起する。交通手段を管理し、子供の教育を助け、日常的な医療ケアを提供し、娯楽を生み出し、毎日の家事や雑用を管理する。
それらの全てが現実のものとなる可能性はある。だが、テクノロジー株主導のバブルに関しては、真の勝者がすぐに明らかになることはほとんどない。AIの最大の恩恵を受ける者はまだ存在していないかもしれないという考えは、ペッツ・ドット・コムの元CEO、ジュリー・ウェインライト氏が最近よく考えるドットコム時代の教訓だ。
「全てのイノベーションは、非常に小さな企業から生み出されてきた。今でもそれは続いているかもない」と語った。
そうしたリスクは中国のAIスタートアップ、DeepSeek(ディープシーク)の高度なチャットボットが数カ月前に登場して顕在化した。より安価なAIモデルが製品需要を圧迫するとの懸念から、エヌビディアの時価総額は5890億ドルも急減。AI分野での優位性が確実なものには程遠いことを思い知らされる出来事となった。
原題:Stumbling Stock Market Raises Specter of Dot-Com Era Reckoning(抜粋)