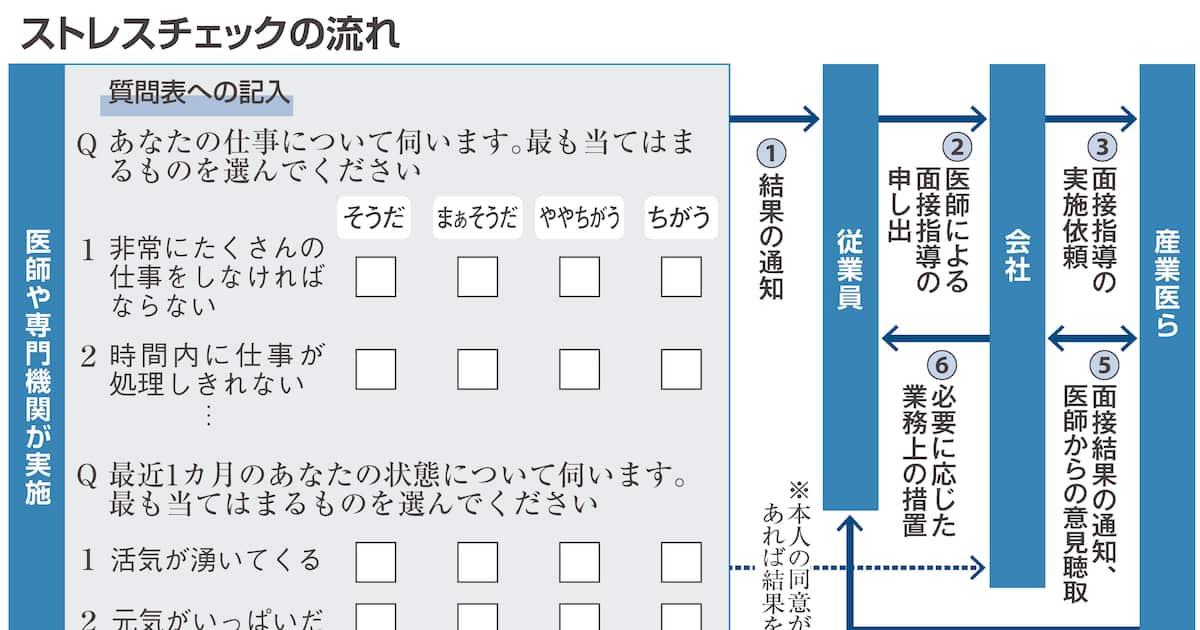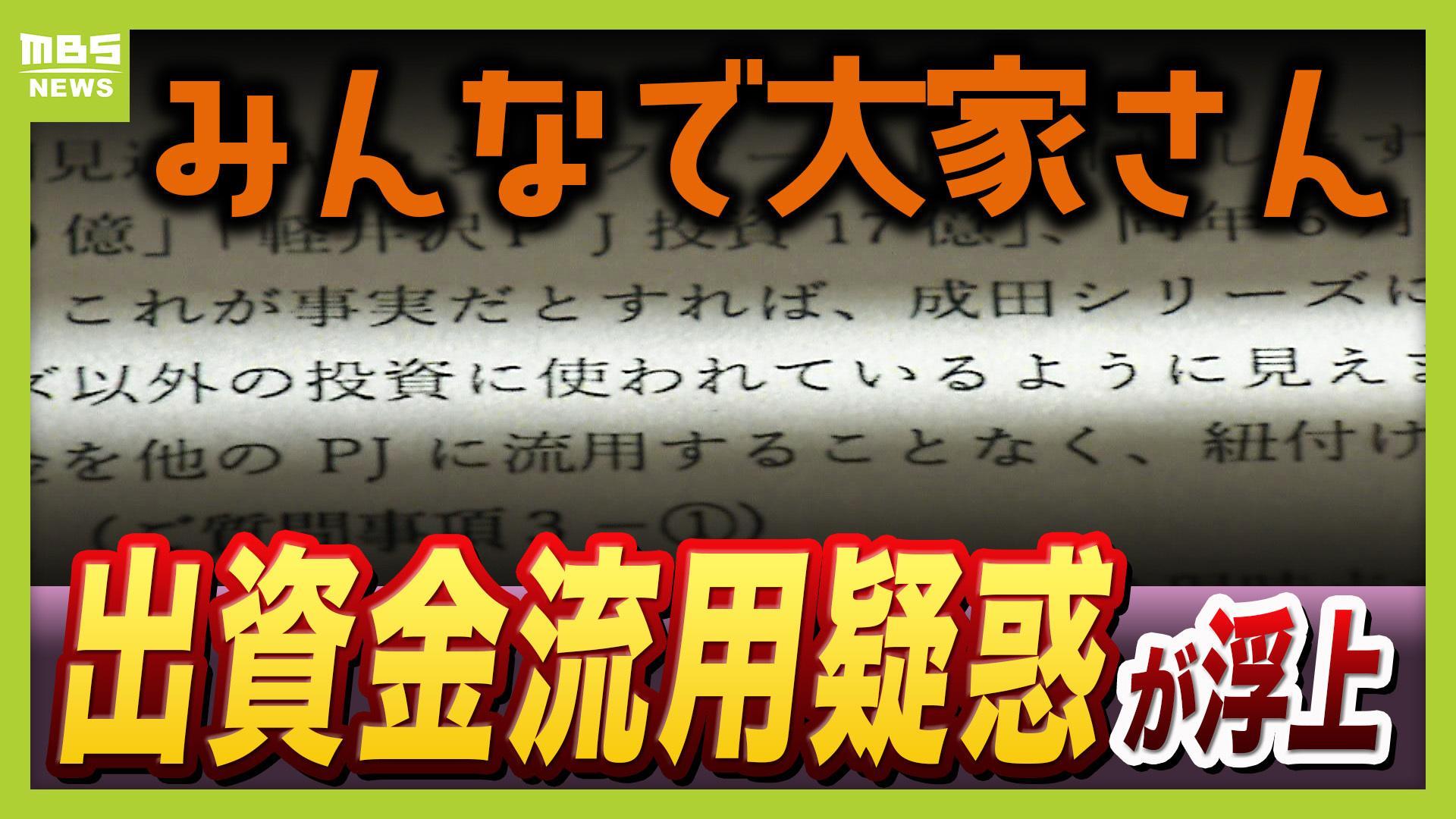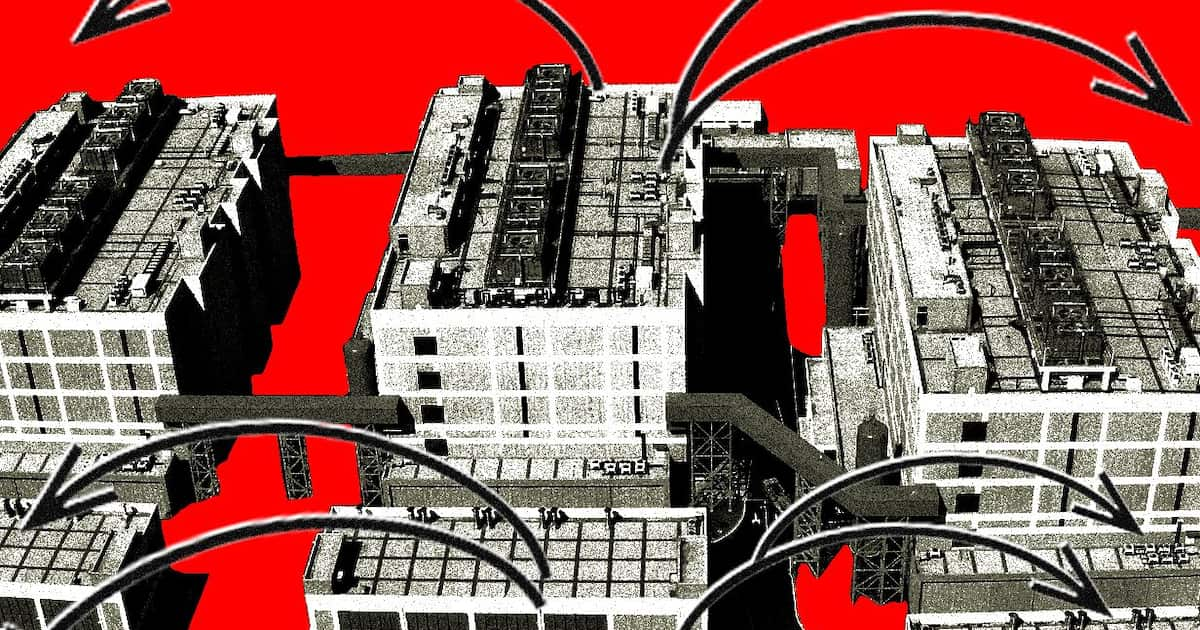パナソニックの"漕がないママチャリ"に乗ってきた

パナソニックは、特定小型原動機付自転車「MU(エムユー)」を12月に発売します。特定小型原動機付自転車(特定原付)は2023年7月に法整備が行なわれてから約2年が経過しましたが、パナソニックが満を持して発表した同社初の特定原付です。さっそく試乗する機会が得られましたのでレポートします。
「MU」は、一見して既存の"ママチャリ"風ですが、実はあえてこうしたフォルムを採用しています。U字型のフレームは乗り降りがしやすく、停車時の足つき性がよいということで、安全に乗車できるよう配慮されています。自転車もそうですが、停車時には足を地面に付けて停車する必要があります。これを誰でも無理なくできるように、ということでこのフォルムを採用したそうです。
タイヤは20インチサイズを採用。もっと小さなタイヤを装着した自転車は沢山ありますが、このくらいのサイズになると、街中の段差も安定して走行が可能になります。
自転車風なのは見た目だけではなく、採用されている各パーツも既存の自転車と互換性があるものが使われています。このためメンテナンスが容易です。バッテリーも同社の電動アシスト自転車と全く同じものが採用されており、流用が可能です。もちろん、充電器も同じ物を使用できます。
これまで特定原付の車両は、一部の量販店など取り扱いが限られていましたが、「MU」に関してはパナソニックの販路を活用し、一般的な自転車店で広く取り扱われる予定です。パーツ類も自転車に準ずるものが採用されているため、こうした対応が可能になっています。
ただし、納車までの流れは一般的な自転車とは大きく異なります。まず、購入にはマイナンバーカードなど身分証明書が必須で、その上で、「安全利用ガイド」という動画を自宅で視聴し、テストを受ける必要があります。テストに合格したらスクリーンショットを保存して販売店に提示します。
さらに、特定原付に必須なナンバープレートの取得は、ユーザー自らが市町村の役所に行って取得します。合わせて保険代理店やコンビニなどで自賠責保険への加入も行ない、ナンバープレートに加入を証明するステッカーを貼ります。最後にこれらの項目を販売店でチェックして、晴れて納車となります。
これらの手続は最低限必要なもので、実際にはさらに、自賠責保険では対応できない事故に遭った場合に備え、自動車と同様に任意保険への加入も強く推奨されています。また、ヘルメット着用は努力義務で任意となりますが、こちらも着用が強く推奨されます。車道上で発生するリスクを考えれば、任意保険もヘルメットも筆者個人としては必須だと考えています。
特定原付は自走する乗物ですので、乗車するまでの手順も電動アシスト自転車とは異なります。まず、電動アシスト自転車と違い、シートに座る前に電源はオンにしません。先に電源をオンにしてしまうと、誤ってスロットルに触れ、暴走してしまう危険性があります。まずはスタンドを起こし、シートにしっかり座ってから電源をオンにします。また、降りる際には電源をオフにしてから降ります。
筆者が着座して電源をオンにすると、車両は「歩道走行モード」になっていました。歩道走行モードは自転車の走行が許可されている歩道を走行するためのモードで、最高時速は6kmに制限されています。まずはこの速度で走行してみました。
最高時速6kmとなると、人間の早歩きぐらいの速度でしょうか。正直なところ足を着かずに安定して走るのは難しく感じました。軽く足を着きながらゆっくり進む感じになります。ただ、特定原付は漕ぐ必要がありませんので、車体が左右に揺れにくいです。自転車で時速6kmで走るよりは安定しているのではないかと思います。
次に、車道走行時のための「車道走行モード」を試しました。切り替えは一旦完全に停車する必要があります。とはいえ、シートから下りる必要はなく、モード切替スイッチで切り替えるだけです。車道を車道モードで走行して、そのまま走りながら歩道に入ることはできず、歩道の手前で一旦停止して歩道モードにするという乗り方になります。車道モードのまま歩道に進入してしまうと、その時点で違反になります。
車道モードは最高時速20kmです。スタート時からフルスロットルにしてみましたが、なかなかの加速力があります。時速20kmとなると、一般的な電動アシスト自転車(平均時速10~15km程度)よりは速く、ロードバイクなどよりは少し遅い(個人差はありますが)くらいの感覚です。とはいえ、体感ではかなりの速度にも感じます。なにより一定の速度で走り続けることができるのが自転車とは大きく異なるところです。
また、タイヤが大きめなのもメリットに感じました。タイヤサイズが10インチ程度の特定原付では、ハンドルが左右に取られ、不安定に感じることが多いのですが、タイヤサイズが20インチとなると、大きな違和感は覚えませんでした。普通の自転車の感覚で安心して乗れるという印象です。
特定原付ではディスクブレーキを採用する車両が多い傾向にありますが、「MU」では前輪はリムブレーキ、後輪はハブブレーキという構成で、一般的なママチャリの電動アシストに採用されているものと同じです。試乗前は制動力は足りるのかと不安があったのですが、実際に乗ってみると杞憂で、全く問題は感じませんでした。冷静に考えれば、最高時速は時速20kmで、重量も24kgと、一般的な電動アシスト自転車と大きく変わらないわけですから当然かもしれません。
ディスクブレーキは雨の日でも制動力が落ちにくいなどメリットもありますが、メンテナンス性においてはリムブレーキのほうが優位ではありますので、これはこれでアリな選択肢ではないかと思います。広く一般に向けた製品ならなおさらでしょう。
特定原付は16歳以上であれば運転免許がいらない乗物です。しかし、実際に車道を走行するにはさまざまな交通ルールを理解している必要があります。2026年4月からは自転車に青切符が導入され、取締が厳しくなりますが、特定原付に関してはそもそも始めから青切符の対象です。交通ルールは「知らなかった」ではすみません。パナソニックでは、元々自転車の事故を防止するため、警察などと協力しながら安全の啓蒙活動を実施しています。今後は特定原付についても啓蒙活動に組み込んでいき、広く周知を図る方針です。
特定原付が登場したことで、たとえば片道10kmの距離を自転車で学校に通っていたような学生でも、通学がとても楽になるというメリットがある反面、交通ルールを知らないままではリスクが増えてしまいます。特定原付に乗る場合は、年齢にかかわらず交通ルールを積極的に理解するようにして乗っていきたいものです。
今回、自転車メーカーとしても大手のパナソニックが初めて特定原付市場に参入しましたが、同社にはさまざまなバリエーションの自転車がラインナップされています。今後、折り畳みやMTB風のものなどの展開にも期待しつつ、他社の参入も楽しみなところです。