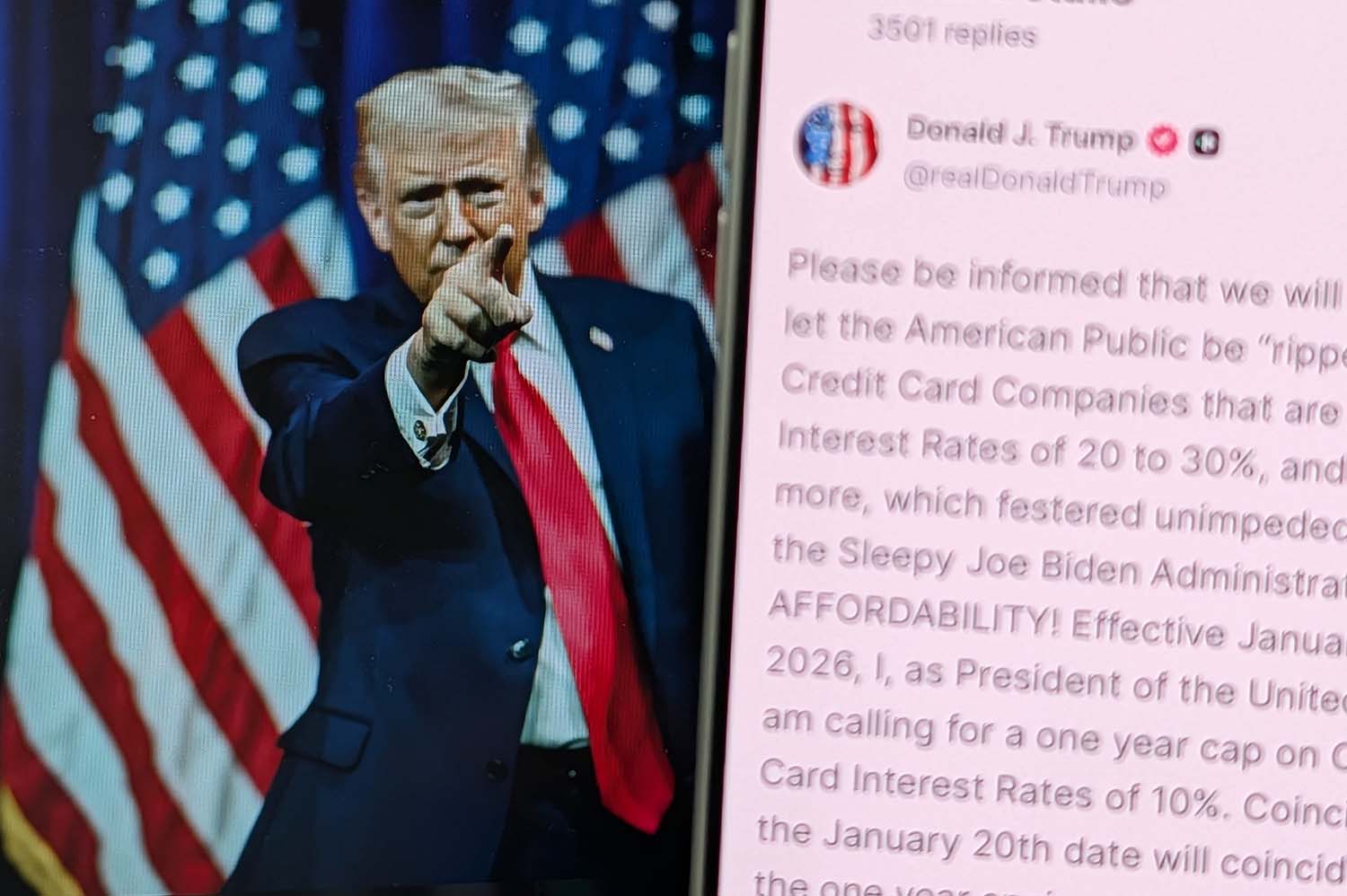トランプ関税で大幅円安へ、18年の人民元が示唆-元日銀調査統計局長

元日本銀行の調査統計局長で一橋大学国際・公共政策大学院の関根敏隆教授は、トランプ米大統領の関税政策により高い確率で起こるシナリオは為替のドル高で、円相場の下落はかなり大きくなる可能性があるとみている。根拠となるのは7年前の中国人民元の動きだ。
関根氏は4日のインタビューで、今回の米国の関税政策は第1次トランプ政権で実施された規模をはるかに上回り、為替がショックを吸収し始めると、円相場に「かなり大幅な調整が起こる可能性もある」と述べた。
トランプ大統領は2018-19年に中国のみに追加関税を課し、この間人民元は対ドルで最大15%下落した。第2次政権では日本を含む全ての対米輸出国に基本税率10%や一部の国に上乗せ税率を適用し、世界景気の減速を警戒するリスク回避の動きが拡大。円は今月に入り対ドルで一時3%超上昇したが、当時の人民元の動きに照らせば、足元の相場はいずれ修正を迫られることになる。
関連記事:日本に24%相互関税、米政権が9日適用-「極めて残念」と石破首相
関根氏によると、今回の関税引き上げが世界経済に及ぼす影響は1970年代初頭の「ニクソンショックに匹敵する」という。米国の一方的な通告でドルが切り下げられ、日銀は円高に対応するため金融緩和を維持した結果、石油ショックへの対応が遅れ、日本の消費者物価(CPI)は25%も上昇した。「日銀にとって2度と繰り返したくない失敗だ」と関根氏は話す。
米連邦準備制度理事会(FRB)も、関税引き上げがもたらすスタグフレーション(物価上昇と景気悪化の同時進行)のリスクに立ち向かわなければならない。関根氏は、パウエル議長の脳裏には「コロナ後の回復過程で物価上昇は一時的と判断し、金融緩和を維持したことで期待インフレが上昇し、物価が上振れた失敗」がよぎっていると推察する。米CPIは2022年6月に9%上昇した。
トランプ関税の影響を見極めるには時間がかかり、日銀が政策変更を当面見送るのはやむを得ないが、いつまでも時間をかけるわけにもいかず、「やはり金利を引き上げ、期待インフレ率が上がるのを食い止めることを考えなければならないだろう」と関根氏は予測する。
みずほリサーチ&テクノロジーズの分析では、今回の関税政策は米国の国内総生産(GDP)を1.3%ポイント押し下げ、個人消費支出(PCE)のエネルギーと食品を除くコアデフレーターを1.6%ポイント押し上げる見通しだ。市場の金融政策見通しを映すオーバーナイト・インデックス・スワップ(OIS)は、年内4回前後の米利下げを織り込む一方、日銀の年内利上げ確率は2割程度に低下している。
フーバー政権の教訓
米国が貿易相手国に高率関税を課し、自らスタグフレーションに陥った失政例としてフーバー大統領によるスムート・ホーリー法がある。金本位制に縛られ、金融政策を十分緩和しなかったことが世界恐慌の拡大を招いたため、「トランプ大統領が同じことをしたのだとすると、金融緩和という選択肢もあり得る」と関根氏は言う。
金融引き締めを取るか、緩和を取るかは物価上昇と景気後退の「どちらのインパクトが大きいか次第だ」と関根氏は指摘。今回の米関税ショックの帰結が「本当に世界的な景気後退だとすると、むしろ為替は円が強くなり、ドルが安くなる」との認識も示した。