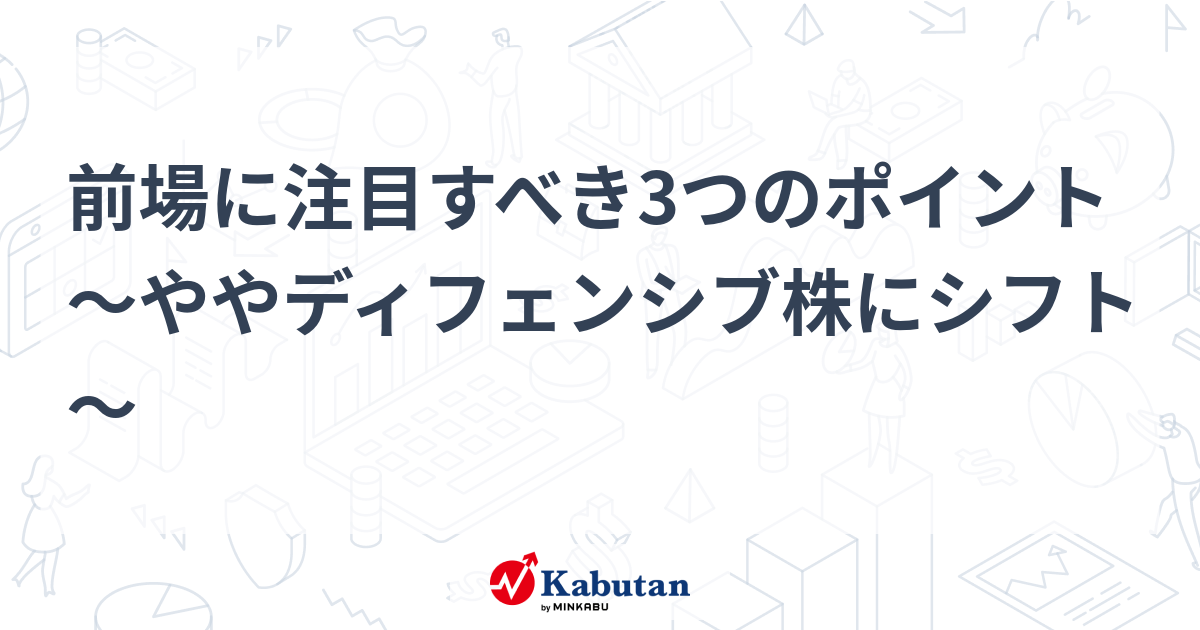名目賃金は4カ月ぶり高い伸び、好調な春闘反映-日銀正常化の支え

6月の名目賃金は4カ月ぶりの高い伸びとなった。春闘の好調な結果が給与に反映される中、基本給に相当する所定内給与が増加した。日本銀行の見方に沿った内容で、金融政策正常化の支えとなる。
厚生労働省が6日発表した毎月勤労統計調査(速報)によると、名目賃金に相当する1人当たりの現金給与総額は前年同月比2.5%増加。42カ月連続のプラスだった。所定内給与は2.1%増と改善傾向が続いたほか、夏季賞与など特別給与が全体を押し上げた。物価変動を反映させた実質賃金は4カ月ぶりにマイナス幅が縮小した。
日銀は、経済・物価が見通し通り推移すれば利上げを継続する方針を維持している。今春闘では平均賃上げ率が2年連続で5%を上回り、賃上げのモメンタム(勢い)持続が確認された。今後は賃金上昇の持続性とともに、実質賃金のプラス転換が焦点となる。
丸紅経済研究所の浦野愛理主任研究員は、6月時点まで「日銀の想定通りに堅調に賃上げの動きも広がってきている」と評価。春闘の結果も良好で、それが実際の統計にも徐々に表れ始めており、利上げの後押し材料になってもおかしくないとの見方を示した。
日銀は現状維持を決めた7月の金融政策決定会合で、消費者物価の見通しを上方修正した。植田和男総裁は会見で、賃金と物価が相互に参照しながら緩やかに上昇していくメカニズムは維持されていると指摘。実質賃金は年後半にいくにつれて「良い動きが出てくる」との見方を示した。
ブルームバーグが7月会合直後の1日に実施したエコノミスト調査によると、次回利上げは10月が最多で、調査対象45人のうち42%が予想。来年1月が33%で続いた。年内利上げ予想は53%と前回調査(42%)から拡大した。
関連記事:日銀の次回利上げは10月が最多4割超、予想の前倒し進む-サーベイ
実質賃金は6カ月連続で前年を下回ったものの、マイナス幅は前月から大幅に縮小した。「持ち家の帰属家賃を除く」消費者物価指数で算出した実質賃金は前年同月比1.3%減。3月分から公表を開始した、持ち家の家賃換算分を含めた総合指数に基づく実質賃金は0.7%減だった。
連合が発表した今春闘の最終回答集計によれば、平均賃上げ率は5.25%で、目標の「5%以上」を達成した。毎月の基本給を引き上げるベースアップ(ベア)は3.70%と、3%以上としていた目標をクリアした。
春闘の結果や物価高などを背景に賃金底上げの動きが続いている。厚生労働相の諮問機関である中央最低賃金審議会は4日、2025年度の最低賃金を全国平均で過去最大の63円引き上げ、1118円とする目安を答申した。目安通りに改定されれば初めて全都道府県で時給1000円を超える。
米関税リスク
今後の賃金動向を巡っては、米国の関税措置による企業収益への影響が引き続き警戒される。日米両政府は、日本からの輸入品に一律で課す関税率を15%とすることで合意したが、現状25%の追加関税がかかっている自動車の税率引き下げの時期は明確になっていない。
SMBC日興証券の関口直人エコノミストは、今のところ企業収益自体が大幅減速する状況ではなく、賃金が大きく減速することはないと分析した。ただ、来年の春闘で今年の賃上げ率維持は難しくなると指摘。4-6月の所定内給与の伸びは2%程度だが、来年4月以降は「1%半ばぐらいまでいく可能性はある」と述べた。
日銀の植田総裁は、日米合意は「日本経済を巡る不確実性の低下につながる」と評価した。一方、関税の影響で特に製造業の収益が下方に屈折し、賃金への影響が懸念されると指摘。その上で、「どの程度の大きさ、強さになるのかを丁寧に見ていきたい」と述べた。
他のポイント
- 一般労働者(パートタイム労働者以外)の所定内給与は2.5%増-前月2.2%増
- 特別に支払われた給与は3.0%増-前月6.6%減
- エコノミストが賃金の基調を把握する上で注目するサンプル替えの影響を受けにくい共通事業所ベースでは、名目賃金は3.0%増と6カ月ぶりの高い伸び
- 6月の消費者物価指数は「持ち家の帰属家賃を除く」が3.8%上昇、総合指数は3.3%上昇だった