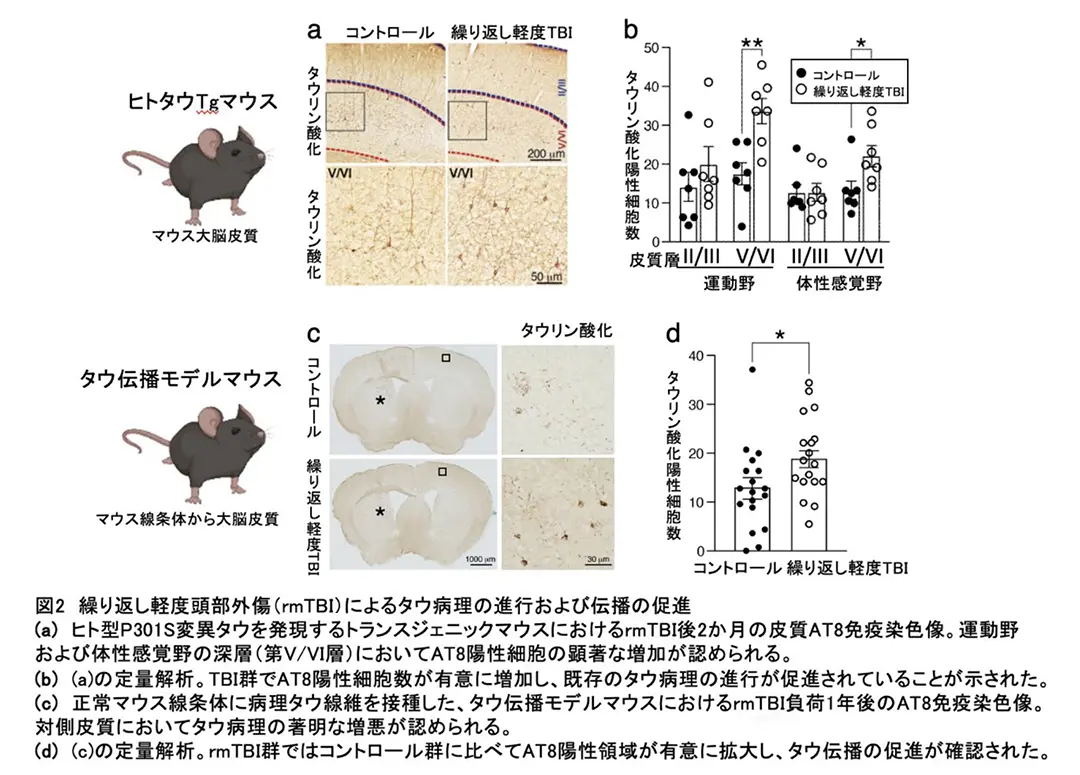脳卒中後遺症で右半身がまひ リハビリ室で待っていた「助けすぎない」トヨタのロボット

「クララが立った」-。昭和49年初回放送の名作アニメ「アルプスの少女ハイジ」には、車いすの少女「クララ」が立ち上がる場面がある。入院中のぼくは幼いころに見たテレビ番組を思い出しながら「どうやったら再び歩けるようになるのか」と考えていた。
46歳で脳出血になり、後遺症で右半身まひの症状があったため、令和2年1月下旬から山あいの回復期病院でリハビリの日々を送っていた。
車いすの生活だったが、前年末の発症から時間が経過し、少しずつ右足が動くようになっていた。クララの病気は脳出血ではなかったが「きっかけがあれば、クララのように立てるようになる」とどこか楽観していた。だが、現実は甘くなかった。
当時は右足全体に長下肢装具を着け、理学療法士さんに介助してもらい、ようやく歩ける状態。歩いているというより、介助によっておもちゃの兵隊さんのように動かしてもらっているという雰囲気だった。
なにしろ、身体のバランスがうまくとれない。自分の感覚は以前の身体イメージのままだが、実際の身体はまひしているので、その状況を正確にとらえられていなかったのだろう。骨折などの回復プロセスと明らかに様子が違った。
自由がきかなくなった右手や右足は、新しいパーツと交換したような気分だった。新しいパーツを身体になじませるような感覚でリハビリを続けていた。
お見舞いにきてくれたみなさんからは「今まで忙しくしていたのだから、ゆっくりしなよ」と声をかけていただいていた。だが、そんな状態だったから、なかなか、ゆったりとした気分にはなれなかった。
脳卒中のリハビリは比較的回復しやすい最初の半年が大事だと聞いていた。漫然と過ごした場合と、効果的なリハビリをした場合の2つの未来の間には大きな差があるはず。「ここで過ごし方を間違えたらまずい」という思いはあったが、何をすれば効果的かは分からなかった。
身体の一部が外部化されたような感覚
そんなとき、医師から「リハビリロボットを試してみませんか」ともちかけられた。願ってもない。良くなりそうなものは何でもやりたいと思っていた。
病院に導入されていたのはトヨタ製の「ウェルウォーク」と呼ばれるリハビリ支援ロボット。脚に装着したウエアラブルロボットがサポートし、ルームランナーのようなベルトコンベヤーの上を歩く。大型の体感ゲーム機のようだ。
自分のできない動きをロボットが補ってくれて、歩いているような感覚になれる。身体の一部が外部化されたような思いもあって、ちょっとした「未来感」があった。
装置についたTOYOTAのロゴを眺めながら、なぜ自動車メーカーがリハビリロボットを手がけているのかと不思議に感じ「復職できたら取材したいな」と考えながら訓練していた。
医療機器として登場するまでに10年
ありがたいことに、その後、取材現場に戻ることができたので、当時の疑問をトヨタの開発者に尋ねてみた。答えてくれたのは、トヨタ新事業企画部ヘルスケア事業室の鴻巣仁司さんら開発チームのみなさんだ。
鴻巣さんによると、開発のきっかけは平成17年の日本国際博覧会(愛・地球博)。トヨタがパビリオンで二足歩行ロボットを展示したことにさかのぼる。
「万博で来場者に楽しんでもらった技術を世の中に役立つようにしたいと思ったんです。なかでも医療や介護の世界で、ロボットの動きで人を助けることができると考えました」
開発が本格的にスタートしたのは2年後の19年。それから、藤田医科大(愛知県豊明市)と共同研究しながら、医療機器として登場させるまでには約10年の歳月がかかったそうだ。
リハビリロボットの最終目的は利用者が自分の力で歩けるようになること。利用者の足の代わりになることではない。回復の度合いに応じてロボットのアシスト機能を調整できるというのが大切で「ロボットが助けすぎてはダメ」ということが開発のポイントになった。
また、利用者が自分の歩き方を検証するためには、映像で歩き方を確認できたり、良い点、悪い点をわかりやすく伝えたりする機能も大事。音や映像などを使いながら、いかに効果的なフィードバックをするのかという点にも苦心した。
開発上、最大の難所になったのは、装着するロボットが重いという点だ。開発チームは試行錯誤を繰り返すうちにロボットをV字ケーブルでつるす方法を考案。重さの問題を解消する手法にたどり着いた。
ウェルウォークを配備している病院施設は、現在は全国約110カ所ある。ウェルウォークを使った場合、使用しない場合よりも早く歩けるようになったり、歩行するときのスタイルがきれいな形になったりするといった研究論文が発表されているそうだ。
雲をつかむような思いだったぼくのリハビリだが、医療スタッフのみなさんのサポートやロボットのアシストによって次第に歩く感覚を取り戻した。元通りではないが、いまでは多くの場所を自分の足で歩ける。
ウェルウォークは脳卒中患者のリハビリを想定したロボットだが、「どんな病気にも効く薬がないように、科学が進んでも一つのロボットがすべての問題を解決してくれることはない」という話が印象的だった。開発チームの中村卓磨さんは「困っている人がいたら、その問題ごとに対応する最適解があるはず。その最適解を増やしていけば、誰も取り残されない社会をつくっていけると思う」と話していた。
開発チームのみなさんはいきなり夢の万能ロボをつくろうとしているわけではないんだと感じた。現実にある一つ一つの課題と向き合い、それを技術の力で解決しようと試みているのだな、と。
ぼくのリハビリはこうしたエンジニアのみなさんの矜持(きょうじ)にも支えられていたのだと改めて思った。(河居貴司)
◇
この記事へご意見や感想、みなさまの経験談を寄せてください。メールアドレス goiken1@sankei.co.jp
車いすを使用していたときの筆者=令和2年3月かわい・たかし WEB編集室長兼新聞教育編集室長。平成9年産経新聞入社。和歌山、浜松支局を経て社会部。関西の事件や行政などを担当してきた。京都総局次長、社会部次長を経て現職。46歳で脳出血を発症したがその後、復職。リハビリを続けながら働いている。この連載では、病気の発症や入院生活などについてつづっている。