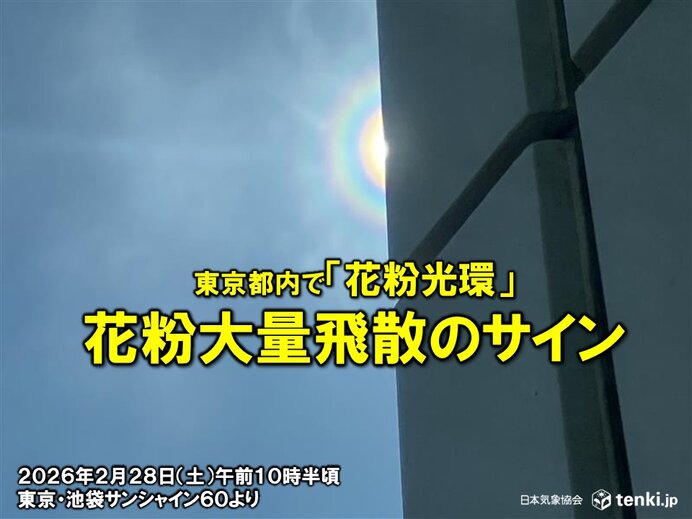また「2割の壁」東大合格者の女子比率が停滞…女子枠の検討は?批判殺到の女子向け家賃補助が「逆差別」ではない理由【国際女性デー】(2025年3月12日掲載)|日テレNEWS NNN

2025年3月12日 8:00
東京大学の一般入試の合格発表が10日に行われ、合格者の女子比率は20%にとどまりました。女子学生を増やすことに取り組んでいる東大ですが、約20年間「2割の壁」をはさんで停滞しています。理事・副学長の林香里教授は、日本テレビの単独インタビューに応じ、「女性の能力とか努力、個人の問題ではない」と、社会構造の問題を指摘したうえで、高等教育の低迷につながる損失だと危機感を表しました。
もうひとつは、東京大学としても、サイエンス、人文社会もいろんな競争がありますから、いい人材が欲しいわけですよ。女性がきちっと志望してくれないことは本当に損失だと思います。高等教育って、新しい発想とか、違う見方がぶつかり合って切磋琢磨していく場所ですから。いつも同じようなグループだけで実験したり議論したりということだったら、低迷しちゃいますよね。
福井:今年10回目になった学校推薦という枠がありますね。今回、学校推薦枠だけで見ると、ほぼ男女同数が実現されたと思います。学校推薦型選抜は、多様性を確保するという意味においてどういう位置付けですか?林:一発勝負の筆記試験ではないところが、別の才能を発見している証拠ですよね。入り口を複数化していくというのはいいと思います。福井:「女子だから受かりやすいのか」と言われることもあるかと思うんですけど。林:問題は、男性と女性が半々の学校推薦よりも、筆記試験で男性が8割ということが、この20年続いていることですよね。福井:一発勝負の一般入試の制度自体の改革も検討されているんですよね?林:藤井総長も“入試の多様化”をかねてから申しております。東京大学のもう1つの課題として、外国人も東京大学まで来て紙の試験を受けるというスタイルが、グローバル化で古くなってきています。そういう意味でも、ちょっとずつでも変えていかないと、時代に追いつかなくなっちゃうと思います。福井:女子枠に関してはいかがお考えですか?林:すごく賛否両論あって、「女子枠で入った」と言われる女性の学生さんにどう考えてもらうかとか、いろいろあります。ですから私も必ずしも女子枠が1番良いソリューションだとは思いません。カンフル剤としては1つのチョイスだと思いますし、女子枠を取り入れている他の大学は立派だなと思います。福井:女子枠の議論に女子学生が反対するという話を聞いて少し驚いたんですが、「君も女子枠で入ったの?」と言われることが怖いという声も実際あるんですか?林:あると思いますね。そもそも“一般入試が王道”みたいに理解されていて、高校の先生も、予備校もそうなんですよね。それ以外は“楽してる”みたいな。その考え方を変えていかないといけません。いろんな試験で多様な才能を集めていくイメージを持たないと、日本の社会にとっても良くないと思いますね。福井:今の男女比率でいうと、理系の女子がとても少ないです。「理系だけは女子枠を」など、分けて対策する可能性もあるんでしょうか?
林:例えば環境問題とかデジタル化とか、理系・文系がパシッと分かれているやり方も見直さなくちゃねと言っているところなので、「理系女子だけ女子枠」という感覚はないです。
福井:首都圏出身の学生が多いという問題もありますよね。地方出身の女子となると、さらにマイノリティーになってしまいます。私自身も四国から受験した東大女子だったんですが、地方出身の女子に対するアプローチはありますか?林:女性在校生に、高校に行って東京大学の良さを説明してもらうために、交通費の補助をするとか。また、女子高校生のためのオンラインの説明会を毎年実施しています。そこには必ず藤井輝夫総長も出てもらって、直接語りかけます。福井:ロールモデルを提示する取り組みですね。20年前ですが、私は入学するまで東大の女性と会ったことがありませんでした。今回、私は当事者だと思って臨みました。でもよく考えると、私は実は当事者ではなくて、本当の当事者はきっと私の周りにいて、私より勤勉で優秀であったけれども東大を志望しなかった彼女たちなんだなということがわかりました。どうすればあのとき「一緒に志望しようよ」と言えたんだろう、と。林:地方から出てきて、浪人を前提に誘うってなかなか難しいと思うと、やっぱり大学にも責任があると思うんです。必ずしも東京大学に来ることがベストというわけじゃないんですよ。可能性として試してみようと思ってくれる雰囲気をもっともっと作っていかなくちゃと思いますね。福井:私の場合は、県人寮が女子も充実していたのがラッキーだったと思います。林:女性学生に対する住まい手当てをちょっと前から始めたんですけど、それが「逆差別だ」とすごく批判されました。だけど、東京にはたくさん県人寮がありますが、実はその多くが男性だけか、女性用の部分が小さいんですよね。浪人とか県人寮、そういうことが積み重なって、本題である、例えば物理を勉強したいとか、海外に行って大きな装置で工学を研究したいとか、あるいは弁護士になりたいとか、そういうことがどんどん消えていってしまう。それがとても残念だと思います。福井:高校の先生たちへのアプローチはありますか?
林:高校の先生や親御さん、そういう大人にもアプローチしなくちゃいけないと思います。日本では世界の国に比べても、高校の先生は男性が多くて、特に理系になるとほとんど男性なので、そこからロールモデルが少なくなっていくというのも、女性に対しての動機付けが弱くなっていく1つの原因だと思いますね。
福井:「#言葉の逆風」プロジェクトの反響はいかがでしたか?林:嬉しかったです。応援してくださる方が多くて。実はやる時はびくびく。特に私は「大丈夫かな?」とか思っていたんですが、男女共同参画室の1番若い研究員たちが企画をして、1年ぐらい前から計画をしたんですね。やるからには、若い研究者や学生にもアンケートしてポスターを作りました。やってみると、「よくやってくれた」とか「私も本当にそう思ってたの」という人が次々と出てきて、そこから会話が始まるんですよね。それが1番良かったです。今まで口に出して言えなかったことが、あのポスターによって「言ってもいいんだ」と。
研究者って、1人勝負なところがあるんですよ。自分1人で研究するとなると案外バラバラで、そんな話もしないんです。キャンペーンをすることで横の連帯ができて、繋がっていくと、やっぱりちょっと強くなれる。言葉の逆風も押し返すことができる。バラバラだと押し返せないことがたくさんあるので、そういう意味で良かったかなと思います。
日テレ報道局ジェンダー班のメンバーが、ジェンダーに関するニュースを起点に記者やゲストとあれこれ話すPodcastプログラム。MCは、報道一筋35年以上、子育てや健康を専門とする庭野めぐみ解説委員と、カルチャーニュースやnews zeroを担当し、ゲイを公表して働く白川大介プロデューサー。 “話す”はインクルーシブな未来のきっかけ。あなたも輪に入りませんか?
番組ハッシュタグ:#talkgender
最終更新日:2025年3月12日 9:59