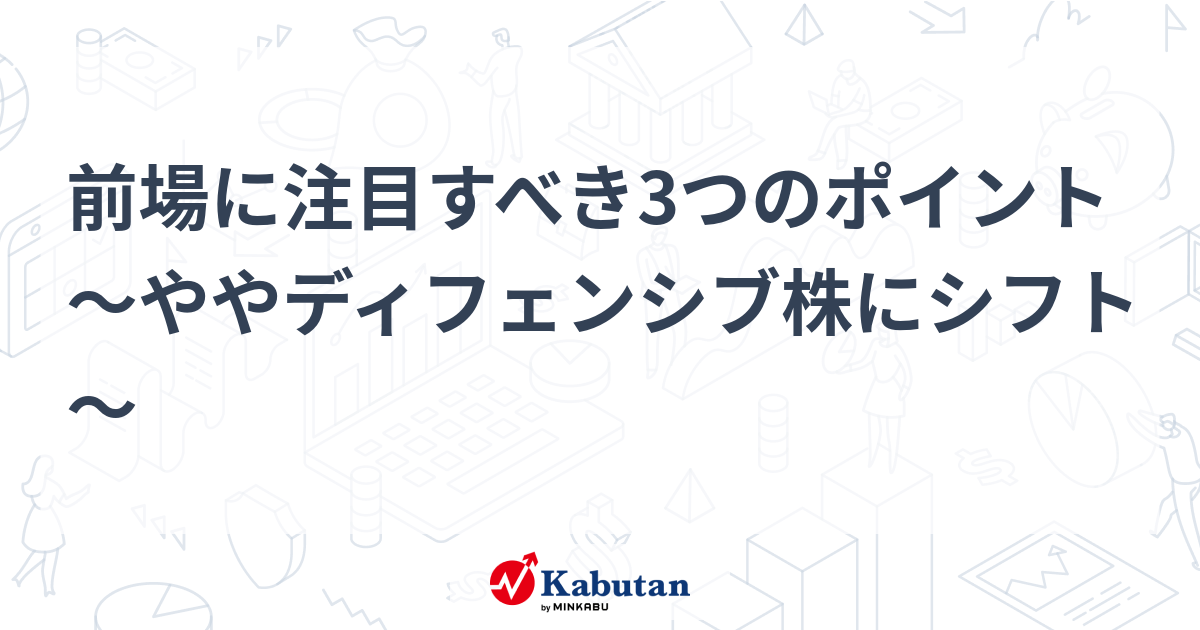中国株にバブルの兆し、上昇相場は低迷する経済指標に反する動き

米国による関税と不動産不況で中国経済は打撃を受けている。一方、株式市場は強気相場に入っている。このいびつさが相場の持続性に疑念を生んでいる。
中国本土株の時価総額はこの1カ月で約1兆ドル(約147兆円)増加。上海総合指数は10年ぶりの高値を記録し、CSI300指数も年初来安値から20%超上昇した。
今回の相場上昇の背景には、潤沢な資金を持つ投資家が株式市場にシフトしていることがある。安定した上げ相場は急激な調整リスクが低いことを示唆しているものの、一部のアナリストはバブルが生じつつあると警告している。
ロンバード・オディエ・シンガポールのシニアマクロストラテジスト、ホーミン・リー氏は、「正しいか誤っているかは別として、市場はマクロ経済の基礎的条件が改善すると見込んでいる可能性がある」と指摘。その上で、「インフレ率がゼロ%近くにとどまり、企業の価格決定力が内需の弱さという深刻な逆風を受けている場合、強気相場が持続することはない」と述べている。
7月の消費者物価指数は横ばい。生産者物価指数は2年10カ月連続で低下し、国内総生産(GDP)デフレーターもマイナスが続いている。政府は過剰生産能力の抑制と価格競争の是正に乗り出しているが効果は限定的だ。
野村ホールディングス(HD)は、株高が経済減速への政策対応をより難しくしていると指摘。経済活性化策が株式市場のバブルを助長するリスクがあるという。
市場関係者は、2015年に起きた株式市場のバブルから崩壊に至るサイクルとの類似性を見いだしている。当時は信用取引の急増が株価急伸を引き起こしたが、当局がレバレッジ取引を取り締まったため歴史的な暴落が起きた。
今の株高は10年前より抑制されているものの、経済の低迷や工業製品価格の下落は共通している。また、当時も「インターネットプラス」構想やビッグデータなどの新技術が熱狂をあおっていたが、これは現在のAIブームと似通っている。
信用取引の債務残高は2兆1000億元(約43兆円)で15年ピーク時の2兆3000億元に近い水準。中国の株価上昇は、流動性や信用残高との相関が強い傾向にある。
ロータス・アセット・マネジメントのハオ・ホン最高投資責任者(CIO)は「市場の豊富な流動性とアニマルスピリッツの復活傾向は10年前の狂乱期を思い起こさせる。現時点ではまだ初期段階だ」と指摘している。
原題:Bubble Risks Grow as China’s Bull Run Defies Economy Angst (1)(抜粋)