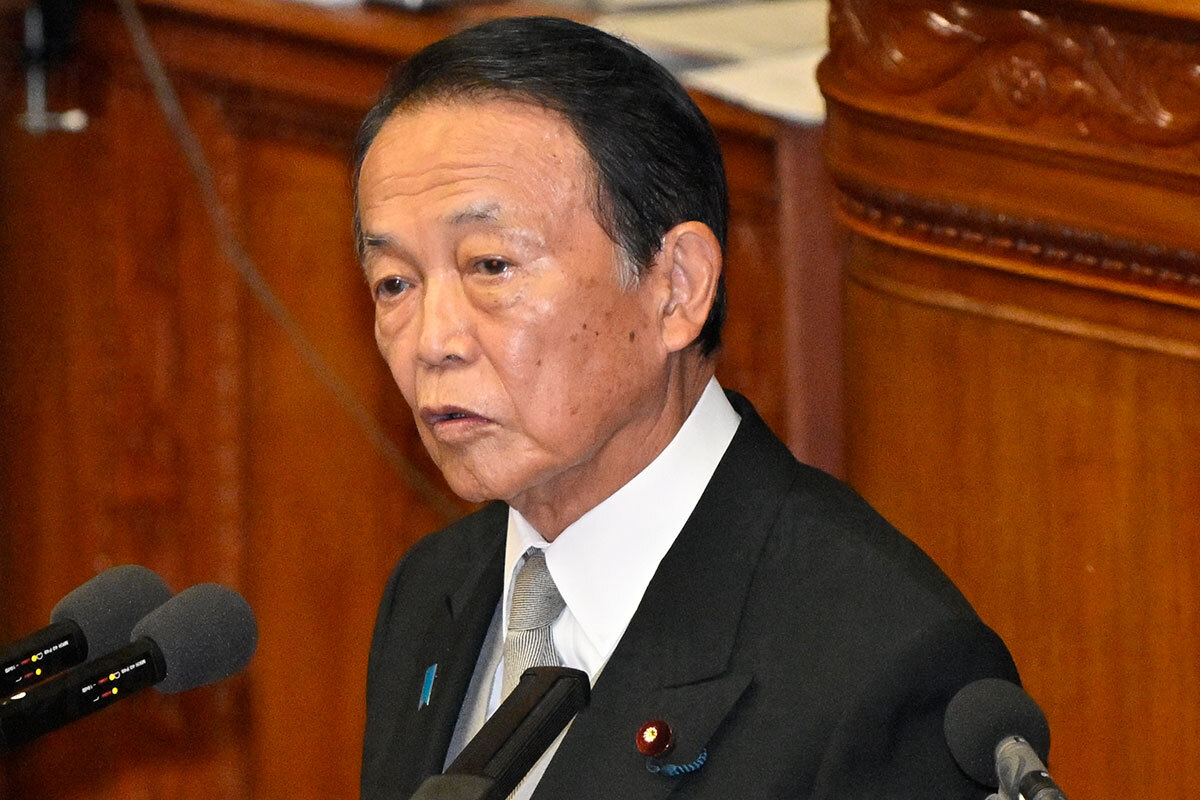私たちがつくる「公・公共」 みんなが〝ただの人〟になれる社会とは

「公」や「公共」というと、国や行政が担う大きな話、自分とは離れたものという認識があるかもしれません。「公」は国家や政府というイメージですが、「公共」は社会全体が関わるもので、私たちの手で作るものでもあります。言語哲学者で「公正」や「正義」についての著書がある朱喜哲さんと、弁護士で公共訴訟の代理人を務めてきた亀石倫子さんが、これからの「公共」のあり方とその可能性について語り合いました。
2026年の世界はどんな方向に進むのでしょう。社会課題は山積する中、いまあらためて問い直したい、立ち止まって一緒に考えたい「時代のことば」を、対談で掘り下げます。
――朱さんは、世界的企業であるビッグテックの台頭による「公共」の変化について言及されていますね。
【朱喜哲】 ソーシャルメディア隆盛の時代においては、私企業であるプラットフォーム事業者が世界中の言論インフラを担い、実質的にパブリックな役割を果たしています。だからこそ企業に責任と倫理が問われています。一方、国家はその存在感を低下させています。
憲法では国民主権がうたわれ、国民は主体的に国家に関わるメンバーシップ意識を持てる。でもパブリックの担い手が企業だとしたら、私たちはユーザーです。契約やプライバシーポリシーがあっても、客としてサービスを利用するだけです。私企業が「公共」を担いつつある現状の危うさがあると思います。
朱喜哲さん=大山貴世撮影米国の哲学者リチャード・ローティ(1931~2007)は、パブリックなものとプライベートなものを「バザールとクラブ」という比喩で表現しました。バザールは生計を立てるために人々が集う公共的空間で、クラブは帰宅前に立ち寄りくつろげる私的空間です。バザールにはルールがあり、だからこそ安全ですが、疲れる場所でもある。そこで、仲間がいてガス抜きができ、度を超すと注意もしてもらえるクラブも必要になります。
しかし、いまや言論空間はすべてパブリックなものになりつつある。過去の失言や問題発言が掘り起こされ、私信もさらされてしまう可能性がある。だから人々は、問題がないように気をつけて発言しますが、そのためにストレスやうっぷんがたまってしまう。そして、クラブ的な場がなくなった今、バザール的な世界で身もふたもない本音を言う政治家らが快哉(かいさい)を得てしまっている。複雑にねじれた状態だとみています。
【亀石倫子】 公共というものにゆがみやバグが生じていると思います。テクノロジーの発達や社会の変化に対して、公は古いままで制度疲労を感じることもあります。法律のバグを取り除いて修復する手段の一つとして、公共訴訟に取り組んでいます。主権者である私たちが、「公」に関わる手段で、新しい公共をつくる試みだと思っています。
亀石倫子さん=大山貴世撮影かめいし・みちこ 1974年、北海道生まれ。弁護士。社会課題の解決をめざす「公共訴訟」を支える「LEDGE」代表理事。
――公共訴訟は、国などを相手に社会課題の解決や差別撤廃を求める訴訟です。「在外日本人選挙権訴訟」では公職選挙法が改正され、「らい(ハンセン病)予防法違憲国家賠償請求訴訟」では地裁の違憲判決に国が控訴せず原告に謝罪するなど、公や公共を変化させてきました。どのような意義がありますか。
【亀石】 代議制民主主義では公に関わる手段として、選挙の投票や署名などがありますが、とにかく声を集めて大きくしないと物事を変えられない。
でも、公共訴訟は1人の原告から世の中を変えられる可能性があります。さらに、1人が声を上げることによって連帯が生まれ、報道されて問題提起にもなります。そもそも政治の場面では人権の話はあまり聞きません。
【朱】 不安や不満、ずるいという本来は個別に事情の異なる個々人の感覚を、例えば「日本人ファースト」などあいまいかつ巨大すぎる大きな言葉で糾合してしまうのが、選挙や代議制民主主義の問題点かもしれません。
一方、公共訴訟は、公を訴えると同時に修復する訴訟でもあると思います。インフラを整え直しているといってもいい。
公共訴訟の原告は、困りごとや不利益がある人を代表して、社会のバグや制度疲労を直す役割を引き受けてくれている。じつは「みんなの」訴訟なんですね。
亀石倫子さん(左)と朱喜哲さん=2025年12月8日、大阪市天王寺区、大山貴世撮影【亀石】 医師免許を持たずにタトゥーを施したとして彫り師が医師法違反に問われた裁判の控訴審(2018年)では、日本で初めてクラウドファンディングで裁判費用を集めました。一審で有罪判決を受け、ネガティブに受け止める人も多かった。どのように呼びかけるか悩んだすえ、当たり前にしてきた仕事が突然犯罪だとして排除されても良いか、そういう社会で生きていきたいか、という発信を心がけました。
「タトゥーは嫌いだけど」と前置きした上で、「でもこういう社会では自分は生きたくない」「こんな社会は恐ろしいと思う」と応援してくれる人が増えていった。結果、目標金額を上回る寄付をいただき、逆転無罪を勝ち取りました(20年最高裁で確定)。
【朱】 声を上げ、どんな社会にしたいのかをみんなが話せる社会こそ、目指すべきものだろうと思います。
クラブ風営法違反訴訟(14年一審で無罪、16年最高裁で確定)も希望を与えてくれました。戦前から続く時代遅れの風俗営業法を盾にした摘発に対し、法律は罰したり拘束したりするためのものではなく、一緒に社会をつくるためのルールだから、かいくぐるのではなく、正面から向き合えばいいのだと示してくださった。
時代に合わない法律は、手続きを踏めば変えられるんだというのも大事なメッセージです。
【亀石】 クラブ訴訟は、いままで夜も踊っていたのに、急に違法だと言われ、なんかおかしくない?という直感から始まりました。原告は、まさか自分の困りごとが職業選択の自由や表現の自由の侵害、憲法上の人権の問題だとは思っていませんでした。直感的におかしいと感じることは、多分憲法の何かの自由とかに関わっている。
私が代表理事を務めるLEDGE(公共訴訟を支える専門家集団)では今、警察による人種差別的な職務質問(レイシャルプロファイリング)を終わらせるための訴訟をしています。真面目に働いて納税もしているのに犯罪者であるかのように決めつけられることは、本当に尊厳を傷つけられることです。憲法14条が守ってくれると位置付けています。
対談する亀石倫子さん(左)と朱喜哲さん=2025年12月8日、大阪市天王寺区、大山貴世撮影【朱】 憲法もインフラということですね。
【亀石】 あたりまえ過ぎて普段意識しないけど、憲法は、生きるベースです。
■「正しさ」を競うのではなく
――CALL4(社会課題の解決を目指す公共訴訟を支援するウェブプラットフォーム)のイベント(対談前日に実施)で、原告の方々が裁判を通して自身が変化したと話していたのが印象的でした。
【亀石】 訴訟は原告の悔し…
この記事を書いた人
- 吉村千彰
- デジタル企画報道部|Re:Ron編集部
- 専門・関心分野
- 文化、芸能、海外ドラマ、フィギュアスケート