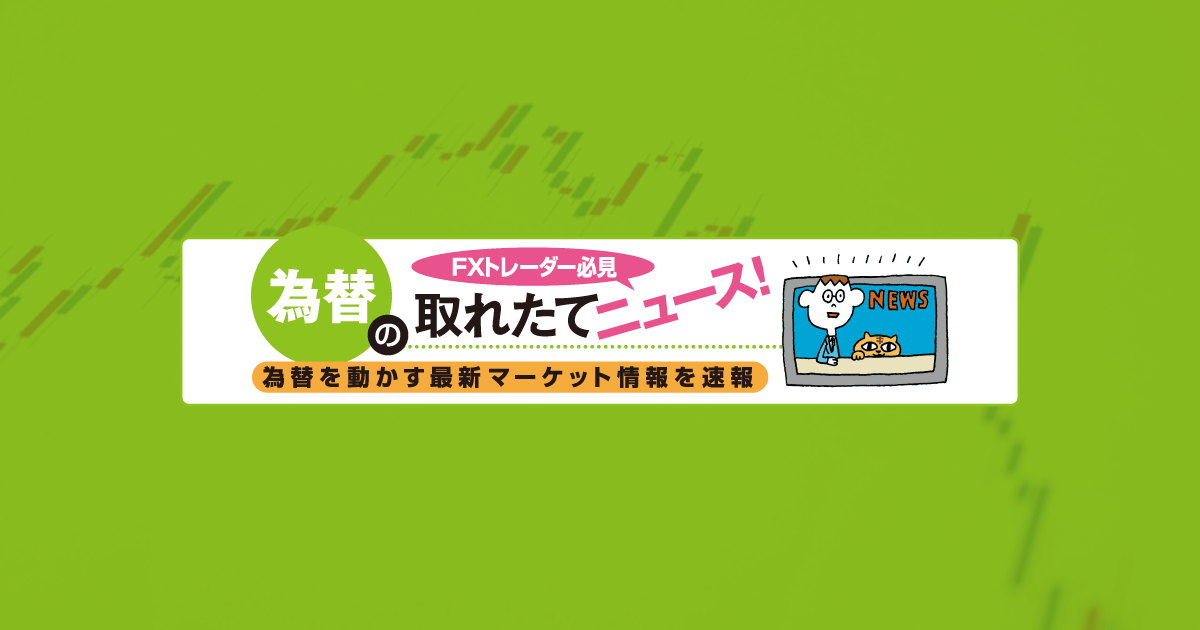海外動向など「不確実性高い」、物価に上下のリスク=植田日銀総裁

[東京 26日 ロイター] - 日銀の植田和男総裁は26日、高騰が続く食品価格について、外食などへの波及が続き、サービス価格が引き上げやすくなるなど、インフレが経済に広がる可能性があれば「利上げで対応することも考えないといけない」と述べた。ただ、各国の通商政策の動きやその影響を受けた海外の経済・物価動向など、日本の経済や物価を巡る「不確実性は高い」とし、物価見通しは「両サイドにリスクがある」と話した。
衆議院財務金融委員会で「通貨および金融の調節に関する報告書」(半期報告)の概要を説明した後、与野党の委員の質問に答えた。半期報告で植田総裁は、現在の実質金利は極めて低い水準にあるとの認識を示し、先行きの金融政策運営については「展望リポートで示した経済・物価の見通しが実現していくとすれば、引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整していく」と述べた。
<見通しより物価上振れなら、緩和調整の度合い強める>
植田総裁は、消費者物価指数(CPI)の上昇率がすでに3年程度2%を上回っている中、2%の物価目標を実現していないと判断する理由について、基調的物価上昇率が2%に達していないからだと説明した。基調的物価上昇率は単一の指標で十分把握できるものではなく「10種類、15種類など様々な指数をつくって、それを眺めて総合的に判断している」と説明した。同席した加藤毅日銀理事は、一時的な物価変動の影響を受けにくい品目やサービスの価格上昇率はおおむね1%程度と述べた。
植田総裁は足元の食品価格上昇について起点は天候要因などと指摘。食品価格の上昇が一時的ならば金融政策で対応すべきではないが、外食などに波及が続き、サービスの値上げをしやすくなるなどインフレが経済に広がる可能性がある場合は「利上げで対応することも考えないといけない」と回答した。また、日銀の見通しよりも物価が「上振れる場合は緩和調整の度合いを強める」とも説明した。
足元の物価情勢については「CPIが上昇しているという意味でインフレの状態」との認識を示した。今年の春闘に関し、「生産性の上昇率が1%とすれば3%の賃上げは2%の物価上昇と整合的で、これが定着するかが重要」と指摘した。
加藤理事は、資産市場に過熱感は見られていないが「今後の動向は非常に注意して見ていかなければならない」とも述べた。
<物価目標、達成後の修正議論否定せず>
植田総裁は、2%物価目標の持続的・安定的達成が実現しない中で目標を見直すのは「やってはいけないことだ」とした一方で、目標を達成したと「人々に納得いただけるような状況になった時に2%目標を続けていくのがいいのかどうかという議論が起こる可能性はある。そこでもう一度(物価目標を)改めて考える可能性は否定すべきではない」と話した。
2%物価目標は「ある程度の幅がある」概念とした上で「(目標達成と見なせる)まだ狭い幅の中には入ってきていない、もうちょっとのところだ」と表現した。
2013年1月に策定した政府・日銀の共同声明へのコメントは差し控えたいとした。
<ETFの取り扱い、検討状況の言及に否定的>
日銀が保有する上場投資信託(ETF)の処分について「すぐに行うことは考えていない」とし、処分を含めた今後の扱いは「ある程度時間をかけて検討したい」と改めて述べた。「(検討の)途中経過等を話すのは、市場に不測の影響を与える可能性があり、なかなかできない」と話し、現時点の検討状況を詳しく述べることはしなかった。
ETF永久保有の可能性を問われた植田総裁は「現時点で、そうしたオプションがあり得ないとするところまでは考えていない」と述べた。
13年以降の大規模緩和について「一定の副作用はあったものの、現時点においては、全体としてみれば日本経済に対してプラスの影響をもたらした」と述べた。ただ、国債市場の機能度の回復が進まなかったり、大規模緩和の副作用が遅れて顕在化する可能性も留意が必要だと話した。「将来起こり得ることについては、注意深くいろいろな可能性を念頭に置いておく」とした。
私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」, opens new tab