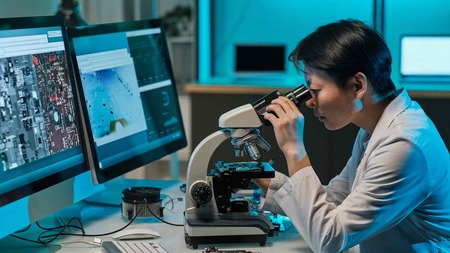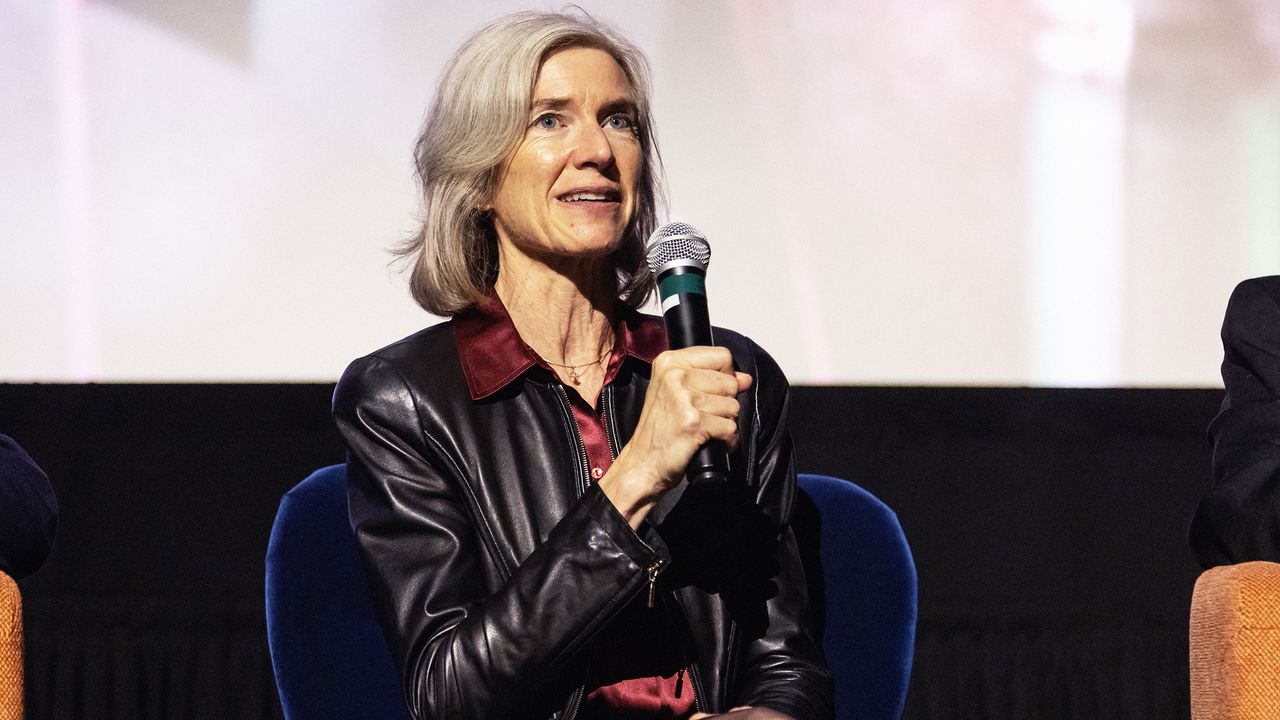イラつかず、マウントもとらず何度でも直してくれる…医師・岩田健太郎が生成AIにお願いしている苦手な仕事 「AIを恋人にする若者が増えても驚かない」
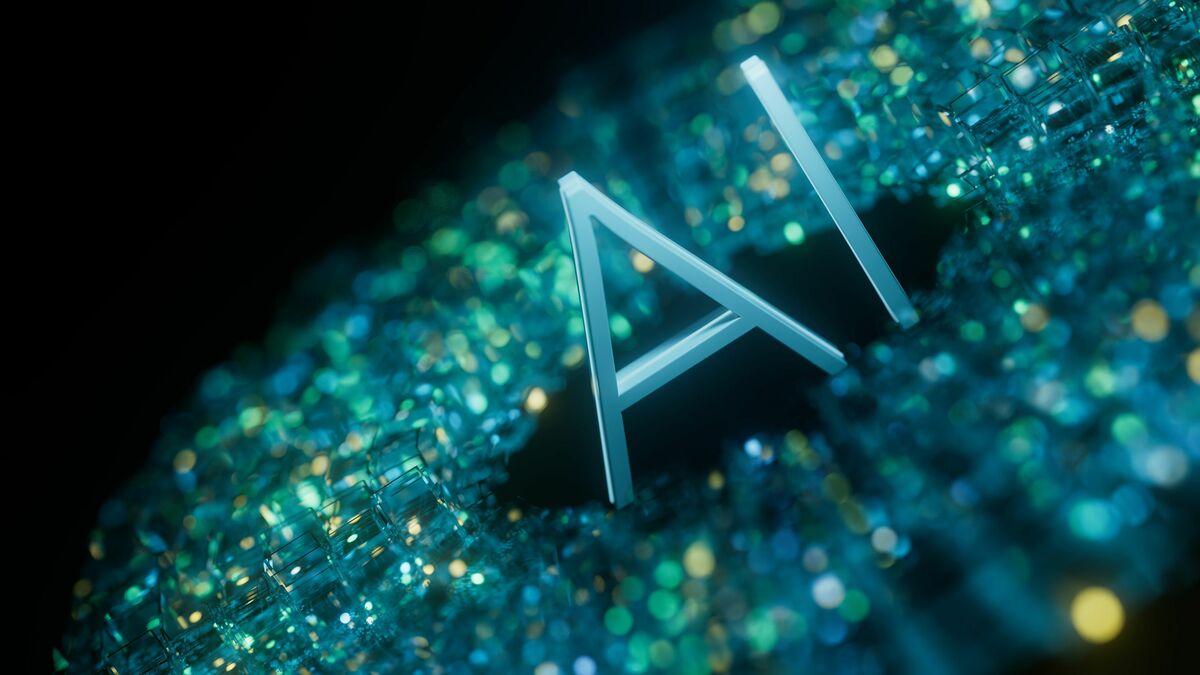
しかし、冷静になって考えれば、ルサンチマンをベースに議論するのは理性的でも、論理的でも、そして科学的でもない。ルサンチマンをベースにした時点で(たとえ哲学的知見を援用しようと)、その科学論は失敗しているのである。
私見だが、世の中で一番役に立たない感情が嫉妬心であり、二番目に役に立たない感情がルサンチマンだと思っている。いずれも負のエネルギーであり、生産性はゼロである。嫉妬心は他人の足を引っ張らせるから、むしろマイナスの生産性をもたらしかねない。
ルサンチマンは仲間内での結束を高め、「他人をdis(ディス)る」ことによる感情的な快楽をもたらすこともあるが、それが何かのポジティブなプロダクトをもたらすことはないし、周囲からは怖がられるだけである。
ルサンチマンの感情が、ルサンチマンの原因を解決するのに役立つことは少ない。ルサンチマンをもたらす原因は、ルサンチマン以外のエネルギーで克服するのが合理的である。例えばプラグマティズム。プラグマティズムとは、チャールズ・サンダース・パースを創始者とするアメリカの哲学で、「実用主義」と訳される。
「真のアウトカム」とは何か
プラグマティズムにおいて大切なのは「結果を出す」ことである。日本社会は全体的にこの「結果にこだわって」こなかった。プロセスのほうが大事なのである。
スポーツの世界で喩たとえるならば、夜を徹して素振りの練習をする、という「死ぬ気でトレーニング」というプロセスのほうが大事なのだ。それで疲れ果てて、肝心の試合でさっぱりヒットが打てなくてもかまわないとすら思っている。
いやいや、部活動では常に指導者も親御さんも「結果」にこだわっているではないか、という反論もあるかも知れない。しかし、小学生や中学生時代の試合の「結果」はほんとうの意味での「結果」ではない。難しい言い方をすれば、「真のアウトカム」ではない。
野球であれ、サッカーであれ、本当に目指すべきは競技年齢のピークでパフォーマンスを最大化することであろう。大リーグやプレミアリーグで活躍するのが、「真のアウトカム」なのだが、なぜか多くの保護者は小学生とか高校生の大会で勝つことに全力を尽くしてしまい、悪くするとそこでバーンアウト、その後は競技をやめてしまったりするのである。若いときは、目先の試合の勝ち負けや優勝よりも、自分が選手として成長するほうを優先させるべきなのだが。