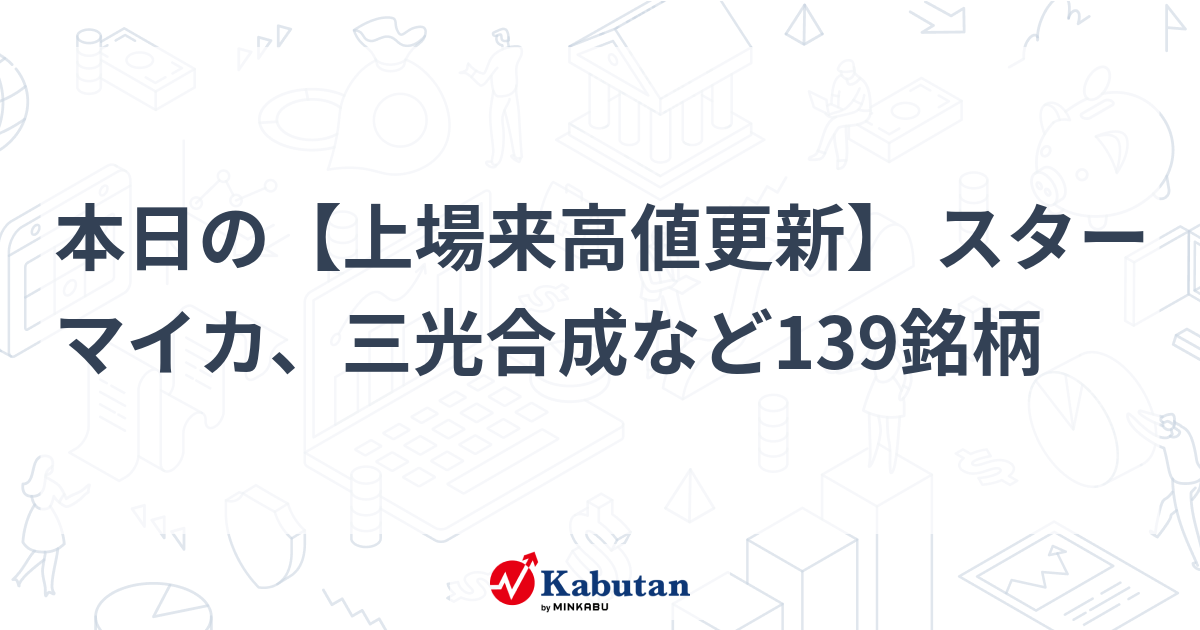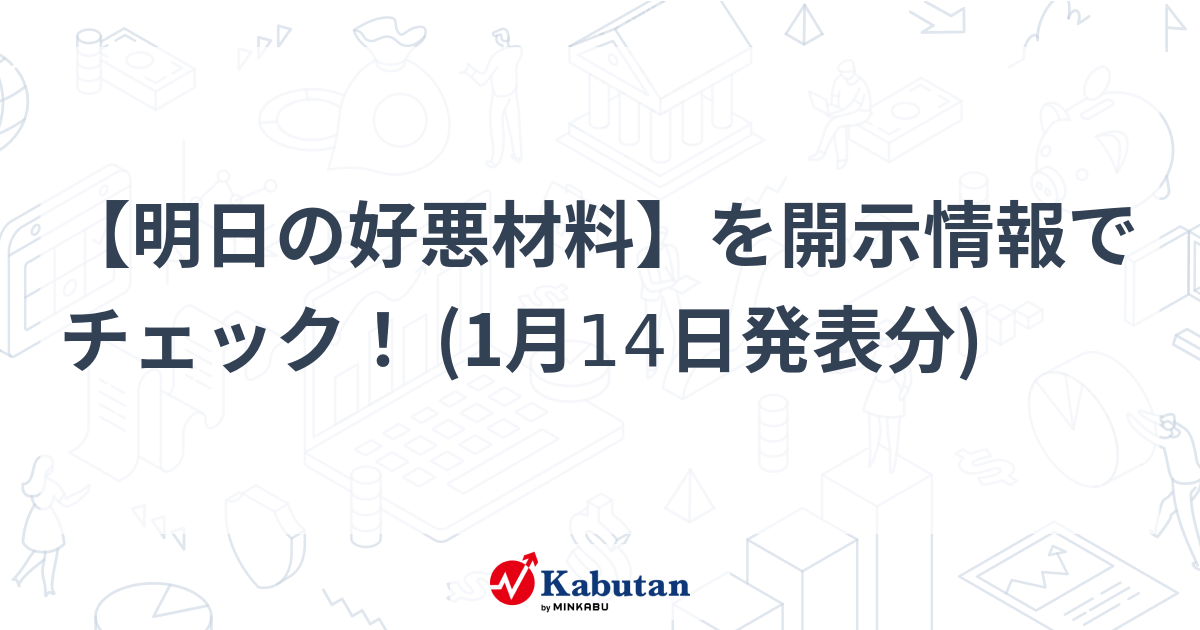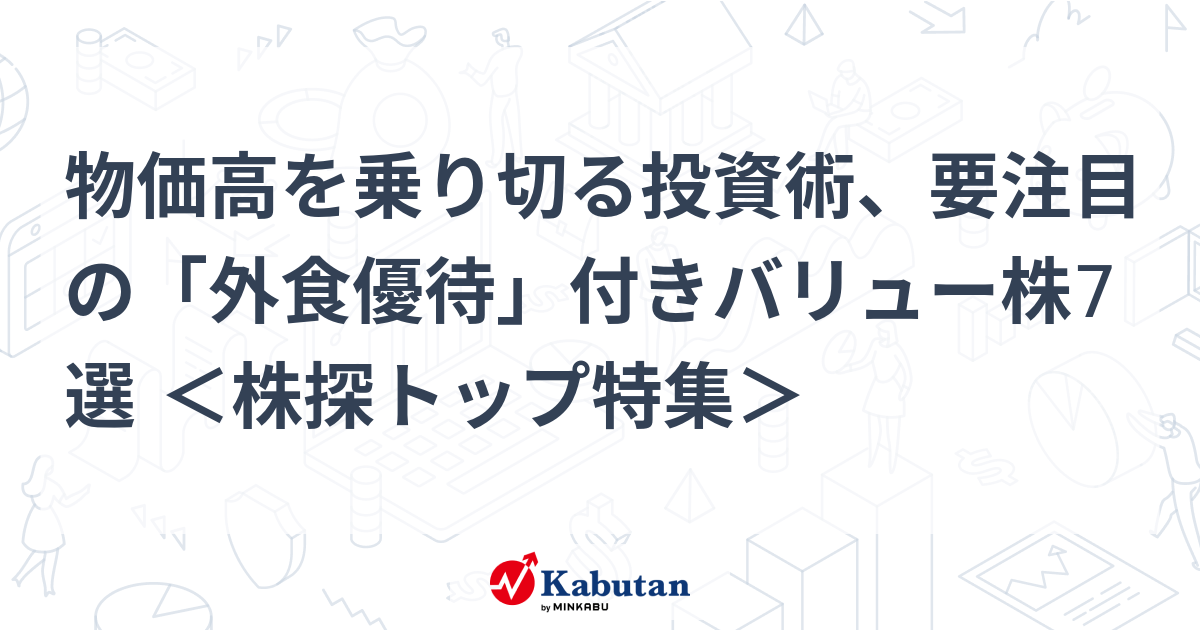日銀のマイナス金利解除から1年、銀行急回復の一方で節約続く消費者

日本銀行の歴史的な政策転換から1年。大手銀行は過去最高益を更新する見込みだが、消費者は物価高の影響で節約を余儀なくされている。政治の場では、借り入れコストの上昇に対して歳出をいかに抑制するかを巡って論争が激しさを増す。
日銀の植田和男総裁は昨年3月、春闘での記録的な賃上げを追い風に、世界で最後となったマイナス金利など大規模緩和の解除に踏み切った。所得環境の改善は、消費者が物価と経済成長のけん引役となってインフレを後押しするとみられた。
昨年3月の17年ぶりの利上げに続き、政策金利は数カ月の間にさらに2回引き上げられた。これはバブル経済のピーク期だった1989年以降で最も早いペースでの利上げだ。エコノミストらの間では、日銀が次回3月18、19日の金融政策決定会合では動かず、7月に追加利上げを行うとの見方が多い。
日銀は、賃金上昇と消費、経済成長の持続的な循環を構築することは、物価上昇に社会が慣れるための苦労に値すると長らく論じてきた。エコノミストや政策当局者は、その循環が定着する確度が高まりつつあるとみているが、食料価格の高騰に苦しむ消費者はそれほどの確信はない。
「賃上げよりも物価高のペースの方が全然上回っていると感じている」と話すのは会社員の藤井雅史さん(50歳)。4人家族で子供が2人いる。預金に対する利上げの効果は「全くない」と語った。
根強いインフレは、国内の変化を加速させる一因となっている。企業はコスト上昇分を価格に転嫁する動きを強めている。将来の物価上昇を見越して、先細る年金に頼るのではなく、退職後の資金を確保する新たな手段を探る個人投資家が増えている。株主重視のコーポレート・ガバナンス(企業統治)は、停滞に慣れきった日本経済の一部に利益重視の姿勢ももたらしている。
現段階で最大の勝者は銀行だ。厳しい局面でコスト削減に努めた3メガバンクグループはいずれも、貸出金利の上昇をてこに2025年3月期決算で最高益を更新する見通しだ。
三井住友フィナンシャルグループ(FG)は、昨年2度の利上げを踏まえて今期900億円の資金利益押し上げ効果を見込む。今後政策金利が0.25%引き上げられるごとに、年間1000億円の増益をもたらすという。一方で、普通預金金利は0.2%にすぎない。
銀行株は昨年3月から約29%上昇しているのに対し、東証株価指数(TOPIX)は横ばいだ。ポートフォリオの分散化が進んでいない中小銀行の場合、保有債券の価格下落によるデメリットが金利上昇によるメリットよりも大きい可能性が高いため、短期の見通しにおいて明るさは劣る。
円相場は日銀の追加利上げによって円高方向に振れるともみられていたが、依然として大きい日米の金利差を背景にその後も円安傾向は続いた。日本の通貨当局は24年、過度の円安進行を抑えるため15兆円規模のドル売り・円買い介入を実施した。
足元の円相場は、日銀の追加利上げを見込む投資家の円買いやトランプ米大統領の関税政策への懸念から安全資産を求める動きで1年前の水準に戻っており、1ドル=150円を若干下回って推移している。
円の価値は13年前の半分程度になっている。継続的な円安は海外からの観光客増加につながり、ホテルやレストラン、小売業を活気づけている。一方、日本は食料や燃料の多くを輸入に頼っているため、円安はインフレを加速させる要因となる。
家計は生活費の高騰で購買力が低下し、節約や値引き品探しを余儀なくされている。日銀は政策判断で生鮮食品を除いた消費者物価指数(CPI)を重視しているが、消費者はそれらを含む総合指数が前年比4%上昇している影響を実感している。1月の毎月勤労統計調査(速報)では名目賃金の増加継続が示されたものの、物価変動を反映させた実質賃金は1.8%減少した。
24年10-12月期の国内総生産(GDP)では、個人消費は実質ベースで前期比横ばいだった。これは成長の好循環がまだ本格的に表れていないことを示している。
元日本銀行理事の門間一夫みずほリサーチ&テクノロジーズ・エグゼクティブエコノミストは、コストプッシュに利上げで対応することは「悪手だ」と主張。所得の低い層ほど住宅ローンなどの負担が増す一方、富裕層は金融資産の利息収入が増え、格差を拡大させる要因になると説明した。これが「政治の不安定化につながるリスクもある」とみている。
NHKの最新の世論調査によると、石破茂内閣の支持率は前回調査(2月)から8ポイント低下し36%となった。優先課題として物価高対策が上位に挙がっている。
これは参院選を夏に控える石破首相にとって好ましくない状況だ。昨年10月の衆院選で少数与党となった石破内閣が挽回するには、有権者の声にもっと応えられることを参院選までに示す必要がある。
石破政権にとって、日銀の利上げで最も痛みを伴う副作用の一つは、政府支出に制限がかかる可能性があることだ。
日銀が政策金利を引き上げ、大規模な国債買い入れの減額を進める中、長期金利の指標となる10年物国債利回りは17年ぶりの高水準に急騰。金利の上昇は、政府の国債利払い費が膨らむ可能性を意味する。
財務省が1月に示した試算によると、国債の元本返済と利払い費を合わせた国債費は28年度に35兆3000億円と、25年度比で約25%増が想定されている。国債費は歳出全体の約4分の1を占めている。
BNPパリバ証券グローバルマーケット統括本部副会長で、経済財政諮問会議の議員を務める中空麻奈氏は、「金利が上がれば、今後の債券発行の利払いが増えることも道理で、利払い費だけでも雪だるま式に債務が膨張する仕組みは再度、理解する必要があるのではないか」と述べた。
関連記事:日本経済の大転換が社債市場を活性化、金利上昇に備え企業急ぐ
今のところ、金融機関の顧客獲得競争を背景に住宅ローン金利の引き上げが遅れているため、住宅所有者には金利上昇の痛みがまだ及んでいない。国内の住宅ローンの約75%は変動金利型で、日銀の短期金利などを基に決められる短期プライムレートに連動している。だが、大手行が提示している変動金利は最低で0.345%と、日銀の政策金利である無担保コール翌日物金利を下回っている。
不動産経済研究所によると、首都圏で発売された新築分譲マンションの平均価格は、24年に前年比3.5%下落。過去6年間で40%近く上昇していた。これは、金利上昇が見込まれる中、住宅市場が既に冷めつつあることを示している。
日銀の調査によると、国民の多くは依然として金利は低すぎるとみている。一方、金利が高すぎると考える人の割合は増えており、現時点で回答者全体の約5分の1程度を占める。金利上昇に伴って消費者の債務や企業倒産件数は増加。東京商工リサーチによると、24年度上期(4ー9月)の倒産件数は10年ぶりに5000件を超えた。
埼玉県で精密金属加工事業を営む野沢茂さんは、「預金などは良い部分もあるかもしれないが、事業者でみると良いことはあまりない」と指摘。自らの会社に借り入れはないとした上で、「金利が高くても見通しがついていれば思い切ってできるが、そうではない」と語った。
原題:Banks Boom And Shoppers Scrimp a Year After BOJ’s Rate Pivot(抜粋)